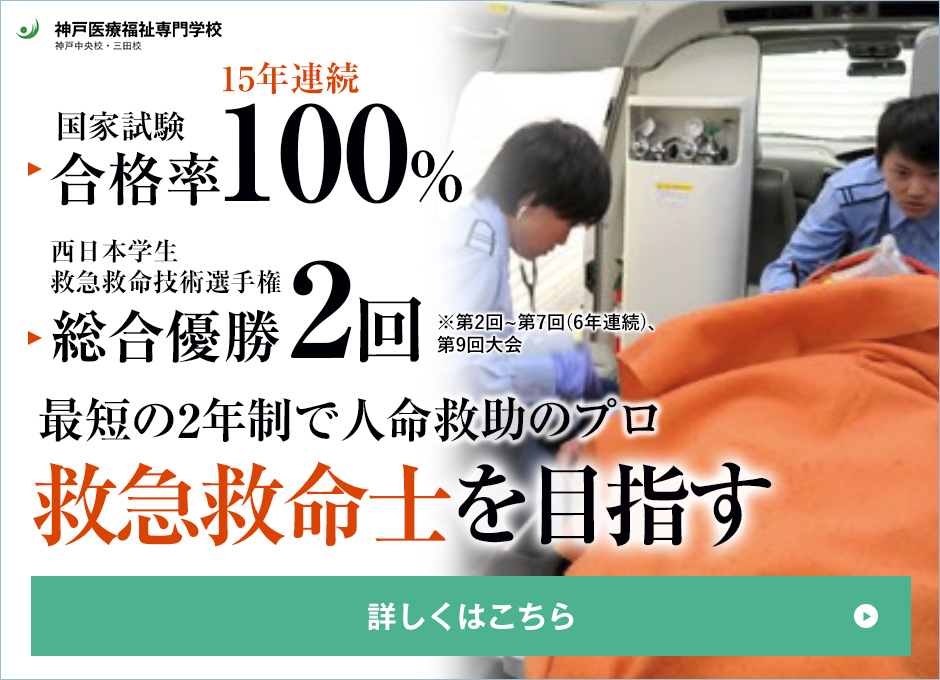消防士といえば男性のイメージが強い職業ですが、女性でもなれるのでしょうか?
特に救急救命士の資格取得を目指す女性のなかには、仮に消防士となれたとしても、仕事内容に制限はあるのか、子育てと仕事は両立できるのかなどの不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、現在活躍している女性救急救命士の数や仕事内容、働き方などについて解説します。
男性社会に飛び込むことに不安を感じている方や、救急救命士を目指すかどうか迷っている方はぜひ進路選びの参考にしてみてください。
目次
消防職員や救急救命士として活躍している女性の人数や割合って?
救急救命士の資格取得者の多くは、消防署で消防士として働くことになります。
総務省消防庁の「令和5年版 消防白書」によると、2022年4月1日時点の女性消防吏員数は5,341人でした。
これは全体の3.4%を占め、2015年の3,850人と比較して増加しています。
また、2022年度の救急救命士国家試験合格者は男性が2,718人、女性は261人でした。
これは全体の約9.2%を占め、2015年の女性合格者237人と比較して0.5ポイント増加しています。
このように近年、女性の救急救命士は増加傾向にありますが、全国的には男性が多いのが現状です。
出典
※1 第46回救急救命士国家試験の合格発-厚生労働省表
※2 第38回救急救命士国家試験の合格発表
※3 女性消防吏員の活躍推進について-総務省-消防庁
女性消防職員・救急救命士の強みや注意点

多くの救急救命士が就職することとなる消防署は、男性の割合が高い職場です。
そのなかで女性の救急救命士が働くことには、以下のような強み・弱みが存在します。
傷病者の気持ちに寄り添うことが得意
女性救急救命士は、相手の気持ちに寄り添う能力に長けていると言われています。
女性ならではの柔らかく親しみやすい雰囲気は、悲しみを抱える傷病者の心を落ち着かせ、不安を和らげるのに大いに役立ちます。
実際に、身体的な接触が多い医療現場では、精神的な負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐ観点から、同性による介助が望ましいとされています。
特に女性の傷病者にとって、同性の救急救命士が救護にあたってくれることは、大きな安心感につながります。
これは、傷病者が安心して治療を受けられる環境を整える上で非常に重要な要素です。
また、婦人科系の疾患や予期せぬ出産、あるいは小さな子どもの救護・対応といった場面においても、女性救急救命士の需要は高まっています。
これらの状況では、性別による配慮が特に求められるため、女性救急救命士が持つ専門知識と共感力は、傷病者とその家族にとってかけがえのない支えとなるでしょう。
このように、女性救急救命士は、その特長を活かし、多岐にわたる場面で重要な役割を担っています。
女性が消防職員・救急救命士を目指す時の注意点
女性が消防職員や救急救命士を目指す上で特に重要なのは、体力面の準備です。
救急救命士の現場では傷病者の搬送や機材の運搬など、男性と同等、あるいはそれ以上の力が求められる場面が多く、筋力で劣る女性は意識的なトレーニングで体力を維持・向上させる必要があります。
これは、採用後の研修で体力は向上しますが、基礎的な体力が不足していると、業務の継続が困難になる可能性があるためです。
学習と並行して、日頃から体力トレーニングを始めることが大切です。
また、消防士は地方公務員であるため、採用試験には年齢制限が設けられています。
自治体によって上限年齢は異なりますが、多くの場合26歳から30歳未満とされているため、志望する自治体の採用情報を事前に確認し、受験資格を満たしているか確認しておくことが重要です。
年齢制限は、キャリアプランを立てる上で考慮すべき重要な要素となります。
女性の消防活動・救命活動に制限はある?
日本で女性消防士が初めて誕生したのは1969年です。
当時は、身体的な違いや法律上の制約から、男女間で職務内容に大きな差がありました。
しかし、2004年に消防庁から「女性消防職員の採用および職域拡大に関する通知」が発出されたことで状況は大きく変わりました。
この通知により、女性の消防活動における制限は、「重量物を取り扱う業務」や「有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務」のごく一部に限定されることになりました。
これ以外の職域においては、男女による差がほとんどなくなり、女性消防士の活躍の場は大幅に拡大しています。
これまでは防火指導や予防、救急といった分野に配属されることが多かった女性消防士ですが、現在では個人の意欲と能力次第で、災害現場で人命救助を行う救助隊員として活躍することも可能になりました。
また、119番通報の受信や無線通信を行う通信指令業務、消防車両の運転や操作を行う機関員として働く女性消防士も増えており、その活躍は多岐にわたります。
女性が消防職員として働く不安とその解消
女性が消防職員として働くことに対して不安を感じる方は少なくありませんが、近年は女性の採用数が着実に増加しており、それに伴い職場環境の整備も進んでいます。
特に体力面での不安は、採用後の研修や訓練で専門的な技術とともに向上させることが可能です。
しかし、日頃からの基礎的な体力の維持・向上は、怪我の防止や業務遂行能力の安定に不可欠であり、継続的なトレーニングが重要となります。
男性が多い職場環境であることに対しては、女性の意見や要望を伝えるための相談窓口やハラスメント研修の実施など、心理的な安全性も確保できるような働きやすい環境づくりが進められています。
これにより、女性特有の身体的・精神的な不安が軽減され、安心して職務に専念できるようサポート体制が整えられているのです。
女性消防職員の増加は、男性中心であった職場の多様性を高め、より柔軟で質の高いサービスの提供にも繋がっています。
女性も消防職員として働く時代!
かつては男性の仕事というイメージが強かった消防職員ですが、近年は女性の活躍も目覚ましく、その割合は増加傾向にあります。
総務省消防庁は、2023年時点で約3.5%である女性消防吏員の割合を、2028年度までに5%へ引き上げる目標を掲げており、女性の採用を積極的に推進しています。
これは、地域住民へのサービス向上だけでなく、多様な視点を取り入れることで組織を強化していく狙いがあります。
現状、全国にいる約16万6千人の消防職員のうち、女性消防職員は約6千人で、約3.5%と低い割合にとどまっています。
しかし、内閣府は男女共同参画社会の実現に向け、女性職員の割合を5%に促進させる取り組みを進めており、これは少なくとも2千人以上の女性がこれから新たに採用されることを意味します。
例えば、大阪府下の24ある消防本部のうち、女性消防職員が5%以上を占めているのは、わずか4か所のみです。
この状況は、女性が消防職員として活躍するチャンスが大きく広がっていることを示しており、もはや珍しいことではなく、時代が求めていることと言えるでしょう。
各消防本部では、女性の受験者増加に向けた取り組みや、女性専用施設の整備など、働きやすい環境づくりも進められています。
女性が消防職員・救急救命士を目指す方法
女性が救急救命士を目指す方法は、男性と変わりません。
高校卒業後に専門学校や大学で学び、救急救命士国家試験を受験して免許を取得。
その後、消防官採用試験を受けて合格することで消防機関で働けるようになります。
また、先に消防官採用試験を受けて消防士としての経験を積んでから、救急救命士養成所で学び、救急救命士国家試験を受験することも可能です。
専門学校などで学んで救急救命士になるルート
高校を卒業後、専門学校などで救急救命士に必要とされる知識や技術を学ぶルートは、比較的スムーズに資格取得を目指せる方法です。
文部科学大臣指定の大学、短期大学、専門学校、あるいは都道府県知事が指定する救急救命士養成所といった特定の学校で2年以上修学し、卒業することで、国家試験の受験資格が得られます。
その後、救急救命士の国家試験と、消防機関への採用試験に合格することで、晴れて救急救命士として活躍できるようになります。
このルートの利点は、消防士として一定の実務経験を積む必要がないため、早期に救急救命士を目指せる点です。
また、学業に専念できるため、効率的に学習を進められます。
消防職員になった後で救急救命士を取得するルート
消防職員になった後で救急救命士を取得するルートは、まず消防の公務員試験に合格し、消防職員として採用されることが最初の条件です。
採用後、救急隊員として5年以上の実務経験を積むか、または2,000時間以上の実務経験を積む必要があります。
加えて、所属する消防本部からの推薦を得ることで、救急救命士養成所に入所できます。
養成所では半年以上の期間をかけて救急救命士に不可欠な知識と技術を習得し、卒業することで国家試験の受験資格が得られます。
最終的に国家試験に合格することで、晴れて救急救命士として活動することが可能になります。
女性が消防職員や救急救命士を目指すきっかけ
救急救命士を目指すきっかけとしては「被災地で活躍している姿を見て憧れるようになった」「火災・風水害から地域の人を守りたい」などがよくあげられます。
一般的に、女性が活躍しやすい医療職種といえば看護師が思いつきますが、両者の仕事内容は大きく異なります。
看護師は医療機関で治療やそのサポートをするのが仕事、それに対して救急救命士は傷病者を救急救命処置しながら医療機関まで搬送するのが仕事です。
どちらも傷病者のために働く仕事ですが、実際に救急救命士として活躍している方は、緊急事態に真っ先に駆けつけ、命の危険が迫る人を助けることができる点にやりがいを感じることが多いようです。
女性消防職員・救急救命士ならではの働き方
これから救急救命士を目指そうと考えていても、男性社会といわれる救急の現場で働くことに不安を感じている方は多いでしょう。
そこで、現役の女性救急救命士は実際どのように働いているのか、雇用形態や妊娠・出産など女性ならではのライフイベントとの付き合い方について解説します。
消防職員は地方公務員
救急救命士の資格取得者は、各自治体の消防署に勤務し、消防士として働くのが一般的です。
消防士は市町村の地方公務員にあたるため、給与や有給、福利厚生などの待遇は充実しているといえるでしょう。
実際に、消防士の平均年収は約635万円、月収に換算すると約34万円です。
これは、日本人の平均年収である約433万円と比べると高い水準にあるといえます。
出産や子育てに関する休暇や制度
地方公務員である救急救命士には、産休や育休などの制度が整備されています。
産休中の給与については自治体により異なり、満額支給されない場合もありますが、ボーナスは満額支給されることがあります。
また、育児休業中は原則として給与は支給されませんが、育児休業手当金を受け取ることが可能です。
育児休業手当金の支給額は、育児休業開始から180日目までは標準報酬日額の67%、181日目以降は50%となります。
復帰後は、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、「地方公務員の育児休業等に関する法律」に基づき、短時間勤務制度や部分休業制度が設けられています。
短時間勤務制度は、子どもが小学校に入学するまでの期間、1日の勤務時間を短縮できる制度です。
部分休業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、正規の勤務時間の始めまたは終わりに、1日2時間を超えない範囲で勤務しないことができる制度です。
これらの制度を活用することで、子育てと仕事の両立を図ることができます。
仕事と子育ては両立できる?
消防士は原則24時間勤務です。
時間的にも体力的にも子育てとの両立は厳しいため、現場の最前線で働き続けるには、家族のサポートを得るなど周囲の協力が必要となります。
消火活動、救急活動、救助活動などの業務だけが、消防士の仕事ではありません。
通報を受けた際に応急処置を口頭で伝える通信司令員や、火災の原因調査や消防用の設備の設置・維持を検査する予防係。
保育園・幼稚園児に火災にあった時どうすれば良いか教える幼児防火教育など、その他にもさまざまな仕事があります。
子育て中は少し現場を離れて、こういった業務に従事するのも手段の一つといえるでしょう。
消防職員・救急救命士として活躍できる方の特徴
消防職員や救急救命士として活躍するために、性別は関係ありません。
重要なのは、職務を遂行するために必要な特性を備えていることです。
具体的には、日々の業務で求められる体力を備えていることが不可欠です。
体力がある方
救急救命士の仕事は、傷病者の搬送や機材の運搬など、身体的な負荷が大きい業務を伴います。
そのため、性別にかかわらず強靭な体力は必須です。
特に、女性は男性に比べて筋力面で劣る場合が多いため、日頃から意識的にトレーニングを行い、体力を維持・向上させる必要があります。
採用後の研修で体力は向上しますが、基礎的な体力が不足していると、実際の現場で業務を継続することが困難になる可能性があるため、学習と並行して体力トレーニングを始めることが大切です。
責任感・使命感が強い方
救急救命士は人の命に関わる重要な職務であり、強い責任感と使命感が求められます。
傷病者の命を救うという確固たる動機を持ち、自らが助けるという強い気持ちで業務に臨むことが不可欠です。
緊急時には医師の指示に従うだけでなく、時には自身の判断で迅速な処置を行う必要もあります。
一刻を争う現場において、冷静かつ的確な判断が求められるため、強い責任感と使命感を持って仕事に取り組める方が活躍できます。
勤勉な方
救急救命士は、日々の学習や訓練を通じて、知識と技術を常に更新していくことが不可欠です。
人の命と向き合う仕事であるため、基本的な事柄はもちろん、応用的な内容まで幅広く理解し、どのような状況でも最善の判断と対応が求められます。
そのため、待機時間中に訓練を行ったり、医療機器や最新の医療技術に関する情報を積極的に収集したりするなど、常に学び続ける意欲と勤勉さが重要な資質となります。
冷静沈着な方
救急救命士には、常に冷静な判断が求められます。
緊急性の高い現場では、パニックに陥ることなく、適切な状況判断と迅速な行動が不可欠です。
重篤な傷病者に対応する場面では、精神的な動揺が許されません。
また、さまざまな医療機器を状況に応じて使いこなし、的確な処置を行う知識と技術も求められます。
女性の消防職員や救急救命士がより活躍するために
女性が男性の多い職場に飛び込むのは少々勇気がいるかもしれませんが、現代では男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな取り組みが進んでいます。
2023年1月に消防庁は「女性消防吏員の活躍推進について」という資料を発表し、女性消防士の採用拡大や環境整備に向けた積極的な取り組みを各自治体へと要請しました。
具体的には、全国における女性消防士の割合を2028年度まで5%まで引き上げることを目標に、インターンシップの実施やポスター、パンフレットの作成、さらに各消防署所に女性専用の仮眠室や浴室、トイレを整備するよう財政措置を実施しています。
これから消防職員・救急救命士を目指す女性の方へ
近年、女性救急救命士の活躍の場は大きく広がっており、これからこの道を目指す方にとって絶好の機会が訪れています。
かつては男性中心の職場というイメージが強かった消防機関も、女性の積極的な採用と働きやすい環境整備を推進しており、その目標達成に向けた取り組みは加速しています。
職場での性差は少なくなり、体力的なサポート体制も整いつつあります。
まとめ~消防職員や救急救命士は女性でもなれる?~
近年、女性の救急救命士は増加傾向にあり、働きやすい環境が整備されつつあります。
総務省消防庁は、2028年度までに女性消防吏員の割合を5%に引き上げる目標を掲げるなど、女性の積極的な採用と環境整備を推進しているため、女性が消防職員や救急救命士を目指すことは、もはや珍しいことではありません。
社会全体で女性の活躍が求められている時代において、体力的な不安やライフイベントとの両立に関する懸念も、短時間勤務制度や部分休業など、さまざまなサポート体制の拡充により解消されつつあります。
自分のやりたいことや、人命救助のプロフェッショナルとして社会に貢献したいという強い意志があるなら、諦めることなく夢を追いかけることが重要です。
神戸医療福祉専門学校救急救命士科は、関西唯一の2年制専門学校として、最短で救急救命士の資格取得を目指せるカリキュラムを提供しています。
現役で活躍する救急救命士からの徹底した指導に加え、地元消防本部の協力による実践的な実習訓練も実施されており、現場で即戦力となる高度な知識と技術を習得することが可能です。
また、16年連続で国家試験合格率100%を達成しているほか、消防職員採用試験対策にも力を入れており、高い就職率を誇ります。
同じ夢を持った仲間とともに、人命救助のプロフェッショナルを目指す第一歩として、まずは資料請求やオープンキャンパスへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
救急救命士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の救急救命士科では、国家試験の合格率は、15年連続で100%!(※2009〜2023年度実績)
最短の2年制で人命救助のプロを目指す! 2年間という限られた期間で、消防や救急救命の現場に即戦力となる技術力が身に付けることができます。
国家試験対策は1年次から実施され、習熟度別に学習をサポート、学生一人ひとりの状況を把握し、国家試験対策担当の教員との情報共有を徹底し、学生が主体的に取り組めます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや救急救命士の詳細情報をご覧ください。
また、救急救命士科の学科の詳細を知りたい方は「救急救命士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「神戸医療でのシミュレーション実習のおかげで実践力が身につき、どんな現場にも柔軟に対応できている」(兵庫県立播磨南高等学校出身)
「現場をリアルに想定したシミュレーション実習を数多くこなせたことが、とても役立っている」(兵庫県立北条高等学校出身)
「学校で学んだシーンに遭遇する場面もある」(鳥取県立八頭高等学校出身)
「採用後は即戦力の隊員として隊長指揮下に入りました。」(愛媛県立今治工業高等学校出身)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!