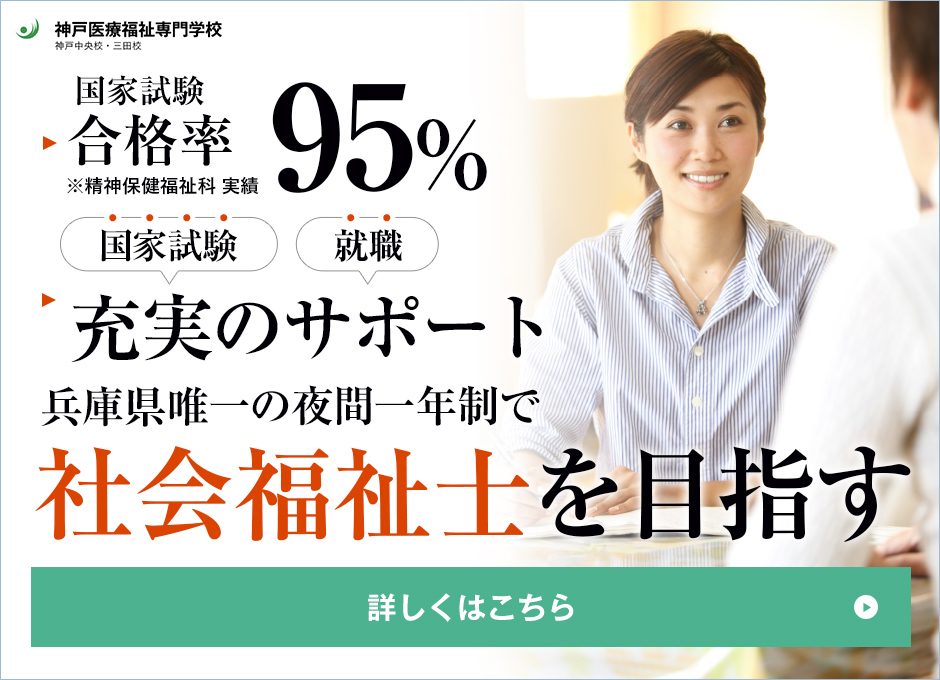かつては「不治の病」といわれ、完全に回復することが困難と考えられていた統合失調症。
しかし、近年では適切な治療を継続することによって、症状の軽減や回復が可能であることがわかっています。
そこで今回は、統合失調症の症状や回復までの流れ、具体的な治療法を解説します。
「自分自身や家族、身近な人が統合失調症と診断された」という方はもちろん「精神疾患に苦しんでいる人の助けとなれるような職業に就きたい」という方はぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
統合失調症は治る?
精神疾患の一つである統合失調症は、かつては「完治が難しい」「進行性の病気である」などといわれ、基本的に回復しにくい病気であると考えられていました。
しかし、研究が進んだ現代では、統合失調症は決して不治の病ではなく、適切な治療によって回復することがわかっています。
また、完全に回復できなかった場合でも、服薬などで症状をコントロールすることで、普通の人と同じように社会生活を送っている人もたくさんいます。
再発のリスクと主な原因
「統合失調症は完治が難しい」といわれる一因は、再発や症状の悪化を繰り返す患者が多いことにあります。
たしかに統合失調症は再発リスクの高い病気ですが、その原因のほとんどが自己判断による治療の中断だといわれています。
統合失調症を回復させるには、服薬や定期的な受診を勝手に中断せず、専門家の指示にしたがって適切な治療を継続することが重要です。
そもそも統合失調症とは

統合失調症とは、考え方や気持ちがまとまらなくなる状態が続く精神疾患です。
日本における統合失調症の患者数は約80万で、その多くが思春期や青年期に発症します。100人に1人の割合で発症すると考えると、決して珍しい病気ではないといえるでしょう。
統合失調症の症状
統合失調症の症状は主に、幻覚と妄想です。
実際にはないものが見えたり聞こえたりするほか、嫌がらせをされていると感じるなどの被害妄想、テレビなどのメディアが自分に関する情報を流している、盗聴されていると思い込んだりする関係妄想などが挙げられます。
統合失調症をはじめとする精神疾患では、このように健康な状態のときにはなく、病気によってあらわれる症状を陽性症状といいます。
反対に病気が発症することで、健康な状態のときにはあったものが失われる陰性症状としては、感情の鈍麻や意欲の欠如、自閉(引きこもり)などが挙げられます。
また、一部の患者には記憶力や注意力、集中力、判断力の低下など、認知機能にも障害があらわれることから、高齢者が発症した場合「初めは認知症を疑ったが、実は統合失調症だった」などというケースもあるようです。
統合失調症が発症する原因
統合失調症が発症する原因は、まだはっきりとわかっていません。
しかし、現段階では仕事・人間関係のストレスや遺伝子などが影響して、脳の機能に問題が発生することで発症すると考えられています。
統合失調症の検査・診断方法
統合失調症を診断するための特別な検査はありません。
基本的には、一定期間にわたって症状の経過を観察し、評価した結果に基づいて診断が下されます。
ただし、脳の感染症やけが、腫瘍、自己免疫疾患や薬の副作用など、同様の症状があらわれる原因と区別するために、脳の画像検査や病歴の聞き取りなどが行われる場合もあります。
統合失調症が回復するまでの流れ

統合失調症の症状は主に、前兆期、急性期、回復期、安定期にわかれます。
前兆期とは、幻覚や妄想など統合失調症の代表的な症状があらわれる前の段階です。人によっては、不眠や不安、神経過敏などの身体症状があらわれる場合があります。
急性期とは、幻覚や妄想などの陽性症状や、感情の鈍麻や意欲の欠如、自閉(引きこもり)などの陰性症状が顕著にあらわれる時期です。
適切な治療を受け、回復期に入るとしだいに陽性症状が軽減していきますが、このときに自己判断で治療を中断すると急性期に逆戻りしてしまうため注意が必要です。
適切な治療を継続すると、安定期となり安定した生活を送れるようになりますが、一部陰性症状が残る場合もあります。
統合失調症の治療方法
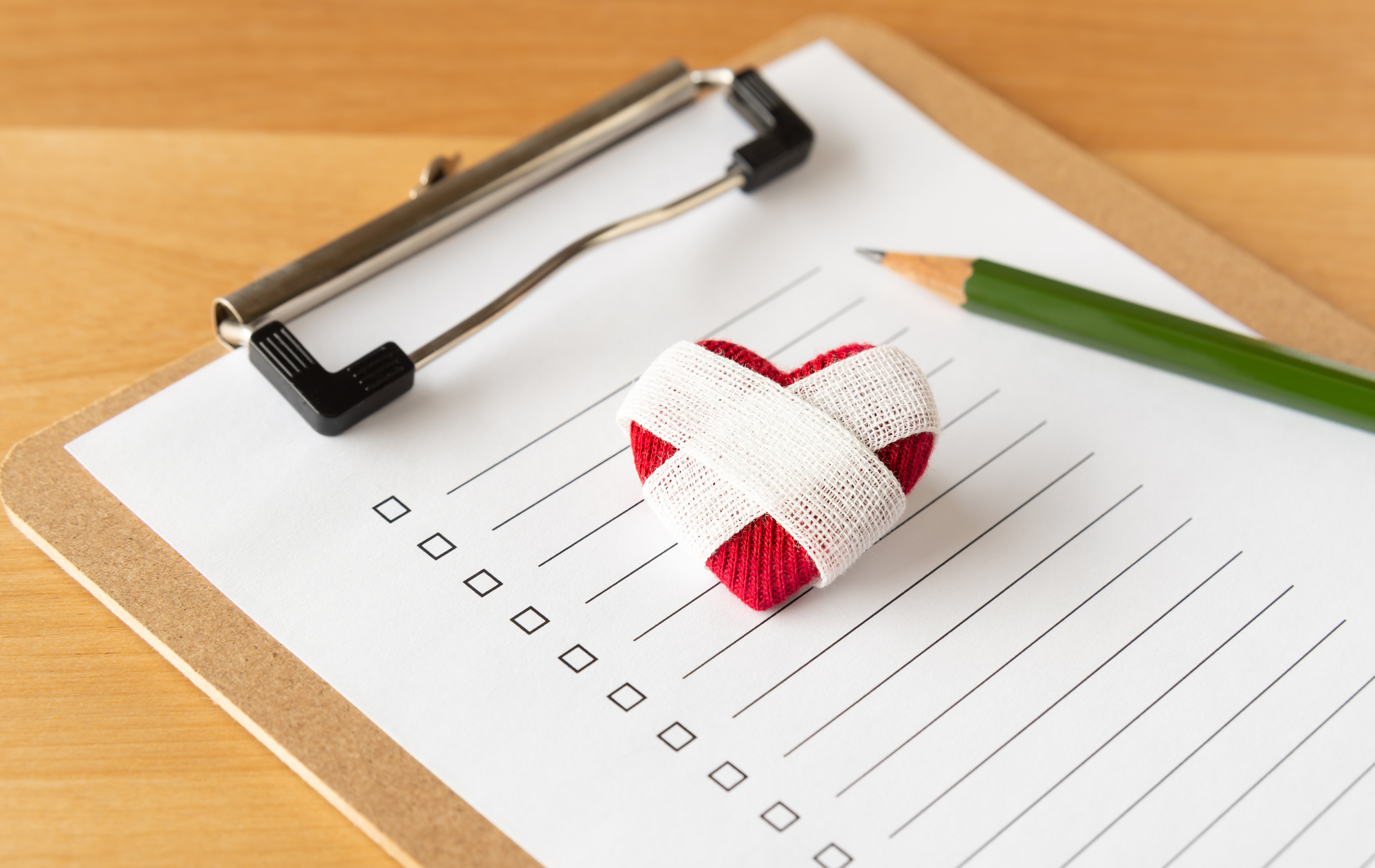
統合失調症の主な治療方法としては、抗精神病薬などを使った薬物療法と、リハビリテーションなどの非薬物療法があります。
薬物療法
統合失調症は、脳内で情報を伝える神経伝達物質のバランスの崩れが原因の一つとして有力視されています。
その神経伝達物質であるドーパミンの活動を弱める働きを持つのが、抗精神病薬です。抗精神病薬でドーパミンの活動を軽減させることは、興奮や妄想など精神疾患の症状の改善に効果が期待できます。
このような抗精神病薬をはじめ、統合失調症の患者には症状に合わせて抗うつ薬や抗不安薬、睡眠薬などが主に処方されます。
抗精神薬は、いわゆる飲み薬である経口剤が主流です。しかし、服薬回数が多い、飲み忘れがあるなどデメリットがあることから、最近では月に1〜2回注射を打つだけでよいLAI(持続性注射剤)も注目されています。
非薬物療法
統合失調症の非薬物療法としては、じゅうぶんな休養や、発症の原因となっているストレスを取り除く環境調整、心理社会療法などが挙げられます。
心理社会療法とは、そのような人たちが日常生活や社会生活を送れるよう、思考力・意欲の改善をめざすために行われるリハビリテーションが叩きつけられます。
幻覚や妄想などの症状が悪化すると、抑うつや自閉(引きこもり)の症状があらわれ、日常生活や他者とのコミュニケーション、社会復帰が困難になります。
そのような人たちが日常生活や社会生活を送れるよう、思考力・意欲の改善をめざすために行われるのが心理社会療法です。
代表的な心理社会療法としては主に以下が挙げられます。
- 心理教育
- 作業療法
- 社会生活技能訓練(SST)
- 就労支援
心理教育
統合失調症の症状や治療法などについて正しい知識を身につける方法です。
病気そのものについて理解を深めることで、困りごとへの対処法や治療への前向きな姿勢を身につけます。
作業療法
料理や手芸、折り紙やレクリエーションなどさまざまな作業活動を通じてこころとからだのリハビリテーションを行う方法です。
症状に応じた作業活動を選択することで、体力や他者とのコミュニケーション、自己肯定感など、社会復帰に必用なさまざまな能力の回復を図ります。
>>兵庫県で唯一4年制の専門学校 神戸医療福祉専門学校 三田校 作業療法士科
社会生活技能訓練(SST)
上手な気持ちの伝え方やストレスの対処法など、社会的なスキルを身につけるためのトレーニングです。
一般的には、5人〜8人程度の少人数のグループで行われ、自分ができるようになりたいと思うことや社会生活の中でうまく人と関わる方法を練習します。
就労支援
症状が回復し、日常生活が送れるようになった場合の就職活動に関するサポートです。体調の変化や能力に合わせて無理なく社会復帰できるよう、就労に関する相談に乗ったり、援助付きの雇用を紹介したりと、その人にとって必要な就労サポートが受けられます。
障害のある方の日常生活や社会復帰をサポートする「社会福祉士」とは?

統合失調症をはじめ、こころやからだにさまざまな障害を抱えている人の自立した生活をサポートする資格としては、社会福祉士が挙げられます。
社会福祉士とは、ソーシャルワーカーとも呼ばれる社会福祉の専門職です。
具体的には、身体的・精神的・経済的などさまざまな面で社会生活にハンディキャップを負っている人の相談援助や支援を行います。
社会福祉士は高齢者福祉や児童福祉、医療などさまざまな現場で働くことが可能ですが、障害者福祉の現場では主に職業指導員や生活支援員、就労支援員などとして活躍しています。
職業指導員は主に履歴書の書き方指導や面接練習など就職活動の支援を、職業指導員は企業で働くために必要な知識や技術を身につけるための訓練を行うことが仕事です。
生活支援員は、障害福祉施設に入所してる人の日常生活を支援することがメインの業務となります。
このように、その業務内容は職種や活躍する施設によって異なりますが、いずれも障害がある方の自立した生活や社会復帰をサポートする仕事です。
「社会的にハンディキャップを抱えている人の力になりたい」「障害の有無に関わらず、ともに
生きていける社会をつくりたい」という方はぜひ、社会福祉士の資格取得を検討してみてはいかがでしょうか。
神戸医療福祉専門学校 中央校 社会福祉士科は、夜間1年間で社会福祉士の資格取得がめざせる専門学校です。
平日の授業時間は18時10分〜のため、日中は仕事がある方でも無理なく通学できます。
まとめ
統合失調症の具体的な治療法としては、薬物療法や各専門家によるリハビリテーションをはじめとした非薬物療法があります。
統合失調症は、自己判断で服薬や治療を中断せず、これらの専門家の指示に従って適切な治療を続けていれば、回復が目指せる病気です。
一部陰性症状が残ったとしても、服薬や症状、ストレスなどとうまく付き合っていく方法を見つければ、普通の人と同じような社会生活を送れるでしょう。
精神障害やこころの病気を抱える人の自立した生活や社会復帰を支援する職種の力も借りながら、無理せず、自分らしく生きられる道を探しましょう。
社会福祉士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の社会福祉士科では、夜間1年でスクールソーシャルワーカーはもちろん、その他医療や福祉の現場でソーシャルワーカーとして幅広く活躍できる社会福祉士の資格取得が目指せます。
夜間制で授業時間は基本的に18時10分〜のため、日中は仕事で忙しい社会人の方でも無理なく通学できます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや社会福祉士科の詳細情報をご覧ください。
また、社会福祉士科の学科の詳細を知りたい方は「社会福祉士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。