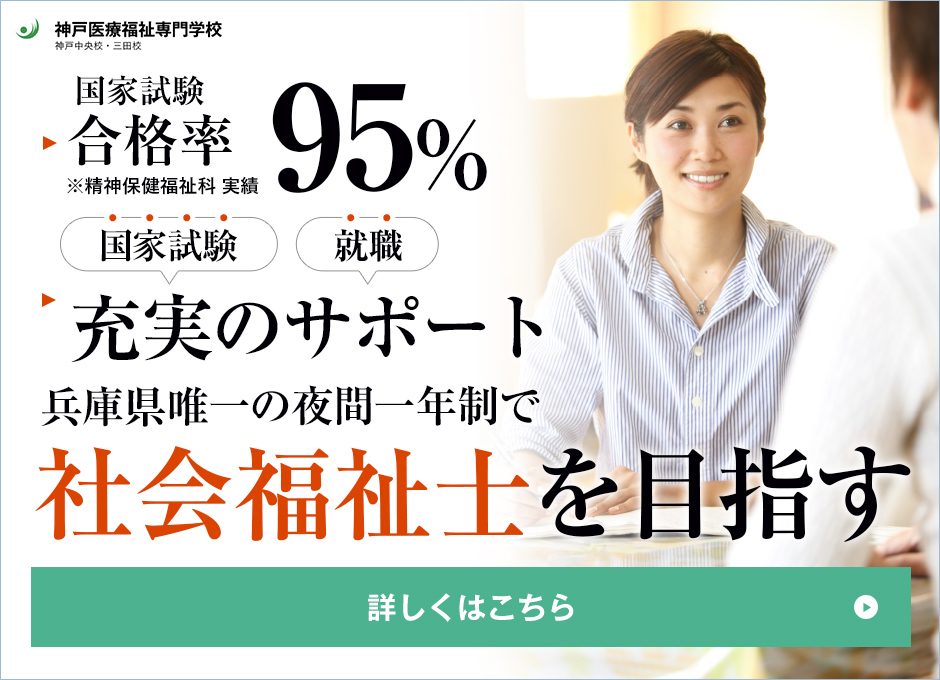社会福祉士が他の福祉系国家資格と比べて好待遇である主な理由としては、社会的な需要の高まり、資格手当の支給、そして昇進につながる可能性が挙げられます。
まず、日本が少子高齢化社会に突入する中で、高齢者福祉施設や障害者福祉施設、医療機関、学校、行政機関など、多岐にわたる分野で社会福祉士の専門性が強く求められています。
特に地域包括ケアシステムの導入により、包括的な支援体制の中核を担う存在として、社会福祉士の役割は非常に重要です。
さらに、社会福祉士は国家資格であり、その専門性の高さが評価され、勤務先によっては資格手当が支給されることがあります。
実際に、資格手当をもらっている社会福祉士の割合は37.4%にのぼり、その平均月額は1万827円です。
中には2万円から3万円以上の手当がつくケースもあり、これらが給与水準を高く保つ要因の一つとなっています。
また、社会福祉士の資格取得は、専門的な知識と能力を勤務先にアピールできるため、昇進の判断材料となることがあります。
一般職員から主任、相談部門の責任者、さらには施設長や事務所管理者へとキャリアアップするにつれて、年収の向上も期待できるでしょう。
このように、需要の高さ、資格に対する手当、そしてキャリアパスにおける昇進の機会が、社会福祉士の好待遇につながっています。
目次
社会福祉士の給料・平均年収はいくら?
社会福祉士の平均年収は、厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、常勤で働く場合35万2,560円です。
これを年収に換算すると約423万720円となります。
ただし、これはベースアップなどの支援加算を取得している事業所に常勤で勤務する社会福祉士の給与であり、国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査結果」による日本の平均年収458万円と比較すると、やや低い水準です。
一方、非常勤で時給制の社会福祉士の平均給与は13万4,350円で、常勤と比較して22万円ほど低い水準です。
しかし、同じ非常勤で働く介護職員全体の平均給与が12万330円であることから、非常勤の社会福祉士の給与水準は介護職員全体と比較すると高いと言えるでしょう。
また、社会福祉士の平均年収は、男女別や年齢、勤務先によっても変動します。
令和2年度の調査では、社会福祉士全体の平均年収は403万円でした。
男性の平均年収は473万円、女性は365万円と、男女で差が見られます。
これは、女性が非正規雇用の割合が高いことが一因と考えられます。年齢別では、経験年数とともに給与は上昇し、50代前半でピークを迎える傾向にあります。
福祉系の仕事の中では、やや年収が高い
福祉系の仕事において、社会福祉士の平均年収は比較的高めの傾向が見られます。
令和2年度の調査によると、社会福祉士の平均年収は403万円と報告されています。
これは、同じく国家資格である介護福祉士の当時の平均年収292万円と比較して、社会福祉士のほうが高い傾向にあることを示しています。
この差の一因として、介護福祉士にはパートや派遣として働く方が多いことが挙げられます。
しかし、正社員として働いた場合でも、社会福祉士の仕事は高年収につながりやすい傾向にあると言えるでしょう。
社会福祉士は、身体上または精神上の障がいがある方や、その他の理由で日常生活に支障がある方の福祉に関する相談に応じ、助言や指導、関係機関との調整など、専門的な知識と技術で援助を行う仕事です。
一方、介護福祉士は、介護が必要な方への身体介護や生活援助を直接行い、利用者やその家族への助言や指導も担当します。
このように、社会福祉士は相談業務を、介護福祉士は直接的な介護サービスを主な仕事内容としている点で違いがあります。
ただし、働き方によっては社会福祉士より介護福祉士のほうが年収が高いケースも存在します。
例えば、社会福祉士が日勤のみで働くのに対し、介護福祉士が夜勤を行う場合などがこれに該当します。
介護福祉士の平均年収も年々増加傾向にあり、令和6年度の調査では月給・常勤の介護福祉士の平均年収は約420万円との報告もあります。
社会福祉士の平均年収は、年代別に見て50代前半でピークを迎える傾向があり、安定した収入を得られる点が魅力です。
資格手当が支給される職場も増えており、高年収を目指せる資格と言えるでしょう。
職場や業務内容によって給料は変わる
社会福祉士の給料は、勤務する職場や業務内容によって大きく変動する特徴があります。
この資格は、介護や障害者福祉施設以外にも、病院や児童相談所、社会福祉協議会など幅広い分野で需要があり、働く場所によって平均年収が異なります。
特に、公務員として働く場合は給与水準が高い傾向にあります。
資格を活かして、自身の希望する給料やキャリアパスに合った職場を見つけることが重要です。
社会福祉士の職場は多岐にわたり、それぞれで平均年収に違いが見られます。
例えば、病院や診療所で働く社会福祉士の平均年収は、約400万円が相場とされています。
ここでは患者の悩み相談や地域医療連携などが主な業務です。
一方、児童相談所で働く社会福祉士は、平均年収が532万円と比較的高い水準です。
これは、児童福祉司として生活に困難を抱える子どもや保護者をサポートする公務員としての働き方が多いためと考えられます。
また、社会福祉協議会では、公務員に準じた給与体系がとられていることが多く、年収は勤続年数や経験に応じて500万円から700万円程度まで見込める場合があります。
地域によっては、関東地方の社会福祉士の平均年収が338万円と最も高く、九州地方が286万円と低い傾向にあるなど、地域差も存在します。
これらの情報を参考に、自身の目指す給料やキャリアを実現できる職場を選択することが重要です。
社会福祉士の年収を左右する要因
社会福祉士の年収を左右する要因としては、主に以下の4つが考えられます。
年齢
地域
個人の経験・スキル
勤務先
年齢・経験年数
社会福祉士の年収は、他の多くの職業と同様に、年齢と経験年数に大きく影響されます。
厚生労働省が実施している「賃金構造基本統計調査」によると、社会福祉士を含む「社会福祉専門職」の平均給与は、経験を重ねるごとに上昇する傾向が見られます。
具体的には、20代前半の経験年数1~4年目の平均給与が284万3,700円であるのに対し、50代前半の経験年数30~34年目では442万7,200円とピークを迎えます。
このデータから、長期的なキャリア形成において年収アップが期待できることがわかります。
年収が年齢とともに増加する背景には、社会福祉士としての専門知識やスキルが経験年数を重ねることで深まり、より複雑なケースに対応できるようになる点や、リーダーシップを発揮して役職に就く機会が増える点が挙げられます。
例えば、主任や相談部門の責任者、施設長といった管理職に昇進することで、役職手当が支給され、大幅な収入アップにつながる可能性があります。
しかし、50代後半以降になると、年収は下降傾向に転じることがあります。
これは、多くの企業で定期昇給がなくなることや、役職から離れることなどが主な理由として考えられます。
このように、社会福祉士の年収は年齢と経験年数に密接に関わっており、キャリアプランを考える上で重要な要素となります。
地域
給与水準や給与体系は働く地域によっても異なります。
地域別に求人を比較してみると、社会福祉士の平均年収が最も高いのは関東地方で338万円。
それに対して給与水準が最も低いのは九州地方で、286万円となっています。(2023年10月時点)
人口が集中している地域では社会福祉士を必要とする施設も多いため、需要の高さから給与が高くなる傾向にあるようです。
このように同じ職業でも物価や最低賃金、需要などの違いから実際に支払われる金額には地域差が生じる場合があります。
個人の経験・スキル
個人の経験やスキルも、年収を左右する要因の一つです。
例えば、ケアマネジャー(介護支援専門員)など、社会福祉士の他にも業務に活かせる資格を取得している場合、勤務先によっては資格手当が支給されることがあります。
公益財団法人社会福祉振興・試験センターが発表している「令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果」によると、実際に資格手当をもらっている社会福祉士の割合は37.4%。その平均月額は1万827円となっています。
職場
社会福祉士は、介護・障害福祉だけでなく、医療や教育などさまざまな分野で活躍できる資格です。
このため就職先も多岐にわたり、どのような職場を選ぶかによって給料は大きく異なります。
職場ごとの年収の違い
それでは早速、社会福祉士の代表的な職場と給与の違いをみていきましょう。
分野別
社会福祉士は、高齢者福祉、障がい者福祉、医療、児童・母子福祉など多岐にわたる分野で活躍しており、それぞれの分野で異なる役割を担っています。
たとえば、高齢者福祉関係では、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどで生活相談員として入所者の相談援助や家族との連絡調整、入退所の手続きなどを行います。
障がい者福祉関係では、障がい者支援施設で生活指導員や生活相談員として利用者の相談援助や自立支援、退所後の生活援助、精神面でのサポートを担います。
医療関係では、医療ソーシャルワーカーとして病院やクリニックなどで患者やその家族が抱える医療費、退院後の生活、心理的な問題などについて相談に応じ、支援します。
児童・母子福祉関係では、児童相談所や乳児院、児童養護施設などでファミリーソーシャルワーカーや児童指導員として、子どもや保護者の子育てに関する悩み、非行、虐待といった問題解決に向けた支援を行います。
地域福祉関係では、地域包括支援センターや社会福祉協議会などで、地域住民の福祉課題の把握や地域資源の調整・開発、ネットワーク形成に携わります。
行政機関では、公務員として生活保護関係や地域福祉関係の業務に従事し、生活困窮者自立支援や地域住民への相談援助を行います。
学校教育関係では、スクールソーシャルワーカーとして児童・生徒の不登校、いじめ、虐待などの問題解決を図り、就業支援関係では、就労が困難な障がい者への実習支援や職場探し、就労機会の確保をサポートします。
このように、社会福祉士はそれぞれの分野で専門的な知識と技術を活かし、多様なニーズに対応しています。
施設・事業所別
社会福祉士の平均年収は、勤務する施設や事業所によって大きく異なります。
最も多くの社会福祉士が働く高齢者福祉関係では、介護老人保健施設が平均年収423万円と最も高く、一方で地域密着型サービス事業所は386万円と最も低い傾向にあります。
障害者福祉関係では、身体障害者更生相談所が504万円と最も高く、これは社会福祉士全体の平均年収と比較しても高水準です。
しかし、同じ障害者福祉関係の中でも就労支援事業所は366万円と最も低く、その差は138万円にものぼります。
医療関係では、多くの社会福祉士が病院・診療所に勤務しており、平均年収は398万円です。
社会福祉士の平均年収が高い施設・事業所のランキングでは、保護観察所や地方更生保護委員会が638万円で最も高く、これは国家公務員としての勤務になるため、唯一600万円台という高い水準です。
2位の児童相談所は532万円、3位の身体障害者更生相談所は504万円と500万円台が続きます。
児童相談所で働く社会福祉士は、児童福祉司として生活に困難を抱える子どもや保護者のサポートを担い、家庭訪問や一時保護を行うこともあります。
また、身体障害者更生相談所で働く社会福祉士は身体障害者福祉司として、身体障がい者やその家族への情報提供や相談対応、医学的・心理的な判定業務などを担当します。
これらの施設は地方公務員の仕事であり、ランキング全体を見ても平均年収が高い職場は都道府県庁や区役所など、地方公共団体が多くの割合を占めていることが特徴です。
社会福祉士は他の福祉系国家資格に比べ好待遇!その理由は?
社会福祉士が他の福祉系国家資格と比較して好待遇で、高い収入を得やすいと言われる理由は多岐にわたります。
その中でも特に大きな要因として、社会福祉士の専門性に対する需要の高まり、資格手当の支給、そして昇進機会が挙げられます。
これらの要素が組み合わさることで、社会福祉士の給与水準が安定し、キャリアパスも広がりやすい状況が生まれています。
社会福祉士の需要が高まっている
近年、少子高齢化が進む日本において、社会福祉士の需要は高まっています。
高齢者福祉施設や障害者福祉施設、医療機関、学校、さらには行政機関や司法関係など、幅広い分野で社会福祉士が求められているのです。
特に高齢者向け施設では、社会の高齢化に伴い施設数と利用者数が増加しており、社会福祉士の需要が大きく伸びています。
社会福祉士は国家資格であり、その専門性と社会的価値は高く、将来性も明るいとされています。
多くの職場では経験年数に応じて給与が上昇する傾向にあり、役職に就けばさらに給与が向上することも期待できます。
また、資格手当が支給されるケースもあり、安定した給与を得やすい点も魅力です。
資格手当がつくことがある
社会福祉士の年収や給与が高いと言われる理由の一つに、資格手当の存在があります。
あらゆる福祉制度に精通し、適切な相談援助を行える社会福祉士は、福祉業界において欠かせない人材であり、勤務先によっては資格手当が設けられています。
実際に福祉・介護・医療分野で働く社会福祉士で資格手当をもらっているのは37.4%にのぼり、その平均月額は1万827円です。
勤務先によっては2万円や3万円以上の手当がつくケースもあり、これらが社会福祉士の給与水準を高く保つ要因の一つとなっています。
資格手当の平均月額
社会福祉士が受け取る資格手当の平均月額は、約10,827円です。
これは令和2年度の調査結果で示されており、1万円以上2万円未満の金額を受け取っている社会福祉士が最も多いことが分かっています
資格手当の金額は勤務先によって異なり、5,000円未満から3万円以上と幅があります。
複数の資格を保有している場合、社会福祉士以外の資格に対して手当が支給されるケースもあります。
社会福祉士の受験資格は、多様なルートで取得が可能です。福祉系の大学や短大を卒業することで得られるのが一般的ですが、卒業した学校の年数や履修科目によって、必要な実務経験や養成施設の期間が異なります。
例えば、福祉系の4年制大学で指定科目を履修していれば、卒業後にそのまま受験資格が得られます。
一方、福祉系の3年制短大を卒業し、指定科目を履修した場合は1年以上の相談援助実務経験が必要です。
また、2年制短大を卒業し指定科目を履修した場合は、2年以上の相談援助実務経験が求められます。
これらの学歴がない場合でも、一般養成施設に1年以上、または短期養成施設に6ヶ月以上通うことで受験資格を得ることも可能です。
昇進につながることがある
社会福祉士の資格取得は、勤務先によっては昇進の判断材料となる場合があります。
福祉分野全般に対する深い理解が求められる社会福祉士の資格を持つことで、専門的な視点から相談業務を適切に行えるだけでなく、知識や能力を勤務先へ効果的にアピールすることにもつながります。
一般職員から主任、相談部門の責任者、さらには施設長や事務所管理者へと昇進するにつれて、年収も向上していくことが期待できるでしょう。
精神保健福祉士との年収の違い
社会福祉士と似ている資格としては、精神保健福祉士があります。
精神保健福祉士とは、精神障がいやこころの病気を抱える方の相談に応じ、日常生活や社会復帰を援助する資格です。
精神科ソーシャルワーカー(PSW:PsychiatricSocialWorker)とも呼ばれ、社会福祉士と同様、福祉のサポートが必要な方に生活支援や相談業務を行うこと、そして数少ない福祉系の国家資格であるという2点から何かと比較されることの多い両者ですが、その年収にも違いはあるのでしょうか?
そこで、社会福祉士と精神保健福祉士の令和元年における平均年収を比較してみましょう。
まず、社会福祉士の全体平均年収は403万円。
それに対して精神保健福祉士は404万円となっています。
(参照:令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果-公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
どちらも相談援助業務をメインとし、地方公共団体で活躍する機会も多い職種であることから、給与もほぼ同水準であると考えられます。
神戸医療福祉専門学校中央校は、社会福祉士科と精神保健福祉士科を併設。
第一線で活躍した経験を持つ講師や、在学中の先輩たちからリアルな現場の話が聞けるため、迷っている方はぜひ一度オープンキャンパスにお越しください。
また、「福祉系の仕事に興味があるけど、まだ希望職種が決まらない」という方に向けて、仕事のやりがいやリアルな働き方を聞けるイベントや、進路相談会なども実施しています。
社会福祉士としてより高い収入を得るために
社会福祉士としてより高い収入を目指すためには、いくつかの具体的な方法が挙げられます。
まず、好待遇の職場を探すことが重要です。公務員として働くことや、児童相談所、病院、市役所、社会福祉協議会といった機関は、一般的に給与水準が高い傾向にあります。
また、十分な実務経験を積んだ後には、社会福祉士として独立するという選択肢もあります。
独立することで、自身の裁量で仕事量や内容を調整でき、働き方によっては高い収入を得ることが可能になります。
いずれの方法を選択するにしても、自身のキャリアプランや働き方に合った道を選ぶことが大切です。
好待遇の職場を探す
社会福祉士としてより高い収入を目指す場合、職場選びは非常に重要です。
平均収入が高い傾向にある職場として、児童相談所や病院、市役所、社会福祉協議会などが挙げられます。
これらの職場は、公務員としての採用が多く、手当や福利厚生が充実しているため、安定した収入が期待できるでしょう。
額面上の収入だけでなく、将来的な昇給の見込みや、通勤手当、住居手当などの福利厚生、そして働きやすい労働環境も考慮し、総合的に判断することが大切です。
社会福祉士として独立する
社会福祉士として独立するというキャリアは、実務経験を十分に積んでから視野に入れることが多い選択肢です。
企業や施設で勤務するのと異なり、非常勤として自身の裁量で仕事量や内容を調整できるため、働き方によっては高い収入を得ることも夢ではありません。
独立後の仕事内容は多岐にわたり、成年後見人制度における成年後見人の受任をはじめ、福祉施設からの相談業務の請負などが挙げられます。
これらの仕事を円滑に進めるためには、地域におけるネットワークの構築が非常に重要です。
人脈を広げ、さまざまな機関との連携を深めることで、独立後も安定した業務を確保し、自身の専門性を最大限に活かした活動が期待できます。
まとめ~社会福祉士の年収・平均年収は?~
令和4年度の調査によると、社会福祉士の平均年収は約423万円です。
これは日本の平均年収である458万円と比較するとやや低い水準ですが、他の福祉・介護職員と比べると高めの傾向にあります。
社会福祉士の年収は、年齢や経験年数、勤務地、そして働く場所によって大きく異なります。
特に、公務員として働く場合は、給与水準が高い傾向にあり、安定した収入が期待できるでしょう。
また、近年は少子高齢化の進展に伴い、社会福祉士の需要が高まっており、給与や待遇の改善も進んでいます。
多くの職場で経験年数に応じて給与が上昇する傾向が見られ、資格手当が支給されるケースもあります。
実際に資格手当をもらっている社会福祉士の割合は37.4%で、平均月額は約1万円です。
さらに、社会福祉士の資格は昇進にもつながる可能性があり、主任や相談部門の責任者、施設長といった役職に就くことで、さらなる年収アップも期待できます。
給与は就職先を選ぶ上で重要な要素の一つですが、高収入の職場には、それに伴う責任や業務の質、量が求められます。
そのため、職業選択や就職活動においては、年収だけでなく「本当にやりたい仕事かどうか」「適性があるか」「働きやすい労働環境か」などを総合的に考慮し、慎重に判断することが大切です。
社会福祉士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の社会福祉士科では、夜間1年でスクールソーシャルワーカーはもちろん、その他医療や福祉の現場でソーシャルワーカーとして幅広く活躍できる社会福祉士の資格取得が目指せます。
夜間制で授業時間は基本的に18時10分〜のため、日中は仕事で忙しい社会人の方でも無理なく通学できます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや社会福祉士科の詳細情報をご覧ください。
また、社会福祉士科の学科の詳細を知りたい方は「社会福祉士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。