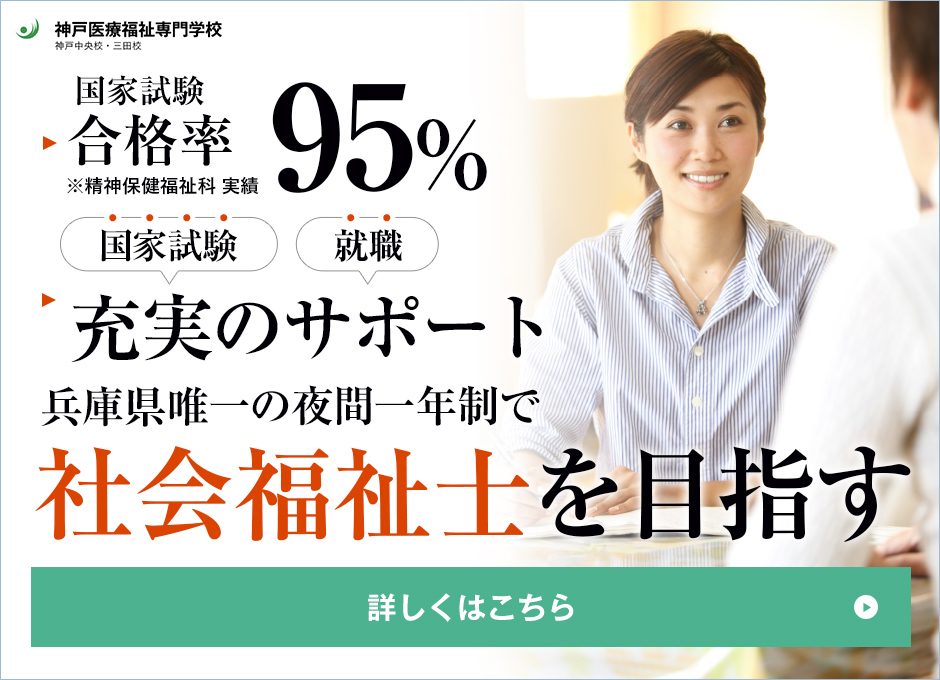福祉事務所とは、社会福祉の窓口として、地域住民の相談対応やサポート、生活保護の手続きなどを行う行政機関です。
そんな福祉事務所で主に活躍している職員を、社会福祉主事といいます。
そこでこの記事では、社会福祉主事とは?について、その仕事内容や主な勤務先、社会福祉主事となるのに必要な任用資格の取得方法を説明します。
目次
社会福祉主事とは
都道府県や特別区を含む市などでは、社会福祉全般に関する窓口である福祉事務所の設置が義務付けられています。
こういった地方自治体の福祉事務所で、支援を求める人たちに社会福祉によるサポートを行うのが、社会福祉主事です。
主事とは、地方公務員の職名の一種であり、位置付けとしては民間の企業でいう一般社員にあたります。
社会福祉主事の仕事内容
福祉事務所で働く人の職種は、社会福祉法第15条によって主に以下の3種類にわかれています。
一 指導監督を行う所員
二 現業を行う所員
三 事務を行う所員
引用:社会福祉法 | e-Gov法令検索
このなかでも社会福祉主事は主に、現業員(ケースワーカー)と査察指導員(スーパーバイザー)として働いています。
現業員(ケースワーカー)
福祉事務所の窓口で、訪れた人の相談対応をするのが現業員(ケースワーカー)の仕事です。
具体的には、生活保護申請の受付や生活状況を知るための情報収集・訪問調査などをおこなったり、高齢者や障がい者など支援を必要としている人を、適切な福祉制度やサービスにつなげたりします。
また、職探しや生活改善のためのアドバイスなど、自立支援を目的とした指導をおこなったりもします。
>>ケースワーカーとは?ソーシャルワーカーとの違いやなるために必要な資格を解説
査察指導員(スーパーバイザー)
福祉事務所では、現業員(ケースワーカー)1名につき、1名の査察指導員(スーパーバイザー)を配置することが福祉事業法によって義務付けられています。
査察指導員(スーパーバイザー)とは、現業員(ケースワーカー)の指導監督役にあたる職員です。
生活保護申請の確認や業務管理、現業員(ケースワーカー)への指導、助言などを行います。
社会福祉主事の主な勤務先
社会福祉主事は福祉事務所だけでなく、知的障害者更生相談所や身体障害者更生相談所、児童相談所など、行政の各種相談所でも働いています。
知的障害者更生相談所では知的障がい者への相談援助や情報提供をおこなう知的障害者福祉司、身体障害者更生相談所では、身体障がい者への相談援助や情報提供をおこなう身体障害者福祉司、児童相談所では子どもや保護者への相談援助や訪問調査をおこなう児童福祉司として、それぞれの職種で活躍しています。
社会福祉主事の任用資格とは

社会福祉主事とセットで、任用資格という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
任用資格とは、特定の職業やポジションに就く(任用される)ために必要となる資格のことです。
つまり、社会福祉主事の任用資格とは、社会福祉主事になるために必要な資格を指します。
社会福祉主事になるには?任用資格の取得方法
任用資格は、働くことで初めてその効力を発揮する資格です。
このため社会福祉主事を名乗るには、社会福祉主事の任用資格を取得して公務員試験に合格、その後社会福祉事務所に配属される必要があります。
社会福祉主事の任用資格を取得する方法は主に以下のとおりです。
- 大学・短大で指定科目を履修・卒業
- 通信課程を修了
- 養成機関を卒業
- 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を取得
- 都道府県等の講習会を修了
大学・短大で指定科目を履修・卒業
4年制の大学または短大(2〜3年制)で、厚生労働大臣の指定科目を3科目以上履修し、卒業することで、社会福祉主事の任用資格が取得できます。
厚生労働大臣が指定しているのは、以下の社会福祉に関する科目です。
引用:平成12年~現在までの卒業者(平成12年3月31日 厚生省告示第153号)-社会福祉主事任用資格の取得方法-厚生労働省
福祉系の大学や福祉系の学部でなくても、上記の科目を履修して卒業すれば任用資格の取得が可能です。
通信課程を修了
すでに社会福祉分野で働いている人なら、通信教育で社会福祉主事の任用資格が取得可能です。
現在、社会福祉主事の通信課程を開講しているのは、中央福祉学院の社会福祉主事認定通信過程と日本社会事業大学 通信教育科で、いずれも1年制となっています。
養成機関を卒業
社会福祉主事の任用資格は、厚生労働大臣が指定した養成機関を卒業することでも取得可能です。
養成機関の多くは2年制または3年制の専門学校で、22科目(1,500時間)を履修、卒業することでその資格を得ることができます。
都道府県等の講習会を修了
厚生労働省のホームページでは、社会福祉主事の任用資格を取得する方法の1つとして、都道府県などが主催する講習会の受講が紹介されています。
しかし、制度上では存在するものの、現在はどの都道府県も実施していないようです。
社会福祉士または精神保健福祉士の資格を取得
社会福祉士または精神保健福祉士の資格を保有している場合、自動的に社会福祉主事任用資格が得られます。
社会福祉士と精神保健福祉士は、どちらも福祉に関する相談援助系の国家資格です。
このためすでに社会福祉主事に任用されるのに必要な専門的な知識が身についていると判断され、条件なしで社会福祉主事任用資格を取得できます。
神戸医療福祉専門学校 中央校は、精神保健福祉士と社会福祉士どちらも目指せる専門学校です。
精神保健福祉士科は兵庫県で唯一の夜間1年制。
2024年4月から新設される社会福祉士科も同じく夜間1年制で、授業時間は18時10分〜となっているため、働きながら無理なく相談援助のスペシャリストが目指せます。
社会福祉主事にとどまらず、精神的な障がいや心の病を抱えている方を支援したい場合は精神保健福祉士、身体的・精神的・経済的などさまざまな理由で困っている人を幅広く支援したい場合は社会福祉士と、それぞれの資格取得も検討してみてはいかがでしょうか。
社会福祉主事と社会福祉士の違い

社会福祉主事任用資格の一つである社会福祉士は、社会福祉主事と混同されやすい資格でもあります。
そこで、ここからは社会福祉士について、もう少し詳しく説明しましょう。
社会福祉士とは、社会福祉に関して専門的な知識と技術があることを証明する国家資格です。
いわゆるソーシャルワーカーとして、身体的・精神的・経済的などさまざまな面でハンディキャップを抱える人の相談に乗り、必要な福祉制度につなげる支援をします。
社会福祉主事の資格は任用資格ですが、社会福祉士は国家資格です。
このため福祉分野で働くにあたってより社会的な評価が高く、就職・転職においても有利になるといえます。
>>ソーシャルワーカーとは|その役割や資格、年収などについて解説
また、社会福祉主事の主な勤務先は福祉事務所や各種相談所などですが、社会福祉士は学校ではソーシャルスクールワーカー、病院などの医療機関は医療ソーシャルワーカーとして、福祉以外にもさまざまな分野で活躍できる資格となっています。
>>社会福祉士になるには|資格取得までのステップ、合格率や難易度について
まとめ
社会福祉主事は、主に地域住民の福祉の窓口である福祉事務所で活躍している職員です。
生活保護の申請手続きや身体的・精神的・経済的に日常生活に困難を抱えている人に対する相談援助業務を行っています。
社会福祉主事として働くには、社会福祉主事の任用資格を取得後、公務員試験に合格し、福祉事務所に配属される必要があります。
もし今後、「社会福祉主事として働きたい」「福祉関係の職業に就きたい」と考えているなら、社会福祉の国家資格である社会福祉士の取得がおすすめです。
社会福祉主事任用資格も自動的に取得できるほか、社会福祉に関して専門的な知識と技術があることを国から認定してもらえるため、より就職や転職に有利。
福祉事務所や相談所に限らず、医療や教育などさまざまな現場で相談援助のプロであるソーシャルワーカーとして雇用してもらえるため、活躍の幅が広がります。
神戸医療福祉専門学校 中央校は、2024年4月に社会福祉士科がスタート!
夜間1年制で、授業時間は18時10分〜となっているため、働きながら無理なく資格取得を目指すことが可能です。
興味がある方はぜひまず一度、来校型またはオンライン型のオープンキャンパスにご参加ください。
社会福祉士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の社会福祉士科では、夜間1年でスクールソーシャルワーカーはもちろん、その他医療や福祉の現場でソーシャルワーカーとして幅広く活躍できる社会福祉士の資格取得が目指せます。
夜間制で授業時間は基本的に18時10分〜のため、日中は仕事で忙しい社会人の方でも無理なく通学できます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや社会福祉士科の詳細情報をご覧ください。
また、社会福祉士科の学科の詳細を知りたい方は「社会福祉士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。