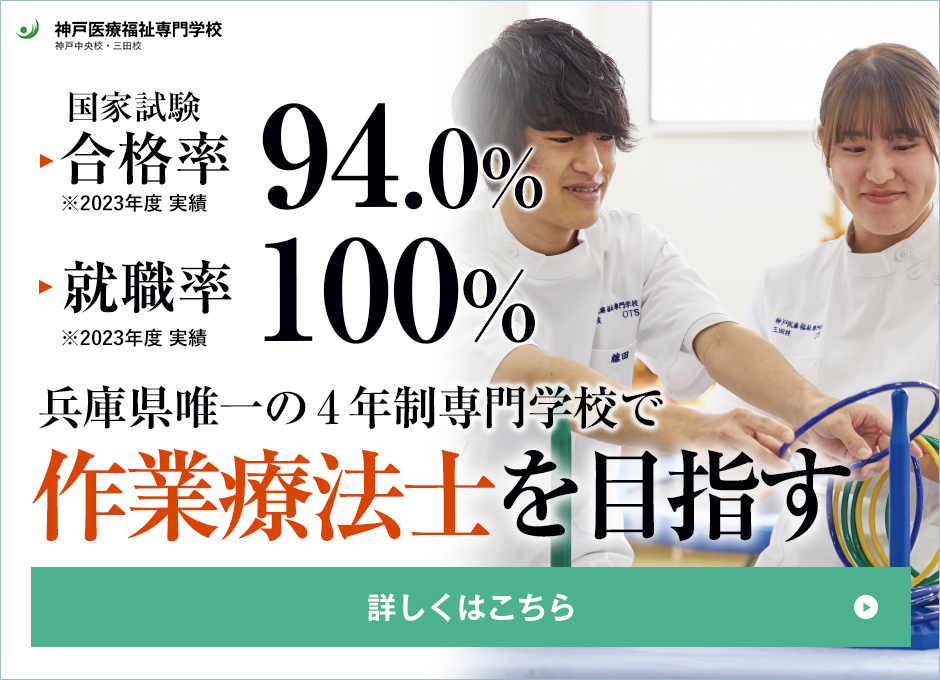高齢化社会が進行する日本では、同時に認知症患者の増加も懸念されています。
認知症は進行すると日常生活が困難になってしまうため、病気の進行を抑制するにはリハビリテーションが重要です。
そこで今回は、そんな認知症のリハビリテーションに役立つとされている作業療法について、その効果やメリット、具体的な取り組みを紹介します。
目次
認知症とは?
認知症とは、脳の病気や障害などが原因で記憶力、判断力などの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態です。
年をとればとるほど発症しやすく、2025年には65歳以上の患者数は約650〜700万人まで増加すると予測されています。これは、高齢者の5人に1人は認知症になるという計算です。
認知症にはいくつかの種類がありますが、そのなかでも最も多いのがアルツハイマー型認知症です。アルツハイマー型認知症は、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程で発症します。
認知症の主な症状(中核症状)としては、もの忘れなどの記憶障害や時間や場所がわからなくなる見当識障害、理解力・判断力の低下やそれまでできていた仕事や家事、身の回りのことができなくなる実行機能障害などが挙げられます。
また、認知症に伴って不安やうつ、幻想や妄想などの心理症状(BPSD)があらわれることもあります。
認知症の治療法
認知症は、徐々に症状が進行していく進行性の病気であり、残念ながら現代医学での完治は困難です。
このため認知症の治療では、認知機能の維持と病気の進行の抑制がメインとなります。
主な治療法は、薬物療法と薬を使わない非薬物療法(リハビリ)の2つです。
薬物治療
記憶障害や見当識障害、実行機能障害などの中核症状に作用する薬としては、抗認知症薬が用いられます。
国内で承認を受けている抗認知症薬としては、3種類のコリンエステラーゼ阻害薬と1種類のNMDA 受容体拮抗薬があります。
また、認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)については、その症状に合わせて抗うつ薬や抗不安薬、睡眠導入剤などが処方されます。
非薬物治療(リハビリ)
薬を用いない非薬物治療としては、主にリハビリテーションが挙げられます。
通常のリハビリテーションでは、骨折前と同程度までの歩行能力を目指すなど、元の状態まで回復させることが目的です。
それに対して認知症におけるリハビリテーションでは、認知機能の維持と症状悪化の予防、病気の進行抑制を目的としています。
認知症の治療では、これらの薬物療法と非薬物療法(リハビリ)が、患者さんの状態に応じて組み合わせて提供されます。
認知症のリハビリには作業療法が効果的

リハビリテーションにはさまざまな種類がありますが、そのなかでも認知症のリハビリ療法として主に用いられているのが作業療法です。
作業療法とは、日常生活に関係する作業活動を通じて、心身の機能維持や向上をめざすリハビリテーションです。
具体的には、食事・入浴・着替えや家事、遊びなどの作業活動を通じて、生活するために必要な動作である応用的動作能力や、地域社会活動や就労などの社会適応能力の維持・改善をめざします。
主に身体的・精神的な障害を抱える人の治療に取り入れられているリハビリ療法ですが、心と体を刺激することは脳の活性化にもつながるため、認知症の治療にも一定の効果があると考えられています。
認知症のリハビリに作業療法を導入するメリットと効果
そのほか、作業療法が認知症のリハビリテーションに効果的だと考えられている主な理由は以下の通りです。
住み慣れた環境で自立した生活がめざせる
認知症の主な症状の一つとして、それまでできていた仕事や家事、身の回りのことができなくなる実行機能障害が挙げられます。
こういった症状が進行すれば、いずれは自立した生活ができなくなり、介護施設への入居などを検討する必要があります。
その点、作業療法は患者さんの自立した日常生活や社会生活を目指すリハビリ療法です。
その専門職である作業療法士によって、自立した動作を行うための能力の維持や環境調整などのサポートが得られれば、可能な限り住み慣れた自宅で生活し続けることができます。
抵抗感なく取り組める
リハビリテーションでは、本人の意欲やモチベーションがその進み具合に大きく影響します。
しかし、認知症の方のなかには、自尊心や不安、精神的ショックから、認知能力を調べるテストやリハビリ治療に対して抵抗感を示す人も少なくありません。
その点作業療法では、日常的な家事や作業をおこなうためリハビリに対する心理的なハードルが下がり、抵抗感なく取り組むことが可能です。
作業を通じて自信を取り戻せる
認知症の方のなかには、認知症だと診断される過程で自尊心が傷つけられたり、今までできていたことができなくなったりすることで、精神的に落ち込んでしまう人もいます。
その点、作業療法は「今できること」にフォーカスして、その力を最大限に引き出すリハビリテーションです。
作業療法を通して、自身の回復や向上を実感することは、自信や安心感を取り戻すことにもつながります。
認知症のリハビリにおける具体的な作業療法の取り組み
それでは、実際に医療機関や介護施設などでは、どのような作業療法が認知症におけるリハビリテーションとして取り入れられているのでしょうか。
認知症のリハビリテーションにおける具体的な作業療法の取り組みとしては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 運動療法
- 回想法
- 認知刺激療法
- リアリティオリエンテーション(RO法)
運動療法
作業療法における運動療法とは、身体を動かし運動することで、運動能力や感覚、心肺機能や認知機能などの基本的動作能力の維持・改善をめざすものです。
有酸素運動やストレッチなど、身体機能に合わせたプログラムを継続することで日常の動作がスムーズとなります。また、自分でもその効果が実感できれば、自信の回復にもつながるといえるでしょう。
回想療法
回想療法とは、過去の記憶や思い出を引き出すことで脳に刺激を与えるリハビリ療法です。
認知症の方に過去の体験やエピソードを共有してもらうことで脳を活性化させ、認知能力の低下を遅らせます。
また、楽しい思い出や経験を共有することで、混乱や不安などの心理症状(BPSD)を落ち着ける効果も期待できます。
回想療法は特別な資格がなくても、話を聞くことさえできれば誰でも・自宅で実践可能です。
アルバムや思い出の品などの小道具があると、より記憶を引き出しやすくなります。
また、認知症には昔の記憶が比較的残りやすいという特徴があるため、とくに幼少時代や学生時代の思い出話が引き出しやすいといえるでしょう。
認知刺激療法
認知刺激療法とは、視覚や聴覚、触覚などの五感を刺激することで脳に刺激を与えるリハビリ療法です。
具体的には、塗り絵や折り紙、習字などの創作活動や、音楽や絵画などの芸術鑑賞で脳を活性化させ、認知能力の低下を遅らせます。
また、こういった体験を楽しみ、活動を通じて他者と会話することは心理症状(BPSD)の緩和にも役立ちます。
リアリティオリエンテーション(RO法)
時間や日付、場所や季節など、今の状況について話をするリハビリ療法です。
認知症の方が自分のおかれている状況を正しく認識できるよう、現実的な会話を日常シーンに取り入れることで、時間や場所を把握する見当識障害の改善を目指します。
また、日常会話の中に「今日は何日の何曜日か分かりますか?」や「私の名前は分かりますか?」などの質問を織り交ぜ、反復することで記憶力を高めます。
認知症のリハビリに作業療法を取り入れるときのポイント

認知症のリハビリテーションに、効果的に作業療法を取り入れるためのポイントや注意点は主に以下のとおりです。
「なじみの作業記憶」を活用する
認知症の方は、人生の中で「体で覚えたこと」や「なじみのある作業」は覚えている傾向があります。
このため認知症における作業療法では、本人にとってなじみのある記憶や作業をチョイスするのが効果的です。
ストレスや抵抗を感じずにリハビリに取り組むことができるほか、なじみのある作業を楽しんだり、作業を通じて昔の記憶や感覚を思い出したりすることには、回想療法のような感情的なメリットも期待できます。
適切な難易度に設定する
リハビリにおける作業内容は、簡単すぎると馬鹿にされているように感じ、逆に難しすぎるとなかなか達成できず自信喪失につながる可能性があります。
作業の難易度は、少し頑張れば達成できるくらいのレベルが望ましいです。
本人の状態や能力に合わせて適切に設定するとともに、できない部分はサポートする、様子を見て調整するなどの工夫をしましょう。
無理強いはしない
先述したように、リハビリテーションでは、本人の意欲やモチベーションがその進捗に大きな影響を与えます。
このため基本的に無理強いは禁物です。
例えば、よかれと思ってなじみのある作業活動を選定しても、本人にとっては誇りをもってきた作業だからこそ、やりたくないと拒否されることもあります。今までできていたことができなくなってしまうというのは、想像以上にショックで受け入れ難いものです。
また、認知症の方は健康な人に比べて脳が疲れやすいです。
集中力が切れると、今までできていた作業ができなくなって不安や苛立ちにつながります。また、疲労が蓄積した状態が続くことで一時的に認知能力が低下することもあります。
適度に休憩を挟む、時間で切り上げるなどして、無理のないペースで実践しましょう。
まとめ
認知症とは、脳の病気や障害などが原因で記憶力、判断力などの認知機能が低下している状態です。
現代医学では完治は困難なため、その治療としては薬物療法や非薬物療法(リハビリ)で認知機能の維持および病気の進行を抑制するのがメインとなります。
認知症治療における非薬物療法(リハビリ)としては、作業活動を通じて心身の機能の維持および向上をはかる作業療法が効果的です。
とくに、認知症患者にとってなじみのある作業活動を取り入れ、心と体を刺激することは、脳の活性化や心理症状の緩和につながります。
神戸医療福祉専門学校 三田校 作業療法士科は、そんな作業療法のプロである作業療法士が目指せる専門学校です。
一人ひとりが自分に合った日常生活や社会生活を送れるよう、その人らしく生きるためのサポートをします。
そんな仕事に興味がある方はぜひ、まずはオープンキャンパスや資料請求で職業理解を深めてみてくださいね。
________________________________________
参考:
https://www.cocofump.co.jp/articles/byoki/88/
https://www.jaot.or.jp/ot_alzheimer/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/59/1/59_59.9/_pdf/-char/en p12~14
作業療法士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の作業療法士科では、開校以来の国家試験の合格率は、94%! 高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
兵庫県で唯一の4年制専門学校のため、作業療法士として働くのに必要な知識と技術をじっくりと段階的に身につけることが可能。
卒業生の就職先も老年期障害領域・身体障害領域・精神障害領域・発達障害領域などさまざまで、自分の活躍したいフィールドで輝ける作業療法士が目指せます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや作業療法士科の詳細情報をご覧ください。 また、作業療法士科の学科の詳細を知りたい方は「作業療法士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「チーム医療が徹底されていて、患者さん一人ひとりに質の高い医療を提供できることにひかれました。」(2018年度卒業)
「医療チームのなかで、患者さんの生活に寄り添う役割」(2016年度卒業)
「入学時から憧れていた児童や精神科領域へ進む」(2016年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!