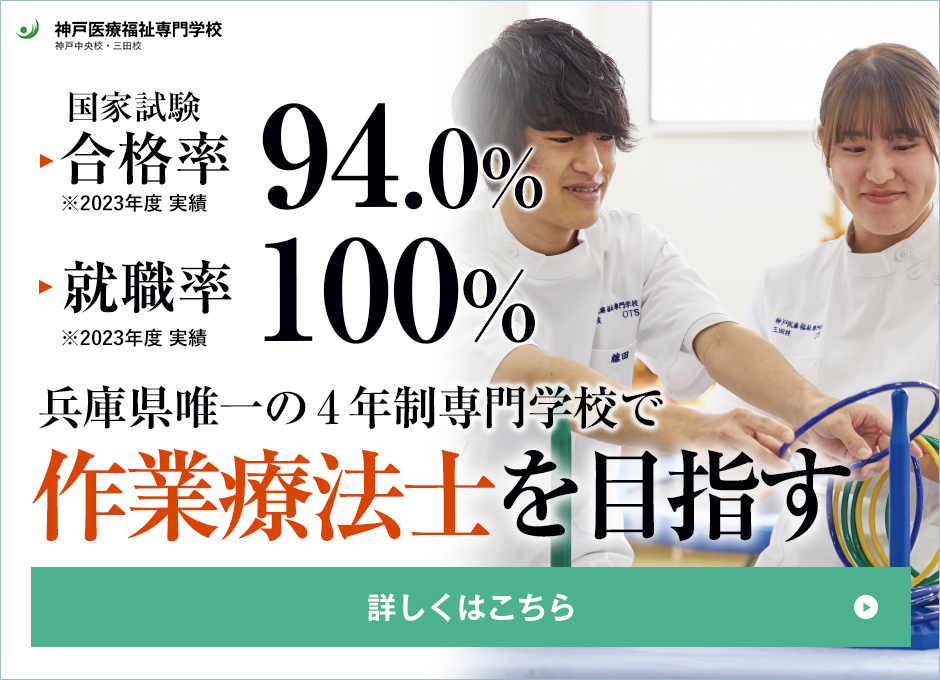厚生労働省の推計では、2025年には5.4人に1人が認知症になると予測されています。
見当識障害とは、そのように増加の一途をたどる認知症の中核症状の一つです。時間や今いる場所がわからなくなったり、親しい友人や家族を認識できなくなったりします。
今回は、そんな見当識障害の主な症状やトラブル、原因や対応法などについて解説します。
目次
見当識障害とは
見当識とは、現在の時間や場所、人、周囲の状況など自分が置かれている状況を総合的に判断し、理解する能力です。
見当識障害が起きると、時間や季節、今いる場所、友人や家族などの身近な人物がわからなくなるなどして、日常生活や社会生活に支障をきたすことがあります。
認知症の中核症状の一つ
見当識障害は、認知症の中核症状の一つです。
認知症の症状は主に、中核症状の周辺症状の2種類にわけられます。
認知症の中核症状とは、脳の神経細胞の働きが低下して起こる症状のことです。見当識障害のほかには、記憶障害や判断力の低下などが挙げられます。
それに対して、周辺症状とは、中核症状によって二次的に起こる行動・心理症状(BPSD)などです。具体的には、抑うつ状態や徘徊、幻覚、暴言などが挙げられます。
見当識障害はとくに、最も発症率が高い認知症であるアルツハイマー型認知症で、記憶障害とともに起こりやすいといわれています。
また、フルーツハイマー型認知症について2番目に多いと言われているレビー小体型認知症では、 記憶障害よりも見当識障害の症状が目立つことがあります。
せん妄との違い
見当識障害と混同されがちな症状としては、せん妄が挙げられます。
せん妄とは、手術や薬物、脳血管障害によって生じる意識障害の一種です。
幻覚や妄想がある、夜中に歩き回るなど見当識障害とよく似た症状が起きるため、その見極めが難しいことがあります。
見当識障害とせん妄の大きな違いは、発症の仕方と症状の持続性、意識障害の有無です。
せん妄は、急性疾患や投薬、手術、入院など身体上の変化をきっかけに発症することが多いです。このため発症時点が比較的明確で、1日のなかでも症状に波があります。
それに対して認知症における見当識障害はじょじょに発症、進行が進み、その症状は永続的です。せん妄のように、正常な時と症状が出る時が分かれるなど1日のうちで大きな変化はありません。
また、せん妄は脳の軽度の注意・意識の障害であるため、睡眠リズムの障害やいらいらや不安、暴言などの精神症状を伴うのに対し、見当識障害は認知や記憶の障害であるため、基本的に意識ははっきりしています。
見当識障害の症状とあらわれ方
見当識障害は、記憶障害とともに認知症の初期の段階から発生し、時間→場所→人物の順に失われていきます。
時間、場所、人物、それぞれの見当識が失われることで起きる主な症状やトラブルは以下のとおりです。
時間
見当識障害が発生すると、まずは時間を認識する能力が低下していきます。
現在の日付や時刻がわからなくなる、朝・昼・夜の区別がなくなるほか、以下のような行動が見られるようになります。
- 約束の時間が守れない、遅刻する
- 夜に仕事に出かけようとする
- 夜中に知人に電話をかける
- 真夏にセーターを着る
時間の感覚が薄れるため、約束の時間に合わせて準備をすることや、長時間待つことが難しくなります。
また、時間や季節の認識にズレが生じるため、自分の年齢がわからなくなったり、季節感のない服装をしたりすることがあります。
場所
見当識障害の症状が進行すると、次は場所に関する見当識が失われていきます。
場所の見当識が障害された場合に起こる主なトラブルは以下のとおりです。
- 通い慣れたスーパーへの道がわからなくなる
- 外出先で家に帰れなくなる
- トイレやリビングの位置がわからないなど、自宅で迷子になる
- 自宅にいるのに「家に帰りたい」と言う
- 遠方の実家など歩いていけないところに徒歩で行こうとする
場所の見当識障害は、認知症患者によくある問題行動として挙げられる徘徊の要因の一つでもあります。
現在地や自宅の場所、位置関係がわからなくなるため道に迷い、途方もなく歩き続ける状態に陥ります。
人物
一番最後に生じるのが、人物の見当識障害です。
親しい友人や家族の顔がわからなくなったり、別の人の名前を呼んだりします。
- 自分の孫を息子だと認識する
- 自分の娘を母や姉、叔母と認識する
- 自身に配偶者や子どもがいることを忘れる
- 自分に子どもがいると思い込むなど、架空の人物を作り出す
- すでに亡くなった親に会いにいこうとする
症状が進むと上記のように、記憶障害と重なって人の生死や周囲の人との関係性がわからなくなります。
見当識障害の原因

見当識障害は、認知症などによって脳の神経細胞がダメージを受け、脳の機能が衰えることで発生します。
認知症が発生する主な原因は、脳の神経細胞を破壊するたんぱく質の蓄積です。
たとえばアルツハイマー型認知症の場合はアミロイドβという、通常は脳内のゴミとして排出されるたんぱく質の一種が脳に蓄積することで発生します。
また、レビー小体型認知症の場合は、レビー小体というたんぱく質の一種が異常発生し、神経細胞を破壊することで発症します。
見当識障害のリハビリ法
見当識障害をはじめ、さまざまな症状を引き起こす認知症は、残念ながら現代医学での完治は困難です。
このため認知症の治療では主に、抗認知症薬を用いた薬物療法や非薬物療法(リハビリテーション)で、認知機能の維持および病気の進行を抑えるのがメインとなります。
認知症のリハビリテーションとしては、日常生活に関係する作業活動を通じて心身の機能維持や向上をめざす作業療法が有効です。
作業療法とは、食事・入浴・着替えや家事など生活に必要な動作や、社会適応力を獲得するために、主に、身体的・精神的な障害を抱える人の治療に取り入れられているリハビリ療法です。
しかし、心と体を刺激することは脳の活性化にもつながるため、認知症の治療にも一定の効果があると考えられています。
>>認知症のリハビリには作業療法が効果的!メリットと効果、具体的なとりくみを紹介
リアリティオリエンテーション(RO法)
作業療法のなかでも見当識障害に対するアプローチとして有効なのが、リアリティオリエンテーション(RO法)と呼ばれるリハビリです。
リアリティオリエンテーション(RO法)とは、時間や日付、場所や季節など、今の状況について問いかけることで、見当識を訓練する方法です。
たとえば、「今日は何日の何曜日ですか?」や「私の名前はわかりますか?」など、日常生活のなかで年齢や時間、場所、日時、人物名などを繰り返し質問することで、見当識障害や記憶力の改善をめざします。
すぐ実践できる!見当識障害が起きたときの対応
認知症などが原因で見当識障害が発生した場合、家族や周囲の人は以下のような対策をとるのがおすすめです。
- 会話の中で時間や場所を伝える
- 時計やカレンダーを設置する
- 自宅に案内表示を作る
会話の中で時間や場所を伝える
リアリティオリエンテーション(RO法)は、日々の認知症ケアとしても簡単に取り入れることが可能です。
「今日は5月5日、子どもの日ですね」「夏至が過ぎたので、どんどんこれから暑くなりますね」
など、日常生活のなかで日付や時間、季節などに関する会話を心がけ、見当識の認識を高めましょう。
時計やカレンダーを設置する
目につくところに時計を設置する、大きなカレンダーを貼るなど、意識しなくても時間や日付を確認できる工夫も大切です。
今日の日付にいっしょに丸をつけたり、「12時だからお昼にしましょう」など時間を意識した声かけも効果的だといえるでしょう。
時計はデジタルとアナログ、どちらが見やすいかは人によって異なりますので、本人に合ったものを自宅の各所に設置するのがおすすめです。
自宅に案内表示を作る
よく部屋の場所を間違えてしまう場合は、扉に表示をつけるなどして、認識しやすいように環境を整えましょう。
とくにトイレは、介護者が眠っている間に夜に一人で行く場合もあります。失禁してしまうと本人がショックを受けるだけでなく、介護者側の負担も大きいため、ベッドからトイレまでの動線に人感センサーライトなどを設置しておくと便利です。
見当識障害がある方との接し方のポイント

時間がわからない、自分のいる場所がわからない、周りにいる人が誰だかわからない…。このような状態では、誰でも不安になって当たり前です。
このため認知症の方が不安や混乱に陥らないようにするためには、その接し方についても気を配る必要があります。
- 失敗を責めない
- 傾聴する
失敗を責めない
見当識障害では、時間や場所に認識のズレがあるため、約束の時間を過ぎてしまうことも珍しくありません。
また、家族の方は自分の名前を間違えられたりすると、ショックで怒りや悲しみが湧いてくることもあるでしょう。
しかし、本人は決してわざとやっているわけではありません。
「どうしてそんなこともできないの?」「またできなかったの?」など、相手を否定するような言葉遣いはしないようにしましょう。
認知症の症状の一つだと理解して、失敗や間違いを責めず、感情に振り回されないことが大切です。
傾聴する
見当識障害では、夜間に外出しようとしたり、すでに亡くなった人に会いに行こうとしたりすることがあります。
こういったときは、頭ごなしに否定するとより興奮、混乱してしまう可能性があるため、まずは本人の考えに耳を傾け、いったん受け入れることが大切です。
傾聴した後に共感するなどして気持ちに寄り添ったあと、自宅から出ないように促しましょう。
また、どうしても気持ちが収まらない場合は少しの間いっしょに歩き、落ち着いてから帰宅を促すというのも一つの手段です。
見当識障害の予防法
見当識障害を予防するには、認知症の進行をなるべく食い止めることが重要です。
まずは栄養バランスの良い食事や適度な運動など、認知症の進行防止になるような生活習慣から始めていきましょう。
また、なるべく同じ生活リズムで過ごす、食事の後は歯磨きをするなど毎日一定の行動をとり続けることは体内時計の調節につながり、時間の見当識障害を維持・改善する効果が期待できます。
まとめ
見当識障害は、認知症などによって脳の神経細胞がダメージを受け、脳の機能が衰えることで発生する障害です。
見当識障害が起きると、時間→場所→人物の順で見当識が失われ、時間や季節、今いる場所、友人や家族などの身近な人物がわからなくなるなどの症状があらわれます。
見当識障害をはじめ、認知症のリハビリテーションには、日常生活に関係する作業活動を通じて心身の機能維持や向上をめざす作業療法が有効です。
食事・入浴・着替えや遊びなど、さまざまな作業活動を通じて心と体を刺激することは、脳の活性化にもつながると考えられています。
神戸医療福祉専門学校 三田校は、そんな作業療法の専門家として、患者さんの「からだ」と「生活」、そして「こころ」のリハビリテーションを行う作業療法士がめざせる専門学校です。
4年間かけてじっくりと、身体的・精神的な障害を抱える人のリハビリテーションの知識と技術を身につけることができます。
リハビリテーションの仕事に興味があるという方は、無料の資料請求や来校型またはオンライン型のオープンキャンパスへの参加で、さらに職業理解を深めてみてくださいね。
作業療法士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の作業療法士科では、開校以来の国家試験の合格率は、94%! 高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
兵庫県で唯一の4年制専門学校のため、作業療法士として働くのに必要な知識と技術をじっくりと段階的に身につけることが可能。
卒業生の就職先も老年期障害領域・身体障害領域・精神障害領域・発達障害領域などさまざまで、自分の活躍したいフィールドで輝ける作業療法士が目指せます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや作業療法士科の詳細情報をご覧ください。 また、作業療法士科の学科の詳細を知りたい方は「作業療法士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「チーム医療が徹底されていて、患者さん一人ひとりに質の高い医療を提供できることにひかれました。」(2018年度卒業)
「医療チームのなかで、患者さんの生活に寄り添う役割」(2016年度卒業)
「入学時から憧れていた児童や精神科領域へ進む」(2016年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!