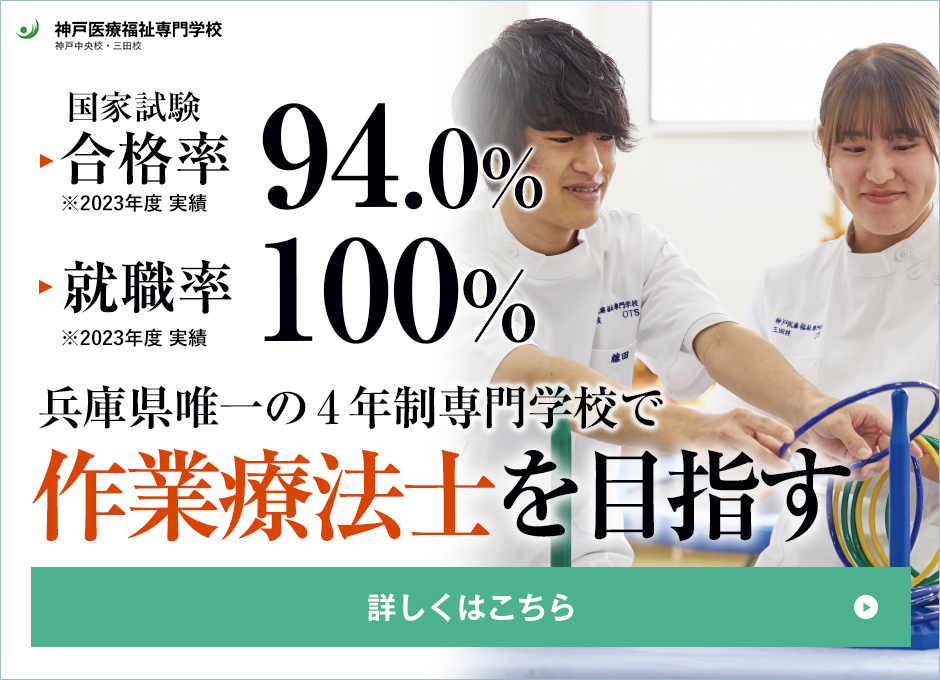リハビリテーションと聞くと、1人で黙々と取り組む姿を想像する人も多いかもしれませんね。
しかし、最近では、遊びやゲームを通じてみんなで楽しくリハビリに取り組む「遊びリテーション」が注目され、積極的に導入する介護施設や高齢者施設が増えています。
そこで今回は、遊びリテーションの効果や導入のメリットについて解説。
記事の後半では、すぐに実践できる遊びリテーションの具体例も紹介します。
目次
遊びリテーションとは
遊びリテーションとは、「遊び」と「リハビリテーション」を組み合わせた造語で、リハビリ効果が期待できる遊びやレクリエーションのことです。
レクリエーションの楽しさとリハビリテーションの効果が両方得られるため、対象者が楽しみながら取り組めるとして今注目を集めています。
遊びリテーションを導入するメリット
リハビリテーションでは、本人の意欲やモチベーションが進み具合にも大きく影響します。
その点、遊びやゲームを通じてリハビリをおこなう遊びリテーションは「楽しい」「もっとやりたい」と前向きな気持ちを持って取り組めることが大きなメリットです。
また、ゲームやレクリエーションを通じて頭や体を動かしたり、他者と交流したりすることは、心身の活性化につながります。
遊びリテーションの効果
遊びリテーションは、実施するゲームや遊びの目的、種類によっても異なりますが、主に以下のような効果が期待できます。
- 身体機能の維持や改善
- 自発性の向上
- 問題解決能力の改善
- 生活空間の拡大
- コミュニケーションの拡大
- 注意力、記憶力の向上 など
単に身体機能を回復するだけでなく、ゲームや遊びに対する興味や関心、向上心などから起こる内発的動機づけにより、自発的な行動が期待できるのが遊びリテーションの大きな特徴です。
また、「より得点するにはどうしたらいいか」「チームに貢献するにはどうしたらいいか」など、戦略を立てて勝利を目指すことは、コミュニケーションの拡大や問題解決能力の改善にもつながります。
遊びやゲームを通じたリハビリはさまざまな領域で活躍している

遊びリテーションという言葉は介護現場で考案されたもので、普及のきっかけとしては1989年に出版された『遊びリテーション 障害老人の遊び・ゲームの処方集』(竹内孝仁ほか著)という書籍が挙げられます。
こういった理由により、遊びリテーションという言葉は、主に老人ホームなどの高齢者施設でおこなわれる集団レクリエーションを指すのが一般的です。
しかし、実は遊びやゲームを通じたリハビリテーション自体は、障がい者や子どもを対象とする領域でも古くから実践されています。
そこでここからは、各領域で実践されている遊びやゲームを通じたリハビリテーションとその効果について紹介します。
高齢者のリハビリテーション(老年期障害領域)
老年期障害領域とは、主に65歳以上の高齢者を対象とする領域です。
具体的には、加齢にともなう身体・認知機能の低下や身体障害、病気・事故などによる後遺症を抱えている人を対象にリハビリテーションを実施します。
老年期障害領域の主なゲームや遊びを通じたリハビリテーションとしては、囲碁・将棋などのゲームや、ボウリングや連想ゲームなどの集団レクリエーション(=遊びリテーション)、なぞなぞやクイズなどの脳トレが挙げられます。
こういったリハビリテーションでは、脳機能の活性化や運動機能の向上、他者とのコミュニケーションによる精神的な好影響などの効果が期待できます。
障がい者のリハビリテーション(身体障害領域・精神障害領域
障がい者のリハビリテーションでは、生まれつきや病気や事故などの後遺症で障害を抱えている人が対象です。
具体的には、身体的な障害を抱えている人や、うつ病などこころの病気や精神的な障害を抱えている人を対象にリハビリテーションを実施します。
身体障害領域の遊びリテーションとしては、ボッチャなどの障がい者向けのスポーツや、足の代わりにサッカーボールを棒でつつく棒サッカーなどのスポーツ系レクリエーションが取り入れられる場合が多いです。
精神障害領域では、社会復帰を目指す取り組みの一つとしておこなわれる、人とコミュニケーションが生まれるような集団レクリエーションが、遊びリテーションに分類されるといえるでしょう。
子どものリハビリテーション(発達障害領域)
発達障害領域とは、心身の発達を妨げるような障がいや発達に遅れがある子どもを対象とする領域です。
具体的には、自閉症や脳性まひ、知的障がいや学習障害、発達障害などがある子どもに対して機能発達訓練やサポートをおこないます。
子どもにとって遊びは、体力や運動能力だけでなく、自発力や認知能力、創造力を高めるほか、社会性を育むなど心身の成長に欠かせない要素です。
また、集中して楽しく取り組んでもらうためにも、子どものリハビリテーションでは年齢に合わせた遊びの要素を取り入れることが欠かせません。
以上の観点から、子どもに対するリハビリテーションは、遊びを通じて実施するのが一般的です。
工作やお絵描きなどの創作活動で認知・学習面をサポートする、集団レクを通じて社会性を育む、絵の具や片栗粉などを使った感触遊びで五感を刺激するなどして、それぞれ適切なアプローチ法でつまずきが生じている発達を促します。
>>子どもたちの発達を楽しく支援!遊びを取り入れたオーダーメイドの作業療法とは?
リハビリでは遊びも作業活動の一つ
上記のように、子どもから高齢者まで幅広い人を対象に「からだ」と「こころ」のリハビリテーションを実施する専門職を作業療法士(Occupational therapist:OT)といいます。
作業療法士は、加齢や心身の病気、障害などにより、日常的な動作や社会への適応に困難を抱えている人がその人らしい生活を送れるよう支援する仕事です。
具体的には、手や体を動かす作業療法を通じて、機能の回復や心の健康、社会とのつながりをめざします。
作業療法では、食事や入浴、仕事など日常生活に関わる動作や、仕事や遊びなど人間の生活全般に関わるすべての諸活動を「作業活動」と呼び、治療の手段とします。
遊びと聞くと、「本当に効果があるの?」「子どもだましじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、リハビリテーションの観点からいえば、遊びも立派な作業活動。
リハビリ効果のあるレクリエーション=遊びリテーションはもちろん、編み物や陶芸などの創作活動やカラオケや映画鑑賞などの趣味活動も、治療における有効なアプローチの一つということです。
神戸医療福祉専門学校 三田校 作業療法士科では
神戸医療福祉専門学校 三田校 作業療法士科は、患者さんの「からだ」「生活」「こころ」のリハビリテーションを行う作業療法士が目指せる専門学校です。
兵庫県で唯一の4年制専門学校のため、作業療法士として働くのに必要な知識と技術をじっくりと段階的に身につけることが可能。
卒業生の就職先も老年期障害領域・身体障害領域・精神障害領域・発達障害領域などさまざまで、自分の活躍したいフィールドで輝ける作業療法士が目指せます。
簡単にできる遊びリテーションを3つ紹介

ここまでは、遊びリテーションの定義や効果、リハビリテーションにおける遊びの重要性について解説してきました。
そこで、ここからは簡単にできる遊びリテーションの具体例として以下の3つを紹介します。
- ボウリング
- 玉入れ
- つまみ競争
①ボウリング
ペットボトルや牛乳パックなど軽くて倒れやすいものを6本用意し、10~50点の点数を書きます。
椅子に座ったままボールを転がし、倒したピンの得点を競いましょう。
腕の筋力や手指の巧緻性(器用さ)の向上につながるほか、みんなで競ったり健闘をたたえ合ったりすることで、コミュニケーションの活性化や意欲向上が期待できます。
②玉入れ
椅子にすわって、自分のチームカラーのフラフープの中にカラーボールを投げ入れ、個数を競います。
ボールは、新聞紙を丸めたものやお手玉でも代用可能です。
ボールを握る、投げる動作が必要になるため腕、手指の運動や協調運動の効果が期待できます。
足を使って入れるルールにすれば姿勢の練習や足の協調運動の訓練にもなるでしょう。
また、人との交流を促進したい場合は、背後に設置された箱に向かってボールを投げ入れる「後ろ向き玉入れ」もおすすめです。
周囲から力加減や距離感のアドバイスをもらうなどコミュニケーションが生まれるほか、予測力が求められるため認知機能の維持向上にも役立ちます。
③つまみ競争
洗濯バサミで机に並べたペットボトルのキャップを、時間制限内に何個つまめるか競うゲームです。
つまみ動作を応用したレクリエーションとして、手指の巧緻性訓練に効果があります。
ペットボトルのキャップの裏に得点を書き、数字の面を下に置いて合計得点を競えば、能力に関係なく誰もが勝てるチャンスがあります。
遊びリテーションを取り入れるときのポイント
自発的に身構えず楽しく取り組めるのが遊びリテーションのメリットです。
このため導入する場合は、リハビリの目的だけでなく、対象者の興味や関心に合った遊びやゲームを選択することが重要です。
また、障がいの部位や程度、低下している機能は人によって異なります。
このためとくに集団レクリエーションでは、難易度を調整する、ルールで運要素をプラスするなどして、あらゆる人が平等に楽しめる工夫をしましょう。
まとめ
遊びリテーションとは、「遊び」と「リハビリテーション」を組み合わせた造語で、リハビリ効果が期待できるレクリエーションのことです。
介護現場が発祥であるため、一般的には高齢者施設でおこなわれる集団レクリエーションを指しますが、実は遊びやゲームを通じたリハビリというのは、障がい者や子どものリハビリテーションなどの領域でも古くから実践されています。
実際にリハビリテーションの手法の一つである作業療法では、遊びも機能の回復や心の健康、社会とのつながりを作るのに役立つ立派な作業活動の一つです。
神戸医療福祉専門学校 三田校 作業療法士科は、そんな作業療法を通じて患者さんの「からだ」と「こころ」のリハビリテーションを行う作業療法士が目指せる専門学校です。
一人ひとりが自分に合った日常生活や社会生活を送れるよう、その人らしさを支える。
そんな仕事に興味がある方はぜひ、まずはオープンキャンパスや資料請求で職業理解を深めてみてくださいね。
作業療法士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の作業療法士科では、開校以来の国家試験の合格率は、94%! 高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
兵庫県で唯一の4年制専門学校のため、作業療法士として働くのに必要な知識と技術をじっくりと段階的に身につけることが可能。
卒業生の就職先も老年期障害領域・身体障害領域・精神障害領域・発達障害領域などさまざまで、自分の活躍したいフィールドで輝ける作業療法士が目指せます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや作業療法士科の詳細情報をご覧ください。 また、作業療法士科の学科の詳細を知りたい方は「作業療法士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「チーム医療が徹底されていて、患者さん一人ひとりに質の高い医療を提供できることにひかれました。」(2018年度卒業)
「医療チームのなかで、患者さんの生活に寄り添う役割」(2016年度卒業)
「入学時から憧れていた児童や精神科領域へ進む」(2016年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!