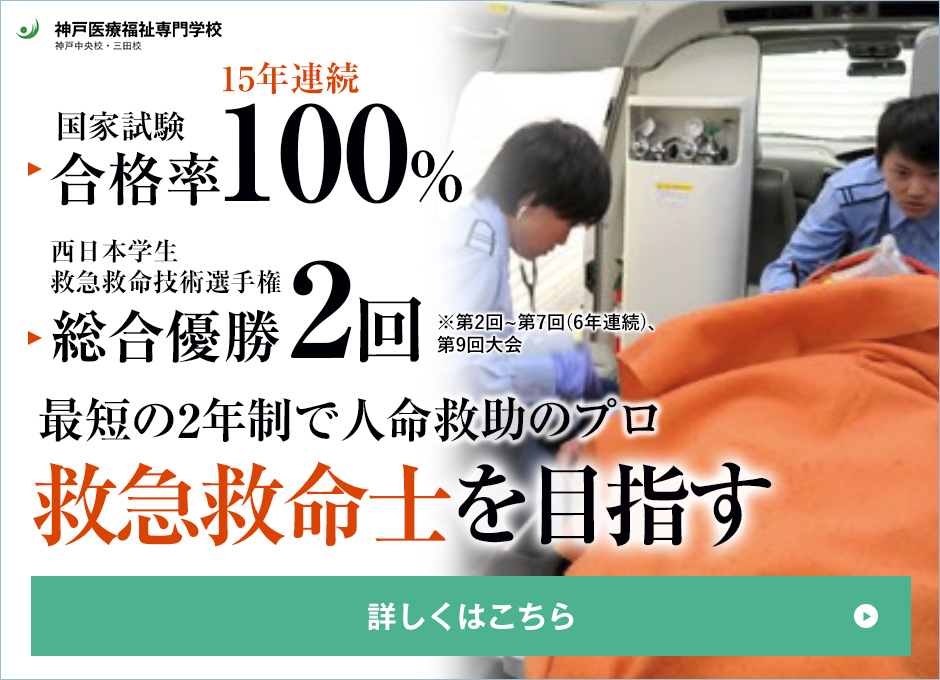救急救命士は医療に携わる国家資格が必要な職業ですが、その勤務状況は他の医療系の職業とは異なり、給料や年収にも特徴が見られます。
例えば、東京消防庁の救急救命士の初任給は、2021年のデータでは専門学校卒業生と大学卒業生で異なるケースがあり、一般的に大卒の方が高めに設定されている傾向があります。
しかし、専門学校を卒業すると短期間で現場に出られるため、早期に実務経験を積むことが可能です。
この現場経験は、救急救命士にとって非常に重要であり、専門的なスキルが求められる職務では経験が有利に働くことが多いです。
また、救急救命士の給与は、基本給に加えて、時間外手当、夜勤手当、出動手当、特殊勤務手当など、さまざまな手当が支給されるため、これらを合計すると月額約10万円程度になることもあります。
これらの手当は、救急救命士の特殊な勤務形態や危険を伴う業務内容を反映しているといえるでしょう。
特に、公安職俸給表が適用される消防士としての勤務形態は、危険と隣り合わせの業務や変則勤務が多いため、他の地方公務員と比較しても高い給与水準が設定されています。
これらの要素が組み合わさることで、救急救命士の全体的な収入は日本の平均年収や他の医療系職種と比較して高い水準を維持しています。
目次
救急救命士とは?
救急救命士とは、急病人やケガ人を救急車で医療機関へ搬送するまでに、医師の指示に基づき必要な救命救急処置を行う専門職です。
この救命救急処置は、国家試験に合格した救急救命士のみが実施できます。
おもな勤務先は消防署ですが、自衛隊や海上保安庁のほか、近年では民間警備会社や医療関連企業などでも活躍の場が広がっています。
救急救命士が必要とされる現場であれば、さまざまな場所でその専門性が求められているのです。
救急救命士の給料ってどのくらい?
救急救命士の平均給与については、情報源によって異なる場合がありますが、消防士の給与体系に準じているとされています。
ある情報では、平均月収は約34万円、平均年収は約635万円という試算もあります。
また、別の情報では、2015年度時点の総務省の調査を基に、救急救命士を含む消防職の平均年収を約718万円としています。
日本の平均年収が約433万円(国税庁「令和2年分民間給与実態統計調査」より)と比較すると、救急救命士の給与水準は高い傾向にあると言えるでしょう。
この高水準の背景には、救急救命士が担う職務の特殊性が大きく影響していると考えられます。
危険を伴う現場での活動や、24時間体制での勤務といった、精神的・肉体的に大きな負担を伴う業務内容が給与に反映されていると考えられます。
また、救急救命士は地方公務員であるため、給与は地方自治体によって異なりますが、公安職俸給表が適用されることが多く、他の公務員職種と比較しても高い傾向にあります。
これは、警察官などと同様に、国民の安全を守る重要な役割を担う職務への評価と言えるでしょう。
さらに、時間外手当や夜勤手当、出動手当などの各種手当が加算されることも、平均年収を押し上げる要因となっています。
これらの手当は、救急現場における予測不可能な事態への対応や、深夜・早朝の勤務に対する補償として支給されるものです。
救急救命士の初任給
救急救命士の初任給は、勤務する自治体によって異なりますが、2025年の東京消防庁におけるⅢ類初任給は、約26万4,000円です。
この金額には、基本給に加え、地域手当や各種手当が含まれています。
地方公務員の給与は、各自治体の財政状況や条例によって設定されるため、地域によって差が生じることを理解しておく必要があります。
例えば、人口の多い都市部では、物価や生活費を考慮して初任給が高めに設定される傾向があります。
一方、地方では、それよりも低くなる場合があります。
また、救急救命士の初任給は、学歴によっても違いが見られます。
一般的に、大学を卒業した救急救命士の方が、専門学校を卒業した救急救命士よりも初任給が高く設定されることが多いです。
しかし、専門学校を卒業した場合は、大学卒業よりも早く現場での実務経験を積めるため、早期の昇給やキャリアアップに繋がる可能性もあります。
救急救命士の各種手当
救急救命士には、基本給に加えて、業務の特殊性や勤務形態に応じた様々な手当が支給されます。
主なものとしては、時間外手当、夜勤手当、出動手当、特殊勤務手当などが挙げられます。
これらの手当の基準や金額は自治体によって異なりますが、一つひとつの手当が高額でなくとも、合計すると月額8万円から10万円程度になる場合もあるようです。
例えば、出動手当は、救急業務のために出動した際に1回の出動ごとに支給され、1時間未満の出動で520円、1時間以上の場合は1時間につき380円が加算されることがあります。
また、夜勤手当は、22時から翌朝5時までの深夜帯勤務に対して支給される深夜割増手当などがあり、24時間勤務の場合は1勤務につき490円が支給されるケースもあります。
さらに、危険を伴う作業や精神的な負担が大きい業務に対しては特殊勤務手当が支給されます。
これには、火災現場や高所での救助活動、遺体搬送などが該当します。自治体によっては、救急救命士免許を持つ職員が特定の救急救命処置を実施した場合に支給される救急救命士手当を設けているところもあります。
例えば、業務1件につき2,000円を支給する例や、出動1回につき700円、特定の救急救命処置を行った場合は510円を加算する例など、手当の内容や金額は多様です。
加えて、通勤手当や扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当(ボーナス)なども支給されることがあり、これらの手当が救急救命士の収入を支える重要な要素となっています。
出動手当
救急業務のため出動した職員に支給される手当で、1回の出動ごとに支払われます。
緊急性の高い現場で、限られた時間の中で適切な処置を行う救急救命士や救急隊員には、その専門性と責任に見合った「救急手当」が支給される場合もあります。
これは、通常の救急活動に加え、特定の高度な医療行為を実施した際に支払われる手当です。
例えば、傷病者の気道確保や薬剤投与など、救急救命士にしかできない専門的な処置が対象となることがあります。
出動手当は、出動回数に応じて支給されるため、出動頻度が高い地域や時期には、手当の額が増える傾向にあります。
支給額や基準は各自治体の条例によって定められており、地域によって異なる点に注意が必要です。
時間外手当
時間外手当とは、正規の勤務時間を超えて業務に従事した場合に支給される手当を指します。
救急救命士は、その業務の性質上、時間外勤務が発生しやすい職種です。
例えば、仮眠時間中に緊急出動要請があった場合や、休日に地域の防災訓練や消防のイベントなどに参加するために出勤した場合などがこれに該当します。
時間外勤務は、労働基準法によって定められており、原則として1日8時間、週40時間を超える労働に対しては割増賃金が支払われることが義務付けられています。
救急救命士の場合、24時間体制での勤務形態が多く、緊急事態が発生すれば時間に関わらず対応が求められるため、時間外手当の支給機会は頻繁にあります。
この手当は、救急救命士の月収や年収を構成する重要な要素の一つであり、基本給と合わせて給与水準を高める要因となっています。
ただし、支給基準や金額は各自治体によって異なるため、勤務地によって差が生じる点には注意が必要です。
夜勤手当
夜勤手当は、救急救命士の給与を構成する重要な要素の一つです。
この手当は、深夜帯(原則として22時から翌朝5時まで)に勤務する際に支給されるもので、労働基準法によって通常の賃金に対して25%以上の割増賃金が義務付けられています。
救急救命士は24時間体制で勤務することが多く、夜間勤務が避けられないため、この夜勤手当が基本給に上乗せされることで、総支給額が大きく変動します。
例えば、月20時間の夜勤を行った場合、時給2,000円であれば、夜勤手当だけで10,000円(2,000円 × 20時間 × 0.25)が加算されることになります。
さらに、深夜帯だけでなく、夕方から深夜にかけての準夜勤や、深夜から翌朝にかけての深夜勤など、勤務時間帯によって異なる手当が支給される場合もあります。
特殊勤務手当
特殊勤務手当は、救急救命士が従事する業務の中でも、特に危険度が高く、身体的または精神的に大きな負担を伴う勤務に対して支給される手当です。
この手当は、命の危険が伴う火災現場での救助活動や、高所での作業、また、亡くなった方のご遺体搬送など、精神的なストレスが大きい業務に携わった際に適用されます。
具体的な支給額や適用される業務の種類は、所属する自治体や消防署の規定によって異なりますが、救急救命士の給与を構成する重要な要素の一つです。
たとえば、感染症患者の搬送といった特殊な状況下での活動に対しても、感染リスクを考慮した手当が支給される場合があります。
これらの手当は、救急救命士が日々直面する過酷な現場環境に対する正当な評価として位置づけられており、業務へのモチベーション維持にもつながっています。
救急救命士のボーナスや昇給について
救急救命士の昇給は基本的に年に一度行われ、ボーナスは年に二回支給されるのが一般的です。
地方自治体によって差はありますが、昇給は年齢に応じて進むことが多く、経験を積むほどに収入が増加する傾向にあります。
たとえば、20代の平均月収が約22万円から30万円台であるのに対し、30代では約30万円から40万円、40代になると約40万円から50万円へと上がります。
これに伴い、ボーナスも20代で約100万円から130万円台、30代で約130万円から170万円、40代では約175万円から200万円と増加する傾向が見られます。
これらのデータは、救急救命士が長期的な勤務を通じて役職に就くことで、安定した収入向上が期待できる職業であることを示しています。
したがって、救急救命士は専門的なスキルと経験を積み重ねながら、着実にキャリアを築き、収入を増やしていける職業だと言えるでしょう。
学歴による給料の違い
救急救命士を目指すには、大学や専門学校の養成課程を卒業し、国家試験に合格することが一般的なルートです。
どちらの学歴を選んでも仕事内容に大きな違いはありませんが、給料面では多少の差が見られます。
一般的に、大卒の方が初任給が高く、昇給のスピードも早い傾向にあります。
例えば、2025年の大阪市消防局では高卒の初任給が約22万円であるのに対し、大卒では約25万円とされています。
ただし、これはあくまで目安であり、勤務する自治体によって異なります。
一方で、専門学校を卒業すると、大学卒よりも早く現場での経験を積めるため、生涯年収で見た場合には大きな差がないと言われることもあります。救急救命士は専門性の高いスキルが求められる職種であり、現場経験が非常に重要視されるため、実践を早くから積めることは大きなメリットとなり得ます。そのため、「より高度な処置を行うポジションに就くには現場経験が豊富な方が有利」という意見も少なくありません。
また、高校卒業後すぐに消防官となり、働きながら救急救命士の資格取得を目指す方法もありますが、この場合は、救急隊員として5年以上(または2,000時間以上)の実務経験を積み、さらに救急救命士の養成校で半年以上の研修を受講する必要があります。
このルートは資格取得までに時間がかかり、働きながら国家試験対策をしなければならないため、厳しい道のりと言えるでしょう。
救急救命士国家試験の合格率は2025年度では94%以上と高いですが、これは受験者が養成校でしっかり学んだ人々に絞られているためであり、決して簡単な試験ではありません。
救急救命士の収入は高い?
救急救命士の収入は、他の地方公務員と比較して高くなる傾向があります。
多くの情報源で、救急救命士の平均年収は約635万円という記載が見られますが、一部の情報源では約718万円、または約310万円と示すものもあり、情報源によって異なる場合があります。
地方公務員全体の平均年収に関する最新の統一されたデータを見つけることは困難ですが、一般行政職の地方公務員の平均年収を約641万円とする調査結果もあります。
この傾向は、救急救命士が従事する消防士の給与体系に起因しています。
消防士は、警察官などと同様に「公安職俸給表」という特別な給与体系が適用されます。
公安職は、その職務の危険性や変則的な勤務形態を考慮し、他の公務員職種よりも高い給与水準が設定されていることが一般的です。
さらに、基本給に加えて、時間外手当、夜勤手当、出動手当、特殊勤務手当といった様々な手当が支給されるため、他の地方公務員と比較して収入が高くなる傾向があると考えられます。
これらの手当は、救急救命士の特殊な勤務状況を反映したものであり、月々の収入に貢献しています。ただし、実際の収入は勤務する自治体や個人の経験、階級によって異なります。
他の地方公務員と比較した場合
救急救命士の平均年収は約635万円で、地方公務員全体の平均年収約630万円と比較すると、やや高い傾向にあります。
この差は、救急救命士の特殊な勤務状況に起因しています。救急救命士の多くは消防署に勤務しており、その給与は地方公務員の給与規定に基づいて支払われます。
公務員の給与は法律で定められた俸給表に沿って支給され、救急救命士が就く消防士は、警察官などと同様に「公安職俸給表」が適用されます。
公安職俸給表は、国や地域の安全を守る公安職に適用されるもので、危険を伴う業務や変則的な勤務体系を考慮し、他の俸給表よりも高い給与水準が設定されているのが特徴です。
例えば、夜勤や土日出勤が多いという勤務形態に加え、火災現場や高所での救助活動、遺体搬送といった危険や精神的負担の大きい業務に対しては、特殊勤務手当が支給されます。
これらの諸手当が加わることで、救急救命士の収入は他の地方公務員と比べて高くなる傾向があります。ただし、地方公務員の給与は自治体によって異なるため、都市部の消防本部では手当や給与水準が高く設定されている場合がある一方で、地方では物価水準に合わせて年収が低くなる可能性もあります。
他の医療系職種と比較した場合
他の医療系職種と比較した場合、看護師の平均年収は約488万円から508万円(2024年時点)、放射線技師の平均年収は約366万円から550万円(2025年時点)、臨床検査技師の平均年収は約353万円から541万円(2025年時点)です。
理学療法士・作業療法士の平均年収は約407万円から432万円(2025年時点)、歯科衛生士の平均年収は約369万円から404万円(2024年〜2025年時点)とされています。
救急救命士の年収が高いとされる理由としては、危険を伴う業務内容や24時間体制の勤務形態、さらには出動手当や夜勤手当、特殊勤務手当など、基本給に加えて様々な手当が支給されることが挙げられます。
これらの手当は合計すると月に約8万円から10万円程度になることもあり、年収を押し上げる要因となります。
また、救急救命士の多くは地方公務員である消防署に勤務しており、公務員の給与体系が安定していることも収入に影響する要因の一つです。
まとめ~救急救命士の給料・平均年収って?~
救急救命士の給与は、日本の平均年収や、地方公務員、その他の医療系職種と比較しても高水準にあることがうかがえます。
救急救命士の平均年収については複数の情報源があり、約350万円から約718万円と幅があるものの、一部の情報では約635万円というデータも示されています。
日本の平均年収が約433万円や約458万円、または2023年(令和5年)のデータで約460万円という情報があることを踏まえると、救急救命士の年収は平均を上回るケースが多いと考えられます。
この給与水準は、基本給に加え、時間外手当、夜勤手当、出動手当、特殊勤務手当など、様々な手当が支給されるためと考えられます。
また、多くの救急救命士が所属する消防署は、警察官などと同様に公安職俸給表が適用されるため、危険性の高い業務内容や不規則な勤務体制が給与水準に反映されているといえるでしょう。
しかし、この給与水準は、救急救命士が24時間体制で市民の命を守るために働き、日々危険と隣り合わせの業務に従事しているという事実に基づいています。
不規則な勤務形態や、人の死に直面する精神的な負担など、過酷な労働環境が伴うことも忘れてはなりません。
救急救命士は、その専門性と責任感に見合ったやりがいを感じられる職業である一方で、心身ともに高い負荷がかかる仕事でもあります。
地域によって給与水準に差があることや、勤続年数や階級によって昇給が見込める年功序列の側面があることも理解しておくことが重要です。
救急救命士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の救急救命士科では、国家試験の合格率は、15年連続で100%!(※2009〜2023年度実績)
最短の2年制で人命救助のプロを目指す! 2年間という限られた期間で、消防や救急救命の現場に即戦力となる技術力が身に付けることができます。
国家試験対策は1年次から実施され、習熟度別に学習をサポート、学生一人ひとりの状況を把握し、国家試験対策担当の教員との情報共有を徹底し、学生が主体的に取り組めます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや救急救命士の詳細情報をご覧ください。
また、救急救命士科の学科の詳細を知りたい方は「救急救命士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「神戸医療でのシミュレーション実習のおかげで実践力が身につき、どんな現場にも柔軟に対応できている」(兵庫県立播磨南高等学校出身)
「現場をリアルに想定したシミュレーション実習を数多くこなせたことが、とても役立っている」(兵庫県立北条高等学校出身)
「学校で学んだシーンに遭遇する場面もある」(鳥取県立八頭高等学校出身)
「採用後は即戦力の隊員として隊長指揮下に入りました。」(愛媛県立今治工業高等学校出身)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!