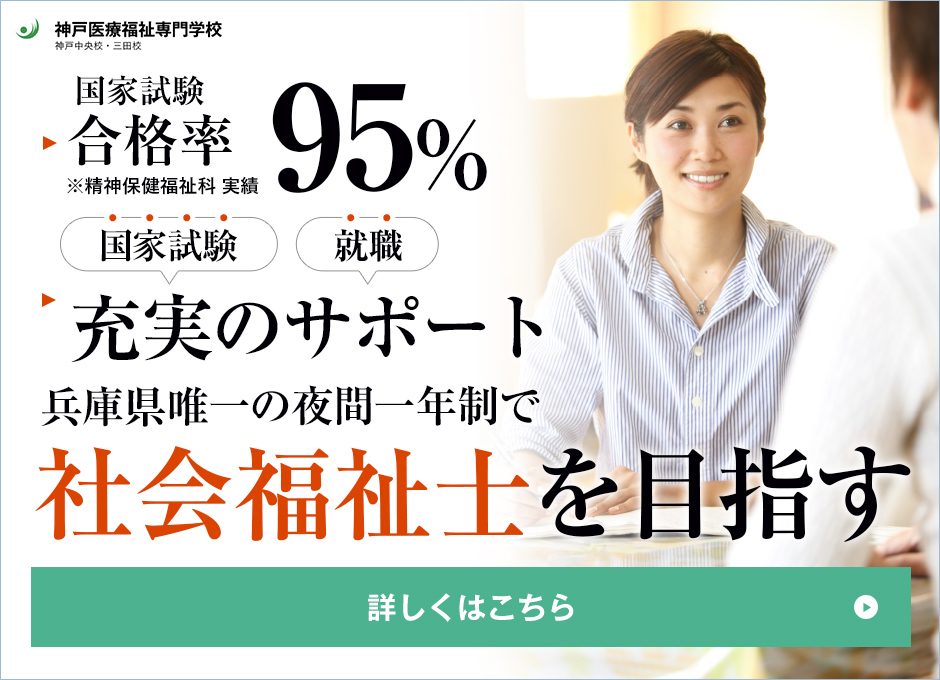目次
社会福祉士とは?
社会福祉士は、1987年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて誕生した国家資格です。
ソーシャルワーカー(SW:Social Worker)とも呼ばれる社会福祉の専門職で、身体的・精神的・経済的なハンディキャップのある人がスムーズに日常生活を送れるよう、相談に乗ったり、支援を行ったりします。
この資格は、生活上の課題を抱える人々に対して、解決に向けた助言や計画立案を行う役割を担っています。
具体的には、福祉制度や介護保険、生活保護、障害者支援といった公的制度の活用を支援したり、医療・介護・教育など他分野の専門職と連携して地域包括ケアを推進したりします。
また、家庭や地域に働きかけ、環境改善や差別解消に向けた社会資源の調整、被援助者の権利擁護(アドボカシー)を実践することも重要な機能です。
単なる対人支援にとどまらず、制度と人、現場と政策をつなぐ「社会の橋渡し役」としての機能も担っています。
社会福祉士の資格は、高齢者、障がい者、児童、生活困窮者、ホームレスなど、多岐にわたる社会的弱者を支えるために専門的な支援を提供します。
少子高齢化や社会的孤立の深刻化により、その社会的意義はますます高まっており、地域社会のあらゆる課題に対して「つなぐ役割」を担う職業といえるでしょう。
社会福祉士の役割と機能
社会福祉士の主な役割は、生活上の課題を抱える方々からの相談に応じ、問題解決を支援することです。
具体的には、個別の状況に応じた社会福祉士としての専門的な助言や支援計画の立案を行います。
また、医療機関や行政機関と連携し、福祉制度や社会資源を適切に活用できるようサポートします。
この職務は単に支援を行うだけでなく、社会の橋渡し役として、制度と個人の間の隔たりを埋める重要な役割も担っています。
支援を必要とする方々の権利擁護も重要な機能であり、彼らが安心して生活できるような環境整備に貢献しています。
社会福祉士の社会的意義
社会福祉士は、個人への支援に留まらず、社会全体の福祉を向上させる上で極めて重要な職種です。
特に社会的包摂の推進や多職種連携の要としての役割は大きく、医療、教育、介護といった多様な現場で調整役を担い、支援の質を高める専門性を持っています。
国家資格として制度に裏付けられた支援を提供する意義は大きく、職務の透明性と信頼性を担保していると言えるでしょう。
最短1年で資格取得を目指せる専門学校もあるため、詳しく知りたい方は調べてみることをおすすめします。
資格がなくても社会福祉士になれる?
社会福祉士は国家資格であり、資格がなければ「社会福祉士」と名乗ることはできません。
しかし、社会福祉士が行う相談援助の業務自体は、資格がなくても行える場合があります。
例えば、介護施設や医療機関では「ソーシャルワーカー」や「生活相談員」といった名称で、利用者の相談支援に携わることができます。
「生活相談員」は、特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護福祉施設で、利用者の手続き支援や他職種・行政機関との連携・調整、利用者やその家族の相談対応など多岐にわたる業務を行います。
生活相談員になるには、一般的に社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが必要とされますが、自治体によっては介護福祉士や介護支援専門員の資格、または一定の実務経験があれば無資格でも認められるケースがあります。
また、医療機関では「医療ソーシャルワーカー(MSW)」として、患者さんやその家族の相談援助や退院支援を行う場合があり、社会福祉士の資格が必須となることが多いですが、無資格・未経験でも応募可能な求人も存在します。
介護分野の「生活相談員」の求人でも、無資格・未経験から応募可能なものが見られます。
社会福祉士の資格は、専門知識の証明や利用者からの信頼獲得につながる「名称独占資格」であり、取得することで就職やキャリアアップに有利に働くメリットがあります。
しかし、資格がなくても相談援助業務に携わる道があるため、まずは実務経験を積みながら資格取得を目指すことも可能です。
社会福祉士はこんな仕事!
社会福祉士は、病気や障がいなどにより「生きづらさ」を感じている方々から相談を受け、その困難の軽減や解決を支援する専門職です。
この仕事内容には、利用者の話を傾聴し、そのニーズに応じたサポートプランを提案するだけでなく、医療機関や行政機関といった様々な機関との連携も含まれます。
社会福祉士自身が直接相談に乗るだけでなく、適切な支援への橋渡し役も担い、多岐にわたる仕事に対応します。
働く場所も病院や高齢者福祉施設、児童福祉施設、行政機関など幅広く、それぞれの現場で専門的な内容の仕事を提供しています。
誰もが自分らしく生活できる社会を創造する仕事
社会福祉士は、生活上の困難を抱えている方の相談に応じ、支援を行うだけでなく、すべての人が自分らしく尊厳をもって暮らせる社会の実現を目指し、社会全体に働きかける仕事です。
個人が抱える問題だけでなく、社会の構造的な課題にも目を向け、制度や仕組みづくりにも貢献することで、誰もが孤立することなく、それぞれの能力を最大限に発揮できる社会を創造することを目指します。
人々の人権や権利を守る仕事
社会福祉士は、社会的に弱い立場にある人々や、孤立している方、マイノリティの人々の人権や権利を守る重要な役割を担っています。
具体的には、人々の声を聞き、その思いを社会に伝え、権利侵害に対して介入することで、人々のエンパワメント(力を与えること)を支援します。
これをアドボカシーと呼び、社会福祉士の重要な役割の一つです。社会福祉士は、これらの活動を通じて、誰もが自分らしく尊厳を持って生活できる社会の実現を目指しています。
社会福祉士の具体的な業務内容
社会福祉士の業務は多岐にわたりますが、中心となるのは「相談援助業務」です。
この業務は、身体的・精神的な障がいがある方、高齢者、ひとり親家庭など、日常生活に困難を抱える方々に対して、その状況に応じたきめ細やかなサポートを提供することです。
具体的には、介護保険制度や各種補助金制度に関する情報提供、適切な施設への入居支援、介護サービスの利用手続きの案内などが挙げられます。相談者が抱える問題は複雑な場合が多く、法的知識や医療、福祉に関する幅広い知識が求められます。
次に重要なのが「支援サービスの管理業務」です。これは、相談者が安心して必要なサービスを受けられるよう、手続きを代行したり、必要な環境を整備したりする役割を指します。
サービス提供後も、相談内容を詳細に記録し、サービスの適切な管理を行うことで、継続的な支援を保証します。
また、福祉・支援サービスを提供する施設だけでなく、関連する法律や制度の変更に対応することも社会福祉士の重要な業務です。
さらに、「各関係機関との連絡・調整」も欠かせません。
利用者に最適な支援を提供するためには、医師、看護師、介護施設職員、行政機関など、多職種・多機関との連携が不可欠です。
社会福祉士は、これらの関係者と密に連絡を取り合い、情報を共有することで、利用者の状況に合わせたサービスの調整や見直しを行います。
最後に、「介護業務」も社会福祉士の業務の一部です。
特に介護施設や障がい者施設に勤務する場合、食事や入浴の介助、清掃や洗濯といった日常生活のサポートを行うことがあります。
ただし、社会福祉士の資格を持つことで、これらの施設ではリーダー的な役割を担うことが多く、介護スタッフの指導やサービスの質の向上にも貢献します。
社会福祉士は、利用者一人ひとりのニーズを把握し、多角的な視点から支援計画を策定・実行することで、その人らしい生活の実現を支える専門職なのです。
相談業務
社会福祉士の相談業務は、日常生活において困難を抱える方々に対し、多角的な視点から支援を行うことが特徴です。
具体的には、身体的・精神的な障がいがある方、高齢者、ひとり親家庭、経済的に困窮している方など、幅広い対象者の相談に応じます。
たとえば、介護保険制度や各種補助金制度に関する情報提供、適切な介護サービスの利用方法、福祉施設の入居手続きなど、多岐にわたる内容に対応します。
利用者の抱える課題は複雑であることが多いため、単に情報を提供するだけでなく、個別の状況を深く理解し、その人に合った支援計画を共に考え、提案することが重要です。
また、相談業務は一度で完結するものではなく、継続的な関わりが求められます。
相談内容に応じて、関係機関との連携を図りながら、支援サービスが適切に利用されているかを確認し、必要に応じてサービスの調整や見直しを行うことも重要な役割です。
例えば、介護サービスの利用開始後も、利用者の心身の状態や生活環境の変化に合わせて、サービス内容を再検討し、より最適な支援を提供できるよう努めます。
これにより、利用者が安心して生活を送れるよう、長期的な視点でのサポートを行います。
支援サービスの管理業務
支援サービスの管理業務では、利用者が社会福祉サービスを安心して利用できるよう、手続きのサポートや環境整備を行います。
具体的には、介護保険サービスや障害福祉サービスなどの申請手続きを支援したり、住環境の整備について助言したりします。
例えば、高齢者の自宅に手すりの設置が必要な場合、適切なサービス事業者の紹介や、工事費用の助成金制度の利用支援などを行います。
サービス提供後も、利用者の状況に変化がないかを確認し、相談内容を記録・管理することで、継続的にサポートしていきます。
これは、利用者のニーズに合わせたきめ細やかな支援を可能にするだけでなく、支援の効果を評価し、必要に応じてサービス内容を見直す上でも重要です。
また、社会福祉士は、福祉・支援サービスを提供する施設において、適切なサービス提供が行われているかを監督する役割も担います。
さらに、福祉支援に関する最新の法律や制度改正に対応し、利用者や関係機関に情報提供を行うことも重要な業務の一つです。
このような管理業務を通じて、社会福祉士は利用者が自立した生活を送れるよう多角的に支援しています。
各関係機関との連絡・調整
社会福祉士の業務では、利用者への直接的な支援だけでなく、医師、看護師、理学療法士、作業療法士といった医療専門職や、介護施設の職員、地域の行政機関など、多岐にわたる関係機関との密接な連携が不可欠です。
利用者の状況は日々変化するため、例えば、病状が改善して退院を検討する際には医療機関と連携して退院後の生活支援計画を立てたり、介護度が変化した場合には介護施設と連携してサービス内容の見直しを行ったりします。
また、利用者が新たな福祉サービスを必要とする際には、そのサービスを提供する機関との橋渡し役を担い、円滑なサービス利用をサポートします。
このような連携を通じて、利用者が包括的かつ継続的な支援を受けられるよう、社会福祉士が中心となって情報の共有や調整を行うことで、個々のニーズに合わせた最適な支援プランを実現しています。
介護業務
介護施設や障がい者施設に勤務する社会福祉士は、介護スタッフとして食事、入浴などの日常生活のサポートや、掃除、洗濯といった生活援助を担当するケースも少なくありません。
特に介護施設は社会福祉士の就職先として最も多く、約4割を占めています。
社会福祉士は、入所希望者やその家族からの相談対応、入所前の実態調査、契約手続き、入所後の生活や退所までの助言など、多岐にわたる業務を行います。
施設によっては介護福祉士などの介護職を補助し、介護業務に携わることもあります。
ただし、社会福祉士の資格を持っていることで、介護業務を行う施設の中でもリーダー的な役割を担うことが多くなります。
介護リーダーは、介護職員の勤務管理やシフト作成、教育・指導、利用者へのサービス内容の見直し、利用者家族との連絡・面談、管理者や他職種との連携など、幅広いマネジメント業務を担います。
また、現場での介護業務も兼任するプレイングマネージャーとしての役割も求められます。
社会福祉士として培った専門知識やコミュニケーション能力、問題解決能力が、チーム全体の質の向上や職員のマネジメントに活かされるのです。
社会福祉士の仕事の流れは?
社会福祉士が利用者からの相談を受けてサービスを提供するまでの流れを大きく分けると、
利用者や家族へヒアリングを行う
⬇︎
サービスの提案をする
⬇︎
提案したサービスに関する相談に乗る
といった順番での進め方になります。
利用者や家族へのヒアリング
社会福祉士の業務において、最初のステップとして利用者やそのご家族へのヒアリングは非常に重要です。
この段階で、利用者が日常生活で抱えている具体的な課題や、どのようなサポートを求めているのかを詳細に把握します。
例えば、身体的な不自由さによる移動の困難、精神的な不安定さによる人間関係の悩み、経済的な困窮による生活費の不安など、多岐にわたる問題が挙げられます。
ヒアリングでは、単に問題を聞き出すだけでなく、利用者やご家族が望む生活の質や将来への希望といった、より本質的なニーズを深く理解することが求められます。
ヒアリングを行う際には、利用者が安心して話せるような信頼関係を築くことが不可欠です。
利用者の話に耳を傾け、共感し、必要に応じて質問を投げかけながら、潜在的なニーズや言葉にならない思いを引き出すよう努めます。
例えば、ご本人は遠慮して言わないけれど、ご家族が「本当はこういうサポートがあればもっと楽になる」と考えているケースもあります。
このような場合、ご本人とご家族、双方の意見を丁寧に聞き取り、それぞれの視点や期待を明確にすることが大切です。
これにより、提供するサービスが利用者の真のニーズに合致し、より効果的な支援計画の立案につながります。
ヒアリングで得た情報は、その後のサービス提案や支援の継続において、常に参照される基盤となるため、非常に丁寧な対応が求められます。
サービスの提案
ヒアリングを通じて得た情報をもとに、利用者とそのご家族が抱える具体的な悩みや問題、そして潜在的なニーズを深く理解し、それらを解決するための最適なサービスを提案いたします。
例えば、経済的な困難を抱える世帯には、生活保護制度や各種補助金制度の活用、就労支援プログラムなどを紹介します。
また、身体的な障がいを持つ方には、介護保険サービスの利用案内、福祉用具の導入支援、バリアフリー改修に関する情報提供など、多角的なアプローチでサポートを検討します。
個別のケースによっては、サービスの具体的な内容や制度について詳細な説明が必要となる場合もございます。
そのような際には、1回の相談時間を1〜2時間とすることに加え、利用者やご家族が完全に理解し、納得されるまで複数回にわたる話し合いの場を設けることもございます。
利用者とご家族の間で意見の相違が生じることもありますが、それぞれの立場や意向を丁寧に汲み取り、双方が納得できる最適な解決策を導き出すために、時間をかけて調整を図ることを重視しています。
利用者一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかなサポート体制を整えることで、より質の高い支援を実現してまいります。
提案したサービスに関する相談
提案したサービスは、利用者が生活の中で直面するさまざまな問題に対応するため、個別のニーズに合わせて柔軟に調整されることが重要です。
サービスの利用開始後も、利用者の状況やニーズは常に変化する可能性があるため、定期的なフォローアップと再評価が不可欠です。
例えば、介護サービスを利用している高齢者が、病気の悪化により自宅での生活が困難になった場合、社会福祉士は再度ヒアリングを行い、介護保険サービスの利用状況や医療機関との連携、場合によっては介護施設への入居など、新たな選択肢を検討し、最適な支援プランを提案します。
また、精神的なサポートが必要な利用者に対しては、カウンセリングの継続や専門機関の紹介など、心のケアにも配慮した支援を行います。
このように、社会福祉士は一度サービスを提供したら終わりではなく、利用者が抱える課題が解決するまで、長期的な視点を持って寄り添い続けることが求められます。利用者の生活全体を多角的にサポートすることで、より質の高い福祉サービスを提供できるのです。
1日の大まかなスケジュール
社会福祉士の1日の業務例を、午前と午後に分けてみてみましょう。
午前のスケジュール
社会福祉士の午前のスケジュールは、利用者やそのご家族との打ち合わせが中心となります。
これは、利用者のお宅へ訪問するケースと、来所していただくケースの両方を含みます。
例えば、介護サービスの利用状況や生活上の困りごとについて、対面で詳しくヒアリングし、今後の支援計画について話し合います。
また、直接の打ち合わせが難しい場合や緊急性の高い内容については、電話での相談対応も午前中に行います。
これは、利用者の急な体調不良や、緊急の支援ニーズなどに対応するためです。
さらに、医療機関や行政機関、他の福祉サービス提供機関など、各関係機関との連携も重要であり、午前中にメールでの連絡や調整を行うことが一般的です。
例えば、利用者の方に必要なサービスを提供するため、病院の医療ソーシャルワーカーと情報共有を行ったり、自治体の担当者と補助金制度について確認したりします。
これらの業務は、利用者がスムーズにサービスを受けられるよう、午前中の早い時間から計画的に進められます。
午後のスケジュール
社会福祉士の午後の業務は多岐にわたり、主に会議や業務報告資料の作成が中心となります。
施設スタッフや関係機関との会議では、利用者にどのような支援を提供すべきかを詳細に話し合い、それぞれの専門性を活かした最適なサービス内容を検討します。
また、行政担当者との会議も重要な業務の一つです。ここでは、地域における福祉課題を共有し、行政と連携して解決策を協議することで、制度の狭間にいる人への支援や、地域全体の福祉施策の構築に貢献します。
業務報告資料の作成も午後の主要な業務です。
これには、相談内容や支援の経過、関係機関との連携状況などを記録し、上司や関係者と情報を共有する目的があります。
報告書は、利用者の支援状況を客観的に示す重要な資料であり、今後の支援計画やサービスの見直しにも活用されます。
必要に応じて、利用者のご自宅や関係機関を訪問し、直接顔を合わせて打ち合わせを行うこともあります。
これらの業務を通じて、社会福祉士は利用者の生活を多角的にサポートし、より良い社会の実現に貢献しています。
社会福祉士が活躍する主な現場
社会福祉士は、子どもから高齢者、障がい者まで幅広い方を支援の対象としています。
このため就職先も高齢者施設や児童相談所、医療機関などさまざまで、活躍する職場によってその仕事内容や呼び方も変わってくるのが特徴です。
そこでここからは、社会福祉士が活躍している主な現場や具体的な職種名について紹介していきます。
高齢者福祉の現場
社会福祉士が最も多く活躍しているのが高齢者福祉の現場です。
具体的な仕事内容として、高齢者やその家族の相談に応じることが挙げられます。
例えば、特別養護老人ホームやデイサービスでは「生活相談員」、介護老人保健施設では「支援相談員」として、利用者さんの生活に関する様々な相談に対応しています。
また、各市町村が主体となって運営する地域包括支援センターも、社会福祉士が活躍する重要な場です。
地域包括支援センターに勤務する社会福祉士は、地域で暮らす高齢者やその家族に対し、介護保険制度の利用方法や高齢者虐待に関する問題など、幅広い相談に応じています。
ここでは、地域における高齢者の多様なニーズを把握し、適切なサービスへと繋ぐ役割を担っています。
例えば、認知症の初期症状がある方や、ご家族の介護負担が大きいといったケースに対し、医療機関や介護サービス事業者、行政などと連携し、包括的な支援体制を構築します。これにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるようサポートしているのです。
障がい者福祉の現場
社会福祉士が活躍する障害者福祉の現場では、障がいを持つ方が地域で自立した生活を送れるよう、多角的な支援を提供しています。
具体的には、生活支援員として、食事、入浴、排泄などの日常生活のサポートや、家事、金銭管理、健康管理といった日常生活の自立に必要なスキル習得を支援します。
また、職業指導員や就労支援員として、障がいを持つ方の就労をサポートすることも重要な役割です。
ハローワークや就労移行支援事業所などと連携し、就職活動の支援、職場での定着支援、そして必要に応じて就労後のフォローアップを行います。
さらに、社会福祉士は、障がいを持つ方が利用できる福祉サービスの情報提供や申請支援、行政機関との連絡調整なども担当します。
例えば、障害福祉サービスの利用計画作成支援、障害年金などの経済的支援に関する相談、住居の確保に関するサポートなど、個々のニーズに応じたきめ細やかな支援を提供することで、障がいを持つ方が社会の一員として安心して生活できる環境づくりに貢献しています。
児童福祉の現場
社会福祉士は、児童が健やかに成長できる環境を支える重要な役割を担っています。
児童福祉の現場では、児童相談所において児童相談員として、虐待や育児放棄、非行などの問題に直面した子どもとその家族からの相談を受け、適切な支援計画を策定します。
また、一時保護や施設入所の必要性を判断し、子どもの安全を確保します。
例えば、近年増加傾向にある児童虐待の通報件数は、令和4年度には219,170件にのぼり、このうち児童相談所が対応した件数は219,170件と過去最高を記録しています。
このような状況下で、社会福祉士は最前線で子どもたちの命と心を守るために尽力しています。
さらに、児童養護施設や乳児院などの児童福祉施設では、児童指導員や児童支援員として、施設で生活する子どもの日常生活のサポートや、学習支援、集団生活への適応支援などを行います。
子どもの発達段階や個々の状況に応じたきめ細やかな支援を通じて、子どもたちが安心して成長できる環境を整えることが求められます。
教育現場においては、スクールソーシャルワーカー(SSW)として、いじめや不登校、発達障がいなど、子どもが学校生活で抱えるさまざまな問題に対し、学校、家庭、地域との連携を深めながら、総合的な支援を行います。
具体的には、保護者との面談、関係機関との調整、必要に応じて家庭訪問を行うなど、多角的な視点から問題解決に取り組み、子どもたちが安心して学校生活を送れるようにサポートします。
このように、社会福祉士は子どもたちの成長を多方面から支え、より良い未来を築くために不可欠な存在です。
医療の現場
病院などの医療機関でも、社会福祉士は医療ソーシャルワーカー(MSW)として活躍しています。
医療ソーシャルワーカーは、患者さんやその家族が抱える経済的、心理的、社会的な問題を社会福祉の立場から解決へと導く専門職です。
主に病院内の医療相談室や地域医療連携室に所属し、多岐にわたる業務を担っています。
具体的な業務としては、療養中に生じる心理的・社会的な問題の解決や調整援助、退院後の生活を見据えた退院援助、社会復帰に向けた援助などが挙げられます。
例えば、高額療養費制度の説明や手続きサポート、精神的な不安を持つ患者さんへのカウンセリング、転院先の選定支援など、患者さんが安心して療養生活を送れるよう包括的にサポートしています。
また、地域の他の医療機関や介護・福祉施設との連携を図り、地域の保健医療福祉システムづくりに貢献することも重要な役割です。
これにより、患者さんのニーズに合ったサービスが地域全体で提供されるよう調整し、地域における患者会や家族会の支援、ボランティアの育成にも取り組んでいます。
社会福祉士の国家資格について
社会福祉士の国家資格は、年に1回、2月初旬に行われる国家試験に合格することで取得できます。
試験は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが実施します。
受験資格を得る
社会福祉士の受験資格を得る方法は複数あり、ご自身の学歴や実務経験によって選択できるルートが異なります。
福祉系の4年制大学を卒業し、指定科目を履修することで受験資格を得られるルートが代表的です。
また、福祉系の大学を卒業した方、または4年以上の相談援助実務経験がある方は、一般養成施設で1年以上の学習が必要なルートがあります。
基礎科目のみを履修した場合は、短期養成施設で6ヶ月以上の学習を行うルートが選択可能です。
それぞれのルートで求められる知識や実務経験の年数が異なるため、ご自身に合ったルートを選ぶことが大切です。
社会福祉士国家試験の受験指定科目
社会福祉士国家試験は、社会福祉に関する幅広い知識と専門性を問うものです。
合格のためには、医学概論や心理学と心理的支援、社会学と社会システムといった基礎科目に加え、社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度など、法律や制度に関する知識も不可欠です。
さらに、地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、高齢者福祉、児童・家庭福祉、貧困に対する支援といった各分野における具体的な支援方法や課題についても深く理解する必要があります。
特に、ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、福祉サービスの組織と経営といった科目は、実践的なソーシャルワークを行う上で核となる知識です。
これらの科目は、「専門科目」としてさらに深く掘り下げて学ぶことが求められます。出題形式は五肢択一を基本とし、総得点の60%程度の正答で合格となります。
そのため、得意な科目で高得点を狙うだけでなく、苦手な科目もまんべんなく学習し、知識の偏りがないようにバランスよく対策を進めることが重要です。
社会福祉士国家試験の受験指定科目
社会福祉士国家試験は、以下19の指定科目があります。
・医学概論
・心理学と心理的支援
・社会学と社会システム
・社会福祉の原理と政策
・社会保障
・権利擁護を支える法制度
・地域福祉と包括的支援体制
・障害者福祉
・刑事司法と福祉
・ソーシャルワークの基盤と専門職
・ソーシャルワークの理論と方法
・社会福祉調査の基礎
・高齢者福祉
・児童・家庭福祉
・貧困に対する支援
・保険医療と福祉
・ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
・ソーシャルワークの理論と方法(専門)
・福祉サービスの組織と経営
これら全19科目を幅広く勉強し、試験対策を進めていかなければなりません。
合格基準点は、90点(正答率60%)ですが、指定科目のうち0点の科目が一つでもあれば不合格となります。
国家試験を受ける
社会福祉士国家試験は、例年2月上旬に実施されています。
全問マークシート形式で五肢択一または五肢択二となっており、問題数は全部で129問、1問1点の129点満点です。
合格基準は60%の正答率が目安とされています。
また、社会福祉士の資格をお持ちの方や、精神保健福祉士として登録中の方、あるいは申請中の方は、必要書類を提出することで共通科目の受験が免除されます。
制度の変更には注意!
社会福祉士の受験資格や制度は、今後変更される可能性があるため注意が必要です。
特に2027年度以降は、一部のルートにおいて要件が厳格化される見込みですので、資格取得を目指している方は、早めに養成機関への進学や受験時期を検討することをおすすめします。
制度変更に関する最新情報は、常に公的機関の情報を確認し、自身のキャリアプランに合ったルートで社会福祉士の資格取得を目指すことが重要です。
社会福祉士の資格取得までの道のり
社会福祉士の資格を取得するまでの道のりは、大きく分けて3つのルートがあります。
・指定科目ルート
・基礎科目+6か月以上の養成施設ルート
・一般大学・短大または4年以上の実務+1年以上の養成施設ルート
これらのルートについて、詳しく見ていきましょう。
指定科目ルート
福祉系大学などで「指定科目」を履修するルートは、社会福祉士の資格取得を目指す主要な道のりの一つです。
指定科目は、社会福祉の原理と政策、社会保障、心理学と心理的支援など、全19科目で構成されています。
これらの科目を大学で学ぶことで、社会福祉士として必要な専門知識を体系的に習得できます。
このルートでは、最終学歴によって求められる相談援助の実務経験の期間が異なります。
4年制の福祉系大学で指定科目を履修し卒業した場合は、相談援助の実務経験は不要です。
しかし、3年制の福祉系短大で指定科目を履修した場合は1年間、2年制の福祉系短大で指定科目を履修した場合は2年間の相談援助実務が別途必要となります。
相談援助の実務経験とは、厚生労働省が指定する職種で福祉に関する相談支援業務に従事することです。
具体的には、児童相談所の児童福祉司、介護老人保健施設の支援相談員、身体障害者更生相談所の身体障害者福祉司などが挙げられます。
これらの実務経験を通じて、実践的なスキルと知識を深めることができます。
また、入学した年度によって指定科目の内容が異なる場合があるため、自身の履修状況を公益財団法人社会福祉振興・試験センターのウェブサイトなどで確認することが重要です。
基礎科目+6か月以上の養成施設ルート
福祉系の大学で基礎科目を履修した方が、社会福祉士の資格取得を目指す場合、「基礎科目+6か月以上の養成施設ルート」を選択することが可能です。
このルートでは、大学で基礎科目を修了後、さらに6か月以上の期間、社会福祉士養成施設で専門的な履修を行う必要があります。
具体的には、福祉系大学で3年間基礎科目を履修した場合は、卒業後1年間、相談援助の実務経験を積む必要があります。
同様に、2年間基礎科目を履修した場合は、2年間の相談援助の実務経験が求められます。
しかし、4年間福祉系大学で基礎科目を履修し卒業した場合は、相談援助の実務経験は不要です。
これらの条件を満たした上で、6か月以上養成施設に通うことで、社会福祉士国家試験の受験資格が得られます。
このルートは、大学入学から最短4年半で社会福祉士の資格取得が可能となるため、比較的早く資格を取得したい方にとって有効な選択肢と言えるでしょう。
養成施設では、実践的な知識やスキルを習得し、国家試験合格に向けた対策も行われます。
一般大学・短大または4年以上の実務+1年以上の養成施設ルート
一般の大学や短期大学を卒業後、社会福祉士を目指す場合は、指定された養成施設に1年以上通学し、必要な知識と技術を習得する必要があります。
このルートでは、大学や短大で福祉系以外の学部を卒業した場合や、福祉系の学部を卒業しても指定科目を履修していない場合に適用されます。
また、実務経験の有無によって養成施設への通学期間が異なる場合があります。
例えば、4年制大学で福祉系科目を履修していない場合は、1年以上の養成施設での学習が必要とされています。
さらに、大学や短期大学を卒業していなくても、相談援助の実務経験が4年以上あれば、4年制大学卒業と同等の要件を満たすことができ、養成校への受験資格が得られます。
この場合も、1年以上の養成施設での学習が必須となります。最短で5年での資格取得が目指せるルートです。
社会福祉士の養成施設には、日中に通学する形式のほかに、夜間制や通信制の大学・専門学校も存在します。
これは、社会人として働きながら資格取得を目指す方にとって大きなメリットです。
例えば、通信制の養成施設であれば、自分のペースで学習を進めることができ、仕事や家庭との両立がしやすいため、社会人からのキャリアチェンジを目指す方々に広く利用されています。
受験資格の「実務経験」とは?
社会福祉士の受験資格として求められる実務経験とは、指定された福祉分野における相談援助業務のことを指します。
これは座学で得た知識を実践で活かすための大切な要素であり、社会福祉士として必要なワーカーの役割を理解し、その職種における専門的な知識を深めるために不可欠です。
例えば、児童福祉分野では、保育士としての経験が実務経験として認められる場合があります。
また、高齢者福祉や障害者福祉の現場でケースワーカーとして働く経験もこれに該当します。
このように、実務経験として認められる職種は多岐にわたり、1年以上の経験を求められるケースがほとんどです。
実務経験として認められない職種とは?
社会福祉士の受験資格に必要とされる実務経験には、一部認められない職種があります。
例えば、介護業務を行う指導員や訪問支援員、障害福祉サービス経験者は、実務経験として認められません。
また、入所者の保護に直接従事する児童指導員や保育士も、社会福祉士の受験資格となる実務経験には該当しません。
これらの職種が実務経験として認められないのは、社会福祉士に求められる専門的な相談援助業務の経験が十分に得られないためです。
社会福祉士の資格取得を目指す際は、ご自身の職種が受験資格の実務経験に該当するかどうかを事前に確認することが重要です。
社会福祉士の国家試験合格率と難易度
社会福祉士の試験は、福祉系国家資格の中で最も難易度が高いと言われています。
以下は、福祉系国家試験のおおよその合格率です。
| 資格 | 合格率 |
| 社会福祉士 | 40%前後 |
| 介護福祉士 | 70%前後 |
| 精神保健福祉士 | 60%前後 |
このように、他の資格と比較して圧倒的に合格率が低いことがわかります。
その大きな理由の一つとしては、19科目という試験範囲の広さです。
専門用語や制度など、覚えなければならない知識がかなり多くあります。
また、全科目を学習するのに必要な時間は300時間とされており、この時間を学校や養成施設に通いながら、もしくは働きながら確保するのは困難であることがほとんどです。
受験日までに、合格できるレベルまで知識を身につけられないことも、合格率の低さに影響している可能性があります。
ただし、2023年の社会福祉士国家試験合格率は44.2%と、例年より高い合格率に。ここ数年、自宅でしっかりと知識を身につける時間を取れるようになったことなどが要因となっていると考えられます。
社会福祉士の国家資格取得におすすめの勉強方法
社会福祉士の国家資格取得を目指す上で、効率的な勉強方法は合否を左右します。
最新の制度を理解するためには、情報が常にアップデートされている専門学校のカリキュラムを活用することがおすすめです。
専門学校では、社会福祉士の国家試験で出題される19科目に対応した効率的な学習計画が用意されており、専門的な知識を体系的に学ぶことができます。
これにより、法改正や社会情勢の変化に伴う福祉制度の違いにも対応できるようになり、広範な試験範囲を網羅しながら質の高い知識を習得することが可能です。
社会福祉士と他の福祉系国家資格の違い
社会福祉士以外にも、他の福祉系の国家資格としてはさらに、精神保健福祉士や介護福祉士などがあります。
これらは、社会福祉士と合わせて3福祉士と呼ばれることもあるほど、社会福祉における代表的な資格です。
それでは、社会福祉士とこれら2つの資格には、一体どのような違いがあるのでしょうか?
それぞれの仕事内容や活躍する場所についても紹介していきます。
精神保健福祉士(国家資格)との違い
社会福祉士と精神保健福祉士は、どちらもソーシャルワーカーとして相談援助業務に携わる国家資格です。
共通点も多い一方で、支援の対象者や仕事内容、活躍する場に違いがあります。
社会福祉士は、高齢者、障がいのある方、子ども、ひとり親家庭など、多様な背景を持つ人々やさまざまな環境上の理由で日常生活に困難を抱える方々を幅広く支援します。
例えば、介護保険や補助金制度の案内、施設入居や介護サービス利用の手続き支援など、多岐にわたる相談に対応し、問題解決に向けた助言やサポートを行います。
就職先も高齢者施設、児童相談所、医療機関、行政機関など多岐にわたります。
これに対し、精神保健福祉士は、主に精神的な病気や障がいを抱える方とその家族を支援します。
その主な役割は、精神障害を抱える方の社会復帰や日常生活への適応をサポートすることです。
具体的には、精神科病院での退院支援や、地域での生活支援、就労支援、医療機関や福祉サービスとの連携などを行います。
精神保健福祉士の活躍の場は、精神科病院や心療内科、精神保健福祉センターなどの専門機関が中心ですが、障がい者福祉サービス事業所、行政機関、教育機関、企業のメンタルヘルス部門など、社会福祉士と共通する領域でも活動しています。
このように、両者は支援の専門性が異なるため、ご自身がどのような対象者を支援したいかによって、目指す資格を選択することが重要です。
介護福祉士(国家資格)との違い
社会福祉士や精神保健福祉士と同じく、介護福祉士も福祉分野の国家資格です。
名称に「福祉士」と付くため混同されがちですが、それぞれの役割は明確に異なります。
社会福祉士や精神保健福祉士が主に相談援助業務を通じて利用者の課題解決を支援するのに対し、介護福祉士は、介護施設や訪問介護事業所などで、利用者に直接介護サービスを提供する専門職です。
具体的には、食事や入浴、排せつといった身体介護のほか、着替えの介助や移動のサポート、調理や洗濯などの生活援助も行います。
介護福祉士が活躍する場は、特別養護老人ホームやデイサービスセンター、グループホームといった高齢者施設に加え、訪問介護事業所など多岐にわたります。
介護を必要とする方の日常生活を直接的に支え、生活の質の向上に貢献することが、介護福祉士の重要な役割です。
ケアマネジャー(公的資格)との違い
ケアマネジャーは、介護保険制度に基づく公的資格であり、主に介護が必要な利用者に対してケアプランを作成し、介護サービスの調整を行う役割を担います。
社会福祉士が福祉全般の相談援助を行うのに対し、ケアマネは介護保険サービスに特化している点が大きな違いです。
資格取得には、介護福祉士や医療分野の国家資格を持ち、5年以上の実務経験が必要となります。
また、利用者へのサービス提供後もモニタリングを通じて、適切なサービスが提供されているかを確認し、必要に応じてプランを見直していく点も特徴です。
地域包括支援センターなどでは、社会福祉士とケアマネが連携し、包括的な支援体制を築いています。
どの資格が向いているかの基準は?
福祉の資格選びは、自分が「誰の支援をしたいか」「どのような役割で仕事をしたいか」によって変わってきます。
社会福祉士は相談援助を軸とした支援の設計者としての役割が強く、現場全体の支援体制を見渡す仕事に向いています。
一方、介護福祉士は直接的なケア、精神保健福祉士は精神医療と地域福祉の橋渡し、ケアマネは制度運用の実務家としての側面が強いです。
各資格には異なるやりがいや課題があり、それぞれが福祉の現場で欠かせない存在であることに変わりはありません。
目指すキャリアに応じて、資格選択を慎重に行うことが大切です。
社会福祉士に向いているのはこんな人
社会福祉士は、相談業務が中心となるため、利用者と信頼関係を築き、困りごとを的確に聞き出すためのコミュニケーション能力は必須です。
傾聴力も重要であり、相手の話を真摯に聞き、共感する姿勢が求められます。
また、利用者の抱える悩みに寄り添い、サポートすることが大切であるため、人のサポートをすることに喜びを感じ、相手の立場になって解決方法を考えられる人は社会福祉士に向いていると言えるでしょう。
加えて、社会福祉士は多岐にわたる社会福祉制度や法律に関する知識が不可欠であり、常に最新情報を学び続ける向上心も重要です。
倫理観やコンプライアンス意識も高く求められ、相談者のプライバシー保護を徹底し、誠実な対応を心がける必要があります。
また、困難な状況に直面しても感情的にならず、冷静に対応できる自己管理能力や、多職種との連携・協調性も社会福祉士にとって大切な資質です。
社会福祉士のやりがいとは?
社会福祉士の仕事は、多様な背景を持つ利用者が抱える課題に対し、さまざまな機関と連携しながら解決に導く点に大きな魅力があります。
この社会福祉士という職種は、利用者一人ひとりが自分らしい生活を取り戻せるよう、医療機関や行政機関など多職種と協力し、その人の持つ力を引き出す役割を担います。
特に、「ありがとう」という感謝の言葉は、仕事のやりがいを強く実感できる瞬間です。
地域社会全体の支援を視野に入れ、人と地域をつなぐ重要な仕事であり、この仕事を通して、多くの人と関わり、社会に貢献できることが社会福祉士という仕事の大きな魅力と言えるでしょう。
社会福祉士の給与などの待遇や働き方について
社会福祉士の気になる平均年収
社会福祉士の平均年収は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが実施した令和2年度の調査によると403万円です。
月給に換算すると約33.5万円となり、安定した収入が見込めます。この平均年収は、平成27年度の調査と比較して26万円増加しており、5年間で給与水準が上昇傾向にあることが分かります。
社会福祉士の重要性が高まっている背景には、日本社会の高齢化や福祉ニーズの多様化が挙げられます。
男女別の平均年収では、男性が473万円に対し、女性は365万円と約100万円の差があります。
これは、女性の社会福祉士が非正規雇用で働く割合が高いことが主な要因と考えられています。
実際、正社員の社会福祉士に限ると、約半数が平均年収の403万円を超えているというデータも存在します。
さらに、社会福祉士の年収は、職種や役職、経験年数、勤務先によっても変動します。
例えば、経営者や施設長、主任などの管理職に就くと、平均年収が500万円前後と高くなる傾向にあります。
また、保護観察所や児童相談所など、高度な専門性や公務員試験の合格が求められる勤務先では、平均年収が高い傾向が見られます。
一方で、スクールソーシャルワーカーなど非正規雇用の割合が高い職種では、年収が低い傾向にあることもあります。
勤続年数を重ねることで年収は上昇し、50代でピークを迎える傾向があるため、長期的なキャリア形成が収入アップにつながると言えるでしょう。
社会福祉士の働き方は?
社会福祉士の働き方は、勤務先によって大きく異なります。
行政の職員として働く場合、基本的に土日祝日が休みとなることが多いですが、関係機関との連携や家庭訪問などで土日に業務が入ることもあります。
一方、民間施設で働く社会福祉士は、シフト制が導入されている場合が多く、必ずしも土日休みとは限りません。
特に、有料老人ホームや障害者支援施設などの24時間稼働する施設では、他の職員と同様にシフト制で勤務し、夜勤が発生する可能性もあります。
民間施設では、利用者の相談対応が主な業務となるため、施設の営業時間に合わせて日勤が基本ですが、早番や遅番、あるいは夜勤を含むシフトが組まれることもあります。
社会福祉士の需要と将来性
高齢化が進む日本では、高齢化福祉に関わる仕事の需要がずっと上がっています。
高齢化福祉の業界はベースとして人手不足であることもあり、就職先に困ることはないでしょう。
また、医療施設や介護施設、学校、少年院など、社会福祉士が活躍できる場は多岐に渡ります。
一つの分野での需要が落ち着いても、他の分野での活躍が見込めるため資格を取っておいて損はありません。
AIやロボットの技術が進んでいく中で職が失われていく懸念がありますが、人と人とのコミュニケーションが重視される社会福祉士の仕事は、機械に変えることはできません。
適切なプランや施設の案内は可能かもしれませんが、「話を聞いてもらいたい」「支えになってもらいたい」といったニーズを満たす心のケアは、ロボットではなく人であることが重要です。
このような理由から、近い将来では社会福祉士の需要が減少することは考えにくいでしょう。
社会福祉士の社会的ニーズ
社会福祉士は、現在の日本社会において非常に高いニーズがあります。
特に、高齢化の進行により、65歳以上の人口が全体の約30%に達すると予測される2025年以降は、高齢者支援のニーズがさらに増加すると考えられます。
厚生労働省が掲げる「地域共生社会」の推進や、医療・福祉連携の強化により、社会福祉士、つまりソーシャルワーカーの専門性が強く求められています。
複雑化する社会的孤立や困窮といった問題に対応するため、社会福祉の専門知識と相談援助の内容を熟知したワーカーの重要性は増しており、制度上もその専門性への期待が高まっています。この5年間で平均年収が向上していることからも、その需要の高さがうかがえます。
社会福祉士のキャリアパス
社会福祉士は、相談援助の専門職として多岐にわたるキャリアパスが考えられます。
例えば、福祉施設での相談援助職から、主任や施設長への昇格を目指すことが可能です。
また、行政職への転身も一つの道であり、福祉事務所や自治体でケースワーカーなどの職種に就くこともできます。
さらに、医療分野で医療ワーカーとして専門性を高め、チームリーダーやスーパーバイザーになる方もいます。
独立して「独立型社会福祉士」として活動する、あるいは上位資格である認定社会福祉士や精神保健福祉士の取得を目指し、より深い専門性を追求する選択肢もあります。
社会福祉士についてのよくある質問
ここでは、社会福祉士についてよくある質問をまとめました。ここまでで解決できない疑問がある方は目を通してみてください。
社会福祉士として働く方の年齢層や性別は?
年齢層の傾向
社会福祉士として就業している方の年齢層は、厚生労働省の調査によると、30代から50代の中堅層が中心となっています。
一方で、60歳以上のベテラン層も全体の約14.5%を占めており、長年の経験と専門性を活かして活躍しています。
社会福祉士の国家試験合格者の年齢層も多様であり、特に31歳以上の合格者が全体の半数以上を占めていることからも、幅広い年代の方が福祉士としてキャリアを築いていることがわかります。
高齢化が進む現代社会において、60歳以上の社会福祉士の需要は高く、今後もその専門性が社会に求められるでしょう。
性別の傾向
社会福祉士の性別構成は、女性が約7割、男性が約3割と女性が多数を占める職種です。
しかし、性別によって仕事内容に差はなく、昇進に関しても有利不利はありません。
社会福祉士の仕事は、相談・支援が主な業務であるため、基本的に筋力や体力を必要としないことが、女性に人気の理由の一つと考えられます。
また、福利厚生が充実している職場が多く、ライフイベントの多い女性でも、結婚・出産・育児といったライフスタイルに合わせて働き方を変えやすい点も、女性が無理なく仕事を続けられる要因となっています。
近年では男性の社会福祉士も増加傾向にあり、福祉の現場では男女問わず、社会福祉士の専門性やスキルを持つ人材へのニーズが高まっています。
社会福祉士の資格は通信で取れる?
社会福祉士の資格は通信教育でも取得を目指せます。
ただし、国家試験の受験資格を得るためには、通信教育で学習するだけでなく、実習や実務経験が必須となります。
通信制の大学や専門学校、養成施設では、社会福祉士国家試験の受験科目を自宅で学習できますが、そのカリキュラムには相談援助の実習が含まれており、この実習は実際に福祉現場で行う必要があります。
具体的には、相談援助の実務経験がない場合、最低でも240時間(約1か月半から2か月程度)の実習期間を確保する必要があるため、計画的な学習と実習準備が重要です。
また、通信教育は自分のペースで学習を進められるメリットがある一方で、学習の進捗管理を自己責任で行う必要があり、強い学習意欲が求められます。
通信教育と実習を組み合わせることで、多様なライフスタイルを持つ方が社会福祉士を目指せる道が開かれているのです。
専門学校なら現場実習を通じて実際の業務を体験出来る!
社会福祉士の資格取得を目指す上で、実習は必須の要素です。
専門学校のカリキュラムには、現場実習が組み込まれており、実際の福祉現場で社会福祉士の仕事内容を肌で感じることができます。
具体的には、特別養護老人ホームや地域包括支援センター、病院など多様な機関で実習を行い、利用者との関わり方や相談援助の進め方を実践的に学ぶことが可能です。
この実習を通じて、講義で学んだ知識がどのように現場で活かされているのかを体験的に理解し、将来の社会福祉士としての仕事のイメージを明確にすることができます。
専門学校によっては、実習先の選定や指導において手厚いサポート体制を整えているため、安心して実習に取り組めるでしょう。
社会福祉士に年齢制限はある?
社会福祉士には、資格取得や働く上での年齢制限は設けられていません。
このため、何歳からでも資格取得に挑戦でき、社会人になってからのキャリアアップとして目指す方も多くいらっしゃいます。
実際に、社会福祉士国家試験の合格者のうち、約半数は31歳以上の方が占めています。
特に30代から50代の中年層が多く、50代でキャリアチェンジをされた方もいるほどです。
人生経験や社会経験が豊富な方は、相談業務で利用者と信頼関係を築く際に強みとなる場合もあります。
働き方によって定年が設定されている場合もありますが、多様な働き方が存在する社会福祉士は、70歳を超えても非常勤で活躍されている方もいます。
独立開業することで、定年を気にせずに働き続けることも可能です。
もし50代以上で未経験から社会福祉士を目指す場合は、最初から正職員を目指すのではなく、非常勤や契約社員として経験を積んでから正職員への登用を目指すのが良いでしょう。
社会福祉士は、高齢化社会において需要が高まっており、年齢に関係なく長く働き続けられる職種と言えるでしょう。
まとめ~社会福祉士とは?~
社会福祉士は、1987年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて誕生した国家資格であり、ソーシャルワーカーとも呼ばれる福祉の専門職です。
身体的、精神的、経済的な理由で日常生活に困難を抱える方々に対し、相談支援、福祉サービスの調整、関係機関との連携を通じて問題解決をサポートします。
具体的には、高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者、被虐待者、出所者など、幅広い対象者を支援します。
社会福祉士の主な仕事内容は、相談業務、支援サービスの管理業務、各関係機関との連絡・調整、そして介護業務の4つに大別されます。
利用者の状況に応じた適切な福祉サービスや公的制度の活用を提案し、その手続きを支援します。
また、医師や介護施設、行政機関などと連携し、利用者にとって最適なサービス提供ができるよう調整役を担うことも重要な役割です。
介護施設などに勤務する場合は、直接的な介護業務に携わることもあります。
社会福祉士と似た職種に精神保健福祉士がありますが、両者の大きな違いは支援対象にあります。
社会福祉士が多岐にわたる生活課題を抱える人々を支援するのに対し、精神保健福祉士は主に精神障がいを抱える人々を対象とし、社会復帰や日常生活への適応を支援します。
そのため、精神保健福祉士は精神科病院や精神保健福祉センターなど、精神科に特化した場所で活躍することが多いです。
どちらの資格も相談援助を主な業務としますが、活躍したい分野によって選ぶ道が変わるでしょう。
もし精神障がいを抱える人々の支援に特に関心がある場合は、精神保健福祉士という職業についても深く知ることが推奨されます。
>>資料請求はこちら
社会福祉士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の社会福祉士科では、夜間1年でスクールソーシャルワーカーはもちろん、その他医療や福祉の現場でソーシャルワーカーとして幅広く活躍できる社会福祉士の資格取得が目指せます。
夜間制で授業時間は基本的に18時10分〜のため、日中は仕事で忙しい社会人の方でも無理なく通学できます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや社会福祉士科の詳細情報をご覧ください。
また、社会福祉士科の学科の詳細を知りたい方は「社会福祉士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。