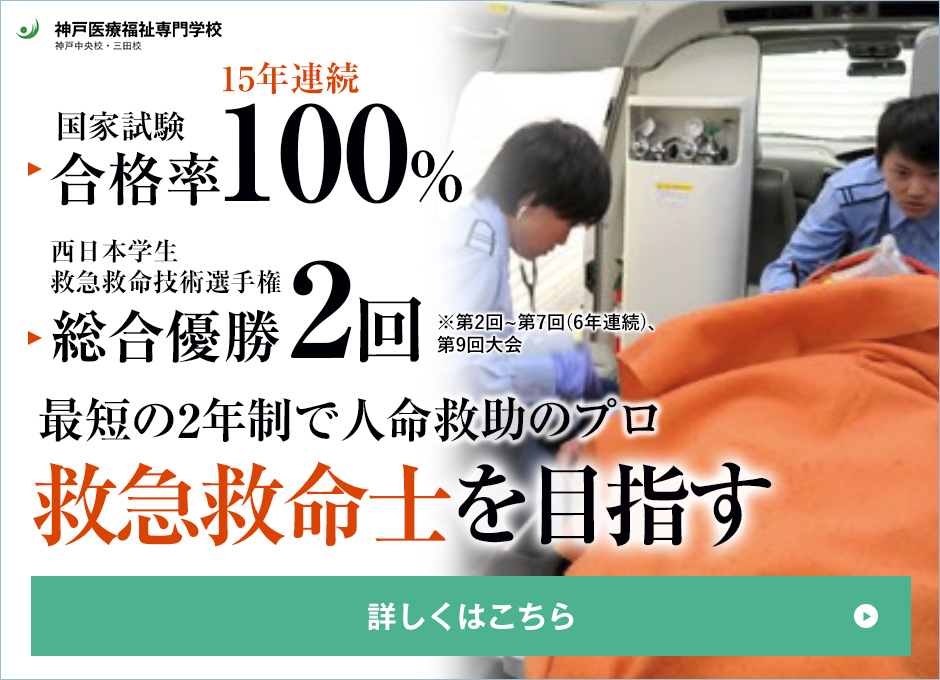誰でも一度は、被災地などで活躍している消防士や救急救命士の姿を見て「かっこいい」と憧れたことがあるのではないでしょうか。
その一方で、「実はいまいち消防士と救急救命士の違いが分かっていない」「救急車に乗っている人は全員救急救命士なの?」などの疑問がある方も多いかもしれませんね。
そこでこの記事では、意外と知らない消防士と救急救命士の関係について紹介。
さらに具体的な仕事内容や出動から救急搬送までの流れ、それぞれの目指し方などについても解説していきます。
将来命を救う職業に就きたいと考えている方や、消防士や救急救命士の仕事に憧れがあるという方はぜひ参考にしてください。
目次
消防士と救急救命士の関係
消防士と救急救命士の関係を簡単に説明すると、救急救命士は消防士がもつ資格の1種です。
消防士は、火災や交通事故、災害現場などに急行し、火災の消火や人命救助にあたります。
消防士の中でも救急車で傷病者のもとに救急隊員として駆けつけ、応急処置や病院への搬送を行うのが救急隊員で、その中でも特別な処置をすることができる資格を持つのが救急救命士です。
消防士の仕事内容

火災や事故、そして地震や風水害などのさまざまな災害から地域住民を守るのが消防士の役割です。
消防士の現場の業務は大きく分けて消火活動・救助活動・救急活動の3つに分かれています。
消火活動
消防車で火災現場に駆けつけ、消火を行う仕事です。
炎や煙の中でも活動できるように防火服や空気呼吸器を装着し、火事の現場で火を消します。
消火隊はおよそ3〜4名で編成され、隊をまとめる小隊長、消防車を動かす機関員、水を出して放水する隊員などにわかれて活動します。
救助活動
交通事故や火災、災害などの現場で救助活動をする仕事です。
煙の中でも目立つようオレンジ色の救助服を着て、危険な場所での人命救助にあたります。
救助隊は主に4名で編成され、隊をまとめる小隊長、救助車を運転する機関員、色々な資器材を使用して活動する隊員などにわかれて活動します。
救急活動
救急車で現場に駆けつけ、傷病人を救急車で病院へ搬送しながら応急処置を施す仕事です。
現場や救急車内で病人や怪我人の初期対応や、医療機関に到着するまでの応急処置をおこないます。
救急隊は主に3名で構成され、隊をまとめる小隊長、救急車を運転する機関員、救命のために応急処置を施す隊員などにわかれて活動します。
そのほか、地域住民の防火・防災意識を高めるために啓蒙活動や指導を行う防災活動や、火災や災害の発生予防のために、建物の消防設備や安全性をチェックする予防活動なども消防士の仕事です。
救急救命士の仕事内容

消防士の中でも救急救命士は主に救急隊員として活躍しています。
救急隊員のなかでも人命救助のスペシャリストとして、事故現場や救急車の車内などで特別な救命処置を行うのが仕事です。
ただし、救急隊の全員が救急救命士の資格取得者というわけではありません。
東京消防庁や政令市など大規模な消防本部の救急隊ではそういったケースも見受けられますが、全国的にはごく一部です。
消防庁では、すべての救急車に最低1名は救急救命士が乗車することを目標に、救急救命士の養成と運用体制の整備を推進しています。
一般隊員と救急救命士の違い
救急隊の一般隊員と救急救命士では、扱える処置に違いがあります。
一般の救急隊員も傷病者の救急処置を行うことができますが、救急救命士はそれよりさらに高度な処置を行うことが可能です。
具体的には、医師の指示のもとで以下のような救急救命処置を施す権限が与えられています。
| 対象 | 特定行為 | 備考 |
|---|---|---|
| 心肺停止状態の傷病者 | 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液 | |
| 器具を用いた気道確保 | ||
| 薬剤投与(アドレナリン) | ||
| 心肺停止前の傷病者 | 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液 | ショック又はクラッシュ症候群が疑われる場合が対象 |
| ブドウ糖溶液の投与 | 血糖測定により低血糖状態が確認された場合が対象 |
このように救急救命士が医師の指示を受けて行なう救急救命処置は特定行為とも呼ばれます。
従来、こういった特定行為は、心肺停止状態の傷病者でなければ行うことができませんでした。
しかし、平成26年4月に救急救命士法施行規則が改正され、心肺停止前の傷病者にも特定行為が認められるようになり、救急救命士が行える処置範囲が広がりました。
救急救命士の仕事の流れ

それでは、消防士として救急隊に所属している救急救命士はどのように働いているのでしょうか?
実際に、出動指令を受けてから救急救命処置を行うまでの流れを見てみましょう。
指令センターへ119番通報が入ると、指令員は内容を聞き適切な隊を選びます。消防署ではブザーと共に出動指令が流れ、選ばれた隊のランプが点滅。救急の指令だった場合、救急隊は指令センターの情報を元に救急車に乗って現場へと急行します。
現場に到着したら隊長と隊員が傷病者のもとに駆けつけ、1人は容態を確認、呼吸や脈を確かめ、心電図で様子を見るなど必要な処置を施します。
万一、心肺停止状態に陥っている場合は、救急救命士が心臓マッサージや人工呼吸などの心肺蘇生を行います。
その間にもう1人は家族や関係者などに詳しい状況を確認し、機関員はストレッチャー(担架)を出すなど傷病者を救急車に乗せるための準備をします。
病院への搬送中も、救急救命士は病院や救命センターにいる医師と連絡を取り合いながら救急救命処置を続けます。
病院に到着し、医師に処置の引き継ぎを無事に終えたら任務は終了です。
消防署に帰って、新たな出動命令のために待機します。
救急隊は、多い時は1日で10回以上の出動があります。
救急救命士になるには

救急救命士として活躍するためには救急救命士の資格を取得し、なおかつ消防官の採用試験に合格する必要があります。
大きく分けると、救急救命士の資格を取得してから消防士として就職する、または消防士として就職してから救急救命士の資格を取得するという2つのパターンがあります。
救急救命士の資格を取得後、消防士として就職
1つ目は高校卒業後、救急救命士の養成課程のある専門学校や大学、短大などで学び、救急救命士の資格を取得してから消防士を目指す方法です。
文部科学大臣指定の大学または厚生労働大臣が指定する学校で2年以上学び、所定の課程を修了することで、救急救命士国家試験の受験資格が得られます。
その後は各自治体の消防士採用試験を受験し、年1回行われる救急救命士国家試験を受験。
両方に合格することで、救急救命士の資格を持った消防士として働くことが可能です。
消防士になってから救急救命士の資格を取得
2つ目は、消防士になってから救急救命士の資格取得を目指す方法です。
消防士となり、5年以上または2000時間以上の救急業務を経験し、さらに救急救命士養成所で6ヵ月以上の研修を受け、救急救命士国家試験を受験し取得します。
こちらの方法は学費は当然必要ないですが、各自治体の消防署から選抜されることによるプレッシャーとの闘い、半年間で救急救命士に必要な実習、病院実習、国家試験の勉強をこなすのは現実的には相当大変な道のりといえるでしょう。
また、高校卒業後養成校に通う方法なら、最短2年で救急救命士の資格が取得できます。
それに対して、消防士になってから救急救命士の資格取得を目指すには、5年以上の勤務もしくは2000時間以上の救急業務の経験が必要です。
そこからさらに半年以上の研修も受けなくてはならないため、救急救命士となるまでの道のりは長くなってしまいます。
神戸医療福祉専門学校 救急救命士科では
神戸医療福祉専門学校 救急救命士科は、 最短2年で救急救命士の資格取得が目指せる専門学校です。
今までも消防や救急救命の現場に即戦力となる人材を数多く輩出しており、実際に国家試験の合格率は14年連続100%!
病院実習やシミュレーション実習などの豊富な実習授業で、現場ですぐに即戦力となる救急救命士が目指せます。
救急救命士の消防士以外の就職先は何がある?

現代日本において、救急業務を主に担っているのは消防機関です。
このため現在、救急救命士の資格を活かして働くためには、消防士となることがほぼ規定のルートとなっています。
しかし、なかには病院や自衛隊、警備会社や医療機器会社などで働いている救急救命士もいます。
特に近年では、2021年10月に救急救命士法施行規則が一部改正されたことにより、病院に勤務する救急救命士は増加しています。
従来では、病院勤務の救急救命士の業務は救急患者の受け入れや転院時の対応などに限られていました。
しかし、今回の法改正により救急外来で医療チームの一員として救急救命処置を行うことが可能となったのです。
今後は病院内でこれまで以上に救急救命士の活躍の幅が広がっていくことが期待されています。
まとめ
救急救命士は主に救急車内や救急の現場で医療行為を行うための資格です。
このため救急救命士の資格取得者の約66%は、救急車の運用を担う消防機関に所属し、消防士として働いています。
救急救命士の資格取得者は救急隊の一般隊員と比べて、より高度な救急救命措置処置が可能です。
できる処置が多いということはそのぶん助けられる命も増えるということですから、消防士となってより多くの命を救いたいと考えているなら、ぜひ取得を目指すべき資格だといえるでしょう。
ただし、消防士になってから救急救命士の資格取得を目指すには、5年以上の勤務もしくは2000時間以上の救急業務の経験が必要となります。
このため今から救急救命士および消防士を志すのであれば、高校卒業後、救急救命士養成校に進学するのがおすすめです。
神戸医療福祉専門学校 救急救命士科なら、2年という最短期間で救急救命士の資格を取得することが可能です。
同じ夢を持った仲間といっしょに、市民の安心安全を守る消防士を目指しませんか?
まずは資料請求やオープンキャンパスへの参加をお待ちしております。
救急救命士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の救急救命士科では、国家試験の合格率は、15年連続で100%!(※2009〜2023年度実績)
最短の2年制で人命救助のプロを目指す! 2年間という限られた期間で、消防や救急救命の現場に即戦力となる技術力が身に付けることができます。
国家試験対策は1年次から実施され、習熟度別に学習をサポート、学生一人ひとりの状況を把握し、国家試験対策担当の教員との情報共有を徹底し、学生が主体的に取り組めます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや救急救命士の詳細情報をご覧ください。
また、救急救命士科の学科の詳細を知りたい方は「救急救命士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「神戸医療でのシミュレーション実習のおかげで実践力が身につき、どんな現場にも柔軟に対応できている」(兵庫県立播磨南高等学校出身)
「現場をリアルに想定したシミュレーション実習を数多くこなせたことが、とても役立っている」(兵庫県立北条高等学校出身)
「学校で学んだシーンに遭遇する場面もある」(鳥取県立八頭高等学校出身)
「採用後は即戦力の隊員として隊長指揮下に入りました。」(愛媛県立今治工業高等学校出身)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!