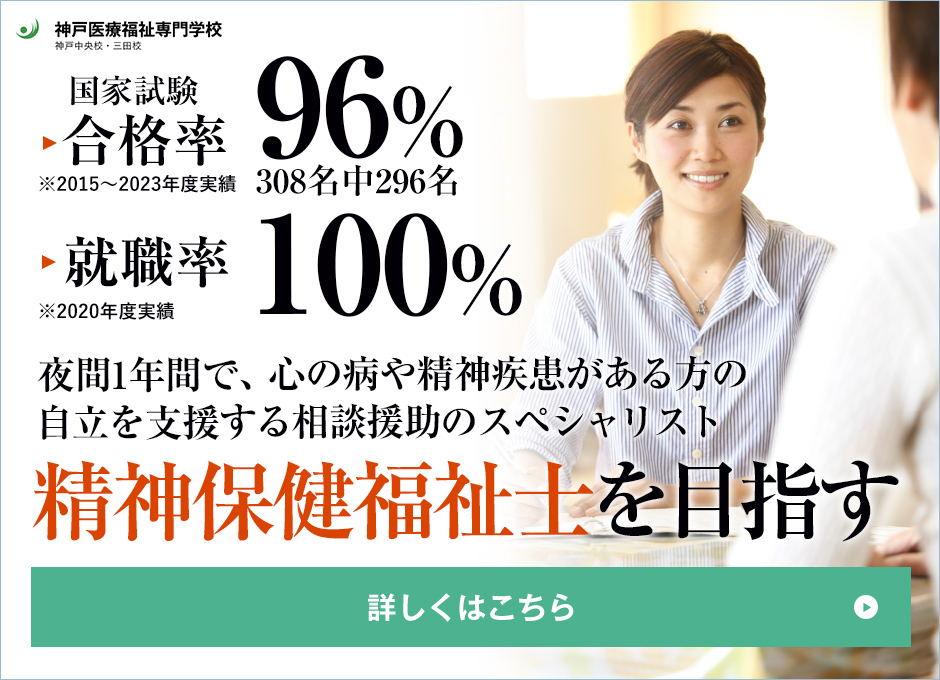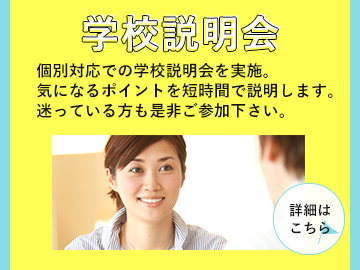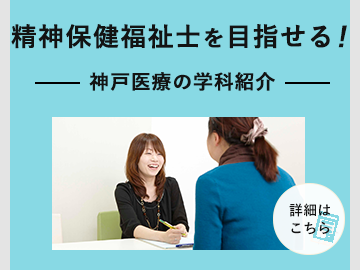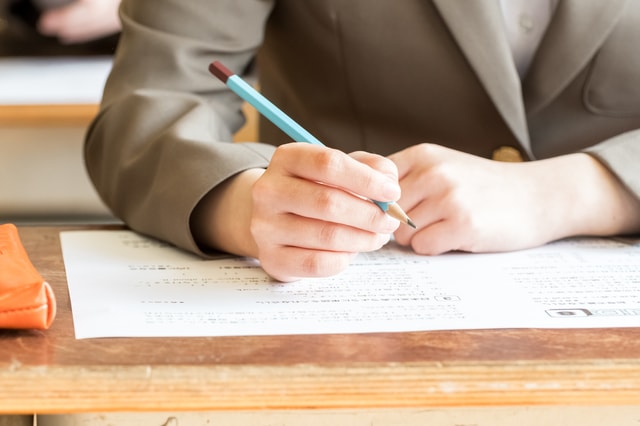
精神保健福祉士の試験を受験しようと考えている方は、事前に対策をして合格率をアップさせたいですよね。
そんな方のために、精神保健福祉士の合格率や受験方法、合格するための勉強方法など、受験者が知っておきたい情報をまとめてご紹介します。
目次
精神保健福祉士の合格率は?
合格率とは、試験を受けた人数のうちの何割が合格したかを表します。
まずは過去5年間の、精神保健福祉士の合格率を見てみましょう。
直近の精神保健福祉士試験の合格率は、65.6%(2022年)です。
これ以前の過去4年間を見ても、6割強といったところです。
なお同じく福祉系の国家資格である社会福祉士の合格率は、2022年で31.1%です。
これ以前の過去4年間でも、合格率は25%〜30%程度です。
このように精神保健福祉士は社会福祉士に比べると、比較的合格率が高いことが分かります。
精神保健福祉士の合格基準
試験を受ける際は、合格率の他にも合格基準を確認しましょう。
精神保健福祉士の合格基準は、次の通りです。
- 問題の総得点の60%程度を獲得する
- 全問正解をめざすのではなく、この合格基準の点数が取れるように効率よく勉強しましょう。
- 試験科目群全てにおいて得点を獲得する
- 科目群の数は、一般の場合17科目です。
社会福祉士の資格を持っている場合、一部免除のため5科目群となります。
精神保健福祉士の資格取得までの流れ

精神保健福祉士の資格を取得するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
合格率アップを狙う前に、精神保健福祉士の資格取得までの流れを把握しましょう。
精神保健福祉士の受験資格を満たす
精神保健福祉士の受験資格を得るには、様々なルートがある、ということは先ほどもお伝えしました。どのようなルートを辿ってとしても最終的に国家試験に合格することは必要なのですが、全部で11通りのルートがあります。
自分の状況と照らし合わせて最も適したルートを選ぶようにしましょう。
精神保健福祉士(PSW)になるルートについて詳しくはこちらへ
福祉系の大学で指定科目を修めた人には、すでに受験資格があります。
指定科目は納めていないものの基礎科目は納めているという人でも、短期の養成施設に6ヶ月ほど通うことで受験することができます。
また、例えば福祉系ではない一般の大学を卒業した社会人の方が新たに精神保健福祉士を目指す場合、一般の精神保健福祉士の養成施設に1年以上通うことで受験資格を得ることができます。
そのため、養成施設の入学者は10代や20代の若い世代ばかりではなく、30~40代の入学者も多くなっています。
ちなみに社会福祉士の資格を持っている方も、養成施設で6ヶ月学ぶことで精神保健福祉士試験を受けることができます。
社会福祉士を持っている受験者の場合には、社会福祉士と精神保健福祉士の共通科目が免除されるため、どちらも取得するという人もいます。
精神保健福祉士の試験に申し込む
精神保健福祉士の国家試験は、年に1回、1月の下旬から2月上旬ごろのいずれかの日程で行われます。出願は9月上旬から10月上旬ごろに期間が設けられています。
会場は全国7ヶ所で、北から北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県に設けられています。
試験科目は「人体の構造と機能及び疾病」「心理学理論を心理的支援」「社会理論と社会システム」「現代社会と福祉」「地域福祉の理論と方法」「社会保障」「低所得者に対する支援と生活保護制度」「福祉行財政と福祉計画」「保健医療サービス」「権利擁護と成年後見制度」「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」「精神疾患とその治療」「精神保健の課題と支援」「精神保健福祉相談援助の基盤(基礎・専門)」「精神保健福祉の理論と相談援助の展開」「精神保健福祉に関する制度とサービス」「精神障害者の生活支援システム」の17科目となっています。
2018年度の第21回精神保健福祉士国家試験の施行は、8月3日に公告されました。試験日は2019年2月2日(土)及び2月3日(日)、出願期間は2018年9月6日(木)~10月5日(金)の1ヶ月間となっています。
精神保健福祉士の試験に合格するには

精神保健福祉士の試験の合格率を上げるためにも、正しい対策を取りましょう。
試験内容を理解する
精神保健福祉士の出題形式は、5択のマークシート方式です。
試験科目は、次の17科目です。
- 人体の構造と機能及び疾病
- 心理学理論を心理的支援
- 社会理論と社会システム
- 現代社会と福祉
- 地域福祉の理論と方法
- 社会保障
- 低所得者に対する支援と生活保護制度
- 福祉行財政と福祉計画
- 保健医療サービス
- 権利擁護と成年後見制度
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
- 精神疾患とその治療
- 精神保健の課題と支援
- 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎・専門)
- 精神保健福祉の理論と相談援助の展開
- 精神保健福祉に関する制度とサービス
- 精神障害者の生活支援システム
引用URL:
精神保健福祉士国家試験 試験科目別出題基準
医学に関するものから行政制度に関する分野まで、幅広く出題されます。
合格基準は全ての科目で点数を得ることなので、全科目まんべんなく勉強するように意識しましょう。
過去の問題を解く
知識がある程度頭に入ったら、今度は過去問を解いてインプットしましょう。
インターネットでも過去問を解説とともに公開していることがありますが、できれば自分の苦手分野をマークして繰り返し練習できる、問題集を使うことをおすすめします。
試験対策のためには、正解していればOKというわけではなく、選択肢1つ1つのどこが合っていてどこが間違っているかを説明できるようにしてください。
まとめ
精神保健福祉士の合格率は60%程度であり、これは合格基準の数字とほぼ同じです。
出題範囲は幅広く、全ての分野で点を取る必要があります。
また受験資格は経歴によってさまざまなので、ご自身のケースに合わせて確認してみてください。
福祉系以外の一般大学を卒業している方は、一般養成施設等に1年以上通う必要があります。
一般養成施設をお探しの方は、神戸医療福祉専門学校をご検討ください。
精神保健福祉士科は夜間の学科のため、働きながらでも精神保健福祉士をめざせます。
アルバイト紹介制度を利用して、実務経験を積むのもおすすめです。
気になった方は、まずは無料の資料請求からお試しください。
精神保健福祉士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の精神保健福祉士科では、国家試験の合格率は、96%!(※2015~2023年度実績)
高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2020年度実績)
通学制ならではの講義・演習・実習を組み合わせたカリキュラムで、夜間1年間で国家試験合格と、就職活動をサポートします。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや精神保健福祉士科の詳細情報をご覧ください。また、精神保健福祉士科の学科の詳細を知りたい方は「精神保健福祉士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「利用者さんの役に立てるよう学び続けていきたい。」(2013年度卒業)
「患者さんの暮らし全般を支えることができる。」(2011年度卒業)
「自分自身の成長を実感できる仕事。」(2010年度卒業)
「国家資格の取得を通して仕事の幅を広げる。」(2009年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!