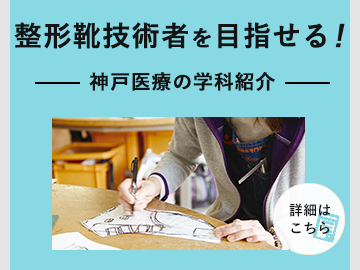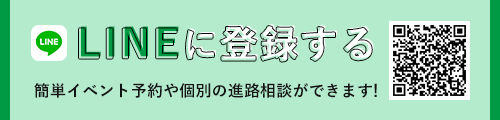自分で靴作りをしてみたい!と思ったとき、まずは道具をそろえる必要がありますよね。
靴作りに必要な道具の中には特殊なものも多くありますが、ネットショップでそろえることも可能です。
この記事では、靴作りに必要な道具を紹介します。
靴作りに必要な道具は工程によって異なる
 靴作りは、工程によって道具を使い分けます。
靴作りは、工程によって道具を使い分けます。
ここでは、靴作りの道具を工程ごとにご紹介しましょう。
木型修正
まず、靴の形の元となる木型作りからスタートします。
木型を、足の大きさにあわせて修正していきます。
木型修正に必要な道具は、次の2つです。
- ヤスリ
- 木型を削るのに必要です。
木型という名前ですが、最近は木材だけでなくプラスチックでできているものもあるので、素材に合ったヤスリを用意しましょう。 - パテ
- 周径が足りない時は、パテで足していきます。
アッパー作り
靴の底以外の部分をアッパーと言いますが、このアッパーを作るためには特殊な道具をいくつか使います。
- 型紙
- 靴の素材を切り出すための型紙を作ります。
- 革包丁
- 革素材の靴の場合、生地を型紙に沿って切り抜くには革包丁が必要です。
また切り抜きだけでなく、革をすくときにも革包丁を使います。
革をそのまま縫い合わせたり重ねたりすると、厚みが出てしまうので、革包丁を使って厚みが出ないように革を薄くすきます。
海外では、シューメーカーナイフなどが使われます。 - ガラス板
- 革包丁を使って革すきをするときは、ガラス板の上ですくと、刃が入りやすくなります。
- すき機
- 革包丁の代わりに、すき機を使って革を薄くすくこともできます。
すき機を使えば正確に、均一にすくことができます。またすき機を使っても、微調整を革包丁ですることも多いです。
- ミシン
- アッパーを縫い合わせるときは、一般的な家庭用のミシンでなく、ポストミシンや腕ミシンといった工業用のものが必要になります。
ソール付け
完成したアッパーを木型につり込み、ソール(靴底)を取り付けます。
このソールの取り付けにも、特殊な道具が使われます。
- ワニ
- アッパーを引っ張り、木型につり込むために使います。
少ない力でもアッパーを引き込むことができます。 - すくい針と糸
- ソールを手縫いする場合には、すくい針と糸が必要です。
このようにすくい針を使った縫い方を、すくい縫いと言います。 - 接着剤
- ソールのうち本底という地面に直接触れる部分を、縫わずに接着する方法もあります。
仕上げ作業
靴の見た目を美しくするためには、仕上げ作業も必要です。
- コテ
- 革靴の場合、コテの熱でツヤを出したり、繊維を引き締めたりする仕上げ作業があります。


靴作りの技術で人の役に立ちたいなら
 靴作りを仕事にしたいという方は、整形靴技術者として医療分野で靴作りの技術を活かしてみてはいかがでしょうか。
靴作りを仕事にしたいという方は、整形靴技術者として医療分野で靴作りの技術を活かしてみてはいかがでしょうか。
足のトラブルを抱える方に対し、医学的知識に基づいてフィッティングや靴選びのアドバイス、靴の製作や加工ができる「靴と足の専門家」、それが整形靴技術者です。
靴作りの技術で人の役に立ちたいなら、整形靴技術者はぴったりの仕事です。
まとめ
靴作りの道具や材料は、特殊なものが多いです。
インターネットなどでもそろえられますが、工房や靴教室、専門学校など、一通り道具がそろっているところで靴作りを経験するのがおすすめです。
神戸医療福祉専門学校では、オープンキャンパスで靴作りの一部を体験することもできます。
靴作りに興味がある方は、専門学校のオープンキャンパスや、靴教室の見学会などに参加されてみてはいかがでしょうか。
義肢装具士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の義肢装具士科では、国家試験の合格率は、2年連続で100%!(※2022~2023年度実績) 高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
義肢装具士養成校、日本で唯一の4年制専門学校で、最新技術&グローバルな学びで多彩な活躍を目指せます。
4年制独自のカリキュラムで、医学や工学の基礎知識から整形靴の本場であるヨーロッパでマイスターの国家資格を取得したヘルプスト先生より直接指導を受けられます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや義肢装具士科の詳細情報をご覧ください。
また、義肢装具士科の学科の詳細を知りたい方は「義肢装具士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「患者さんの願いを叶えられるスペシャリストをこれからもめざしていきます。」(2017年度卒業)
「患者さんに本当に喜んでいただけた時、やりがいを感じます。」(2008年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!