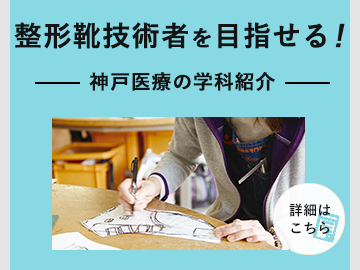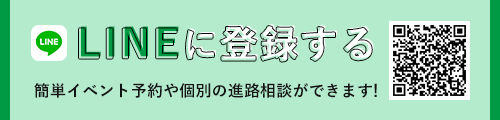「靴作りに興味がある」「自分にぴったりの靴が欲しい」「洋服から靴まで自分で衣装を作りたい」など、靴を作りたい理由は人それぞれです。
今回は靴の作り方についての主な方法と、靴作りの手順をご紹介します。
神戸医療福祉専門学校は、整形靴技術者として活躍するのに必要な知識や技術を学べる専門学校です。
整形靴技術者になりたい!目指している!という方は、オープンキャンパスの開催や、学校に関する資料請求ができますので、ぜひ一度チェックしてください!
目次
靴を作るための主な方法
靴の作り方は、手軽にできるものから本格的なものまでさまざまな方法があります。
ここでは代表的な方法をご紹介するので、自分に合った方法でオリジナルの靴を作ってみましょう。
デザインなどだけ決めてオーダーする
まずは、デザイン、サイズなどを決めてオーダーメイドで靴を作る方法です。
オーダーメイドの場合、自分の希望通りの靴を職人に作ってもらえます。
この方法は、フィットして歩きやすい靴を探している、オリジナルデザインの靴が欲しいといった方におすすめです。
靴の形の元となる木型から作るフルオーダーや、素材やデザインを選んで決められるセミオーダーなどがあります。
作成キットを使う
靴作りを楽しみたいけど、1から自分でやるのは大変そうだと思う方は、作成キットを使う作り方がおすすめです。
靴の作成キットを使うと、型やソール、糸などがセットになっていて、説明書を見ながら自宅で靴を作ることができます。
中には2〜3時間で靴が完成するキットもあり、手軽に靴作りを楽しめます。
本格的に作るなら工房や靴教室に行く
本格的に靴を作りたい方は、工房や靴教室に行ってプロから靴の作り方を教えてもらいましょう。
工房のワークショップだと、週1回、1ヶ月ほどかけて靴を作るところが多いです。
また靴作りの道具や材料も一通りそろっているので、プロと同じような靴作りを体験することができます。


靴の基本的な作り方
 靴を作るにはたくさんの工程があります。また作り方も様々です。
靴を作るにはたくさんの工程があります。また作り方も様々です。
ここでは作り方の一例を紹介します。
足の採寸
まずは、足の採寸です。
既製品の靴を買うとき、つま先からかかとまでの長さで靴を選ぶと思いますが、靴を作るときは足の幅や高さなども測ります。
長時間歩いても疲れない、靴ずれにならないなど、足への負担を減らすためにはその人の足にぴったりの靴を作る必要があるので、採寸はとても重要です。
採寸・採型
靴を作るときは、まず足の状態を正しく読み取ります。
足の長さや幅、甲の高さ、足底へどのように圧がかかるのなど、足に関してのあらゆる情報が必要になります。
その後は、木型をつくる「足型」をとるために、足に石膏包帯を巻きます。
この足型をとる作業は、靴をつくる作業で最も重要です。
特に足にトラブルを抱えている方用の靴の場合、小さな誤差でも生活に支障をきたしてしまうため、慎重に行いましょう。
※医師の指示でつくられる「整形靴」は「装具」の一種となります。そのため、その採型や適合を行うのは、医療系国家資格である「義肢装具士」の免許がある方に限られます。
木型製作
足型をもとに、靴の原型になる「木型」を作成します。
以下のような流れになります。
- 採型でとった足型に樹脂を流し込む
- 樹脂が固まるのを待つ
- グラインダーなどの機械が工具を使って削ったり、パテを盛ったりして形を整える
製甲
続いては、木型をもとに靴のパターン(型紙)をつくっていきます。
靴のデザインや見た目に大きく関わる作業になります。
デザインを考えつつ革を裁断し、ミシンで縫い合わせていく作業です。
ステッチ(糸のライン)から革の特徴、伸縮の向きなど様々な知識を使って、計算して靴をつくりあげなくてはなりません。
計算した通りの靴にするために繊細な作業も求められます。
つり込み
甲革が完成したら、それを木型にかぶせて、つま先やかかとなどの形状をつくります。
つり込みは専用の小道具を多く利用します。
このような小道具をうまく使いこなし、一枚の革を靴らしい形に変えていくのは、靴職人だけができる作業になります。
底付け
革が靴らしい形に変わったら、革の底面に「本底」と呼ばれるパーツを貼り付け、その上からヒールを貼り付けて靴の底をつくっていきます。
本底には、革やゴムなどの素材があるため、それぞれの特性に合わせて加工していきます。
仕上げ
靴の底付けが完了したら、最後に仕上げの作業をしていきます。
靴の見栄えを左右する作業なため、表面をしっかりみがき、木型を外してクリーニングをし、紐を綺麗に結びなおしたら完成です。
誰が見ても納得してもらえるように、丁寧かつ慎重に作業をしていきます。
ぴったりの靴を届けるのが整形靴技術者
 靴作りのどの工程でも、少しのズレが靴の完成度を大きく変えます。
靴作りのどの工程でも、少しのズレが靴の完成度を大きく変えます。
ぴったりで美しい靴を作るためには、高い技術や知識が必要になります。
また靴作りに関する仕事に、整形靴技術者というものがあります。
整形靴とは、足にトラブルがある方のための医療用の靴です。
高い精度が必要になる分、求めている方の気持ちに寄り添った靴を作ることができるので、やりがいも大きなものになります。
困っている人を靴作りで助けたい、より高い精度が必要な靴を作りたいという方は、整形靴技術者をめざしてみてはいかがでしょうか。
義肢装具士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の義肢装具士科では、国家試験の合格率は、2年連続で100%!(※2022~2023年度実績) 高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
義肢装具士養成校、日本で唯一の4年制専門学校で、最新技術&グローバルな学びで多彩な活躍を目指せます。
4年制独自のカリキュラムで、医学や工学の基礎知識から整形靴の本場であるヨーロッパでマイスターの国家資格を取得したヘルプスト先生より直接指導を受けられます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや義肢装具士科の詳細情報をご覧ください。
また、義肢装具士科の学科の詳細を知りたい方は「義肢装具士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「患者さんの願いを叶えられるスペシャリストをこれからもめざしていきます。」(2017年度卒業)
「患者さんに本当に喜んでいただけた時、やりがいを感じます。」(2008年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!
監修・運営者情報
| 監修・運営者 | <神戸医療福祉専門学校 三田校> 理学・作業・言語・救急・義肢 |
|---|---|
| 住所 | 〒669-1313 兵庫県三田市福島501-85 |
| お問い合わせ | 079-563-1222 |
| ホームページ | https://www.kmw.ac.jp/ |