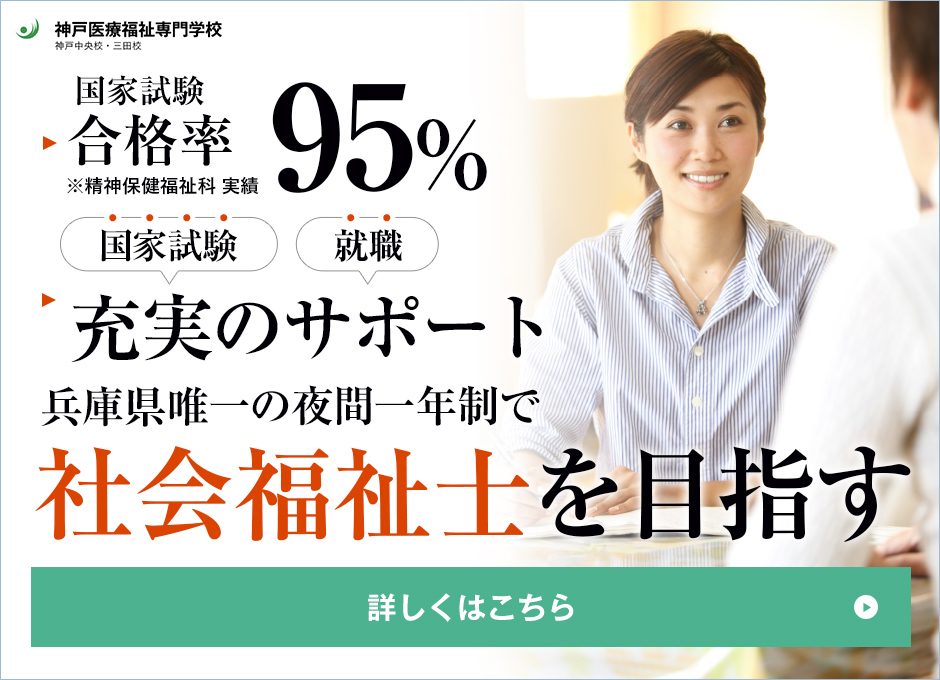世の中には、虐待(DV)や経済的な事情など家庭環境が困難であったり、心身に障害があったりと、さまざまな問題を抱えている子どもたちがたくさんいます。
そんな子どもたちのために社会的に必要な援助(公的サービス)を提供するのが児童福祉の仕事です。
そこでこの記事では、そんな児童福祉に関わる仕事の中でも、児童相談所という公的機関で働く児童福祉司という職業について解説。
さらに、児童相談員や児童指導員など似ている職業との違いや、そのほか児童福祉に関わることができる社会福祉系の職種などについても紹介していきます。
目次
児童福祉司とは?児童福祉司の仕事内容とは?
児童福祉司とは、社会福祉法の1つである児童福祉法に基づいて、各自治体(都道府県)に設置されている児童相談所に勤務する公務員です。
心身に障害を抱えている子どもや、DVや非行、虐待など家庭内の環境に問題を抱えていたりする子どもやその保護者の相談に乗り、問題解決に向けてサポートします。
子ども、保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じる
児童相談所では、子どもや保護者の方々からの様々な相談に応じています。
虐待や養育に関する相談をはじめ、発達障害に関する相談も受け付けています。
相談内容に応じて、適切な支援を提供できるよう、専門の職員が対応します。
相談に対して必要な調査、社会診断を行う
相談内容を把握するため、専門職である児童福祉司は、子どもの家庭環境や性格、行動などについて調査を行います。
相談内容の確認として、家庭訪問を行い面接を実施することがあります。
調査によって得られた内容をもとに、社会診断を行い、支援の方向性を検討します。
問題を抱える子ども、保護者、関係者等に必要な支援や指導を行う
問題を抱える子どもや保護者、関係者に対して、児童福祉司は必要な支援や指導を行います。
問題の原因を明らかにするために、カウンセリングや調査を実施します。
生活環境に問題がある場合は、家庭内での生活習慣や教育方法についてアドバイスを行います。
家族関係や経済的な困難が原因の場合は、福祉サービスや支援機関を紹介するため、関係機関と連携を取ることが児童福祉司の仕事です。
子どもの命や健康に危険が及ぶ可能性がある場合は、一時保護の判断や、警察署、福祉施設などの専門機関との連携も重要です。
子どもたちが安心して成長できるよう、関係機関と連携し、仕事や役割分担を行いながら、必要な支援や指導、相談援助を行います。
問題を抱える子ども、保護者等の関係調整(家族療法など)を行う
問題を抱える子どもや保護者に対し、関係調整として家族療法が行われることがあります。
家族療法は、家族全体を対象とする治療法です。
全国53ヶ所(2024年現在)にある児童心理治療施設では、親子で通い、医師や臨床心理士などの専門家によるカウンセリングや心理療法を通じて家族関係の改善を目指します。
家族療法では、家族間のコミュニケーション改善や、対立や誤解の解消を支援します。
対象は、不登校やひきこもり、DV、虐待などにより対人関係に不安を感じている子どもとその家族です。
家族全体で問題解決に取り組む力を身につけることを目的としています。
家族関係の改善とともに、子どもの問題行動や心理的な困難が和らぐことが期待されます。
児童福祉司の働き方について
児童福祉司は、地方公務員として児童相談所に勤務し、子どもや家庭の問題解決をサポートします。
勤務時間は原則として平日ですが、緊急時には夜間や休日出勤もあります。
児童虐待の相談件数が増加傾向にあるため、児童福祉司の負担は大きいと言えるでしょう。
しかし、子どもたちの笑顔を守るやりがいのある仕事です。
ワークライフバランスを保ちながら、専門性を活かして活躍している方もいます。
児童福祉司になるには?
児童福祉士になるためには、一定の要件を満たして、児童福祉の任用資格を取得。
その後、地方公務員試験の「福祉職」もしくは「社会福祉区分」を受けて、筆記試験・面接試験に合格する必要があります。
多くの場合、大学や専門学校で児童福祉に関連する学部や科を修了し、必要な知識と技術を習得することからスタートします。
児童福祉司の任用資格を取得する
児童福祉司としての任用資格を得るには、特定の資格や研修プログラムの修了が求められます。
これには、児童福祉法に基づく児童福祉司任用資格研修などが含まれ、児童相談所における専門的な業務を遂行するための深い理解と技術が必要とされます。
資格取得後も、定期的な研修や学習を通じて最新の知識と技術を身に付け、専門性を高めていくことが重要です。
地方公務員試験に合格し、児童相談所へ配属される
児童福祉司として公的な機関、特に児童相談所で働くには、地方公務員試験に合格する必要があります。
この試験は、児童福祉に関する専門知識だけでなく、一般教養や法律知識など幅広い分野をカバーしており、高い競争率を勝ち抜く必要があります。
合格後、児童相談所などでの実務研修を経て、児童福祉司としてのキャリアをスタートさせます。
児童福祉司の任用資格取得のための2つのルート
児童福祉司の任用資格を取得するには、主に2つのルートがあります。
1つ目は、大学で心理学、教育学、社会学などを専攻し、卒業後に指定施設で1年以上の相談援助業務を経験するルートです。
このルートでは、大学で専門知識を学び、現場での経験を通じて実践的なスキルを習得できます。
もう1つのルートは、都道府県知事が指定する児童福祉司養成校を卒業することです。
養成校では、児童福祉に関する専門的な知識や技術を体系的に学ぶことができ、最短で任用資格取得を目指せます。
児童福祉司とは、子どもの福祉に関する相談に応じ、必要な調査や支援を行う専門職です。
どちらのルートを選ぶかは、自身の状況やキャリアプランに合わせて検討することが重要です。
研修制度も充実しており、資格取得後も継続的なスキルアップが可能です。
①大学で心理学、教育学、社会学を専攻し、指定施設で1年以上相談援助業務に従事するルート
児童福祉司の任用資格を得るルートの一つに、大学で心理学、教育学、社会学のいずれかを専攻する方法があります。
大学卒業後、厚生労働省が指定する児童相談所や児童養護施設などの指定施設において、1年以上の相談援助業務に従事することが必要です。
この経験を通じて、児童福祉に関する相談や支援に必要な知識と技術を習得します。
1年以上の実務経験を積むことで、児童福祉司の資格が任用されるため、各自治体の児童相談所などで児童福祉司として業務に携わることが可能です。
②都道府県知事指定の養成校を卒業するルート
都道府県知事が指定する養成校を卒業するルートも存在します。
このルートでは、児童福祉司として必要な法律や制度、子どもの心理、相談援助技術など、専門的な知識を養成校で集中的に学びます。
豊富な実習を通して経験を積むことも可能です。
養成校での学びを通して、児童福祉司に必要な知識と技術を習得し、修了することで児童福祉司の任用資格を得ることが可能です。
児童福祉の専門家として、相談援助のエキスパートを目指すことが出来ます。
児童福祉司と似ている職業との違い
児童福祉司という仕事に興味がある方は、他に児童相談員や児童指導員という言葉も聞いたことがあるでしょう。
そこで次は、児童福祉司と混同されがちなこの2つの職業について、その仕事内容や活躍している場所などの違いを解説していきます。
児童相談員
児童福祉司と児童相談員は呼び方が異なるだけで、ほとんど同じ意味と考えて問題ありません。
児童福祉司は、児童相談所に配置することが義務付けられた職員の名称です。
このため、児童相談所に所属し、地方公務員として働く場合のみ児童福祉司と呼ばれます。
それに対して、たとえ児童福祉司の任用資格を持っていたとしても、民間の児童福祉施設などで働く場合は児童福祉司ではなく、児童相談員と呼ばれることが多いようです。
児童指導員
児童指導員とは主に、18歳以下の子どもの一時保護業務を行う職業です。
家庭の事情で支援が必要な子どもたちへの学習指導や、障害のある子どもたちの生活をサポートなど、将来的な自立や社会参加のために必要な訓練を実施します。
児童相談所に勤務する児童福祉士司に対して、児童指導員は主に、児童養護施設や知的障がい児施設などの児童福祉施設で活躍しています。
児童心理司
児童心理司は、児童相談所に配置され、子どもの心の状態を専門的に診断し、心理的なサポートを行う専門家です。
児童相談所では、児童福祉司が子どもや保護者との面談や家庭訪問を通して問題の原因を探り、環境面からの指導や援助を行います。
一方、児童心理司は、心理検査や面談を通じて子どもの心理状態を把握し、心理療法などの心理的な支援につなげます。
また、児童養護施設などの福祉施設では、児童指導員が子どもたちの生活指導を行います。
児童心理司は、問題を抱える子どもたちの成長を心理面から支える重要な役割を担っています。
他の福祉系の国家資格との違い
ここまで、児童福祉司をはじめ、児童相談員や児童指導員など、児童福祉に関わる職業を紹介してきました。
しかし、「児童○○」という名称でなくとも、児童福祉に携わることができる職業はたくさんあります。
そこでここからはその他にも、子どもの日常生活を支援したり、療育(発達支援)などの観点から、子どもが自立した生活を送れるようサポートしたりする福祉系の職業について紹介していきます。
社会福祉士
社会福祉士とは、いわゆるソーシャルワーカーと呼ばれる社会福祉の専門職です。
身体的・精神的・経済的な事情などにより、さまざまなハンディキャップを抱えている人の相談に乗り、日常生活がスムーズに送れるよう支援します。
あらゆる福祉サービスを取り扱うため、高齢者支援や障がい者支援だけでなく、生活困窮者や児童・母子など、さまざまな人を支援できるのが特徴です。
実際、社会福祉士の資格を活かして、母子支援関連や障がい児施設などの福祉施設で職員として働き、日常生活にさまざまな困難を抱えている子とその親を援助している人もたくさんいます。
精神保健福祉士
精神保健福祉士とは、精神に障害を抱えた人たちの自立した生活や社会復帰を支援する専門職です。
主な活躍の場としては、精神科病院などの医療機関や、精神障がい者福祉施設などがあげられますが、近年では児童福祉の分野でもその必要性が謳われはじめ、児童福祉施設や教育機関などで活躍する精神保健福祉士も増えています。
実際に、精神保健福祉士の資格取得は、児童福祉士司の任用資格を取得する要件を満たす方法の一つともなっていることからも、その関連性の高さがうかがえますね。
児童分野で活躍する精神保健福祉士は、主に障がい児施設で精神障害のある児童の発達支援を行なったり、児童養護施設や母子生活支援施設などで、児童相談員という立場から親と子どものサポートを行なったりします。
介護福祉士
介護福祉士とは、介護にまつわる一定の知識や技術を習得していることを証明する唯一の国家資格です。
介護というと、高齢者の方の食事や入浴など身の回りの介助を行うイメージが強いかもしれませんが、中には児童福祉施設や障がい児入所施設などで、子どもたちの日常生活を支援している介護福祉士もいます。
児童福祉司に向いている人は?
児童福祉司には、高いコミュニケーション能力が求められます。
子どもや保護者の話を丁寧に聞き、共感する姿勢が重要です。
問題解決能力も不可欠であり、子どもの状況を的確に把握し、適切な支援策を検討する必要があります。
また、責任感も重要な要素です。
子どもの命や未来に関わる仕事のため、強い責任感を持って職務を遂行しなければなりません。
子どもや保護者と信頼関係を築ける人間性も大切です。
相手の気持ちを理解し、寄り添うことで、安心して相談できる関係性を築くことが求められます。
1.コミュニケーション能力がある
児童福祉司には、子どもや保護者の状況を的確に把握し、円滑な支援を進めるためのコミュニケーション能力が求められます。
相手の話を丁寧に聞き、本音を引き出すことはもちろん、問題の内容やこれから行う支援について、わかりやすく説明する能力が必要です。
複雑な状況を整理し、相手に理解してもらえるように伝えることで、問題解決の糸口が見つかることもあります。
また、関係機関との連携も不可欠です。学校や医療機関などと協力し、情報を共有することで、一貫した支援につなげられます。
2.共感力がある
共感力とは、相手の感情や状況を理解し、寄り添う能力のことです。
児童福祉司には、子どもや保護者の気持ちを理解し、最適な支援を提供することが求められます。
問題を抱えている子どもや保護者は、否定的な言葉や態度に敏感になっている場合があります。
そのため、相手の気持ちに寄り添い、共感することが大切です。
「自分の気持ちを理解してくれている」と感じてもらうことで、より深い悩みや不安を共有してもらいやすくなります。
3.問題解決能力がある
児童福祉司には、子どもや家庭が抱える問題の本質を見抜く問題解決能力が求められます。
状況を的確に把握し、緊急性や優先順位を判断する必要があるためです。
家庭訪問や関係者からの聞き取りを通じて情報を集め、迅速かつ適切な対応策を決定する能力が重要になります。
子どもや家庭を取り巻く問題を解決に導くためには、多角的な視点と冷静な判断力が必要不可欠です。
4.責任感がある
児童福祉司には、子どもの安全を最優先に考え、迅速に適切な措置を決定する責任感が求められます。
時に、子どもの成長のために、保護者から離す決断をしなければならない場合も、倫理的な判断を下す必要があります。
常に子どもの未来を第一に考え、感情に流されず、冷静に判断することが重要です。
困難な状況に直面しても、強い責任感を持って職務を遂行することが求められるからです。
5.子どもや保護者と信頼関係を築ける人間性
児童福祉司の仕事は、子どもや保護者との信頼関係が不可欠です。
そのためには、誠実で温かい人柄が求められます。
子どもや保護者が安心して何でも相談できるよう、親身になって話を聞き、寄り添う姿勢が大切です。
仕事をする上で、相手の立場を理解し、共感する能力は非常に重要になります。
信頼関係を築くことで、より深く問題を把握し、適切な支援につなげることが可能です。
児童福祉司の給与は?
児童福祉司の給与は、勤務する自治体や経験年数によって異なります。
地方公務員であるため、各自治体の給与規定に準じて支給されます。
一般的に、経験年数や役職が上がるにつれて昇給する仕組みとなっています。
具体的な金額は、各自治体のウェブサイトや人事委員会が公表している給与情報を参照することで確認できます。
児童福祉司は、子どもの福祉を支える重要な仕事であり、その貢献に見合った待遇が期待されます。
児童福祉司の将来性は?
児童福祉司は、子どもを取り巻く問題を解決するために、今後ますます必要とされる存在です。
社会的なニーズの高まりに伴い、児童福祉司の専門性への期待も高まっています。
児童虐待や貧困、発達障害など、子どもに関する課題は複雑化、多様化しており、専門的な知識やスキルを持った人材が求められています。
児童福祉司の資格取得を支援する制度も充実してきており、キャリアアップを目指しやすい環境も整いつつあります。
社会貢献を実感できる仕事であり、やりがいを感じながら働くことができるでしょう。
まとめ~児童福祉司とは?児童福祉司になるには?~
児童福祉とは、孤児や障がい児、経済的に厳しいひとり親家庭など、特別な支援を必要とする児童が「しあわせに」そして「ゆたかに」暮らせるよう社会的な援助を行うことです。
そしてそんな児童福祉に関わる仕事には、児童福祉司や児童指導員をはじめ、社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士などさまざまな職種があります。
一口に児童福祉といっても、子どもとの関わり方や支援の方法などは職種によってさまざま。
このため、まずは業務内容や活躍している場所など、一つ一つの職業の違いについてよく知ることが大切です。
「困っている子どもたちの力になりたい」という想いを、最もあなたに合った形で叶えるためにも、ゆっくりと時間かけて自分のなりたい職業を探してみてくださいね。
福祉の専門職を目指すなら、神戸医療福祉専門学校中央校へ!
児童福祉司をはじめ、福祉の現場で活躍するためには、専門的な知識と実践力が求められます。
神戸医療福祉専門学校中央校には、福祉職を目指す学科として介護福祉士科・精神保健福祉士科・社会福祉士科の3学科があり、それぞれの分野で即戦力となる人材を育成しています。
介護福祉士科(2年制)
国家試験合格率は全国平均を上回る高水準!現場で求められる「介護技術」だけでなく、「コミュニケーション力」や「生活支援力」も身につけられるカリキュラムが特長です。
実習先との連携も強く、卒業後の就職率も非常に高い実績があります。
精神保健福祉士科(夜間1年制)
大学卒業者を対象とした短期集中型の学科です。
精神疾患を抱える方への支援や、地域での生活支援に必要な知識・技術を、実践的に学ぶことができます。
現場経験豊富な講師陣による指導で、国家試験対策も万全です。
社会福祉士科(夜間1年制)
社会福祉士国家試験の合格を目指すための専門カリキュラムを提供。
相談援助のプロフェッショナルとして、児童福祉・高齢者福祉・障害者福祉など、幅広い分野で活躍できる力を養います。
毎年多くの卒業生が福祉施設や行政機関に就職し、地域社会で活躍しています。
神戸医療福祉専門学校中央校では、「人を支える仕事がしたい」「福祉の専門職になりたい」という想いを、確かな力に変える学びがあります。
児童福祉司をはじめ、福祉の道を志す高校生・社会人の皆さんにとって、理想的な環境がここにあります。
情報収集のための一つの手段として、ぜひ神戸医療福祉専門学校への資料請求やオープンキャンパスへのご参加もお待ちしております。
>>資料請求はこちら
>>精神保健福祉士科のオープンキャンパスはこちら
>>介護福祉士科のオープンキャンパスはこちら
社会福祉士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の社会福祉士科では、夜間1年でスクールソーシャルワーカーはもちろん、その他医療や福祉の現場でソーシャルワーカーとして幅広く活躍できる社会福祉士の資格取得が目指せます。
夜間制で授業時間は基本的に18時10分〜のため、日中は仕事で忙しい社会人の方でも無理なく通学できます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや社会福祉士科の詳細情報をご覧ください。
また、社会福祉士科の学科の詳細を知りたい方は「社会福祉士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。