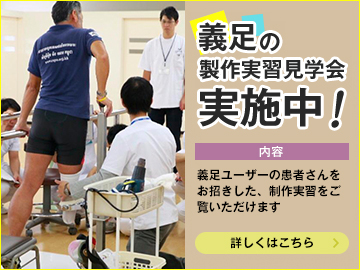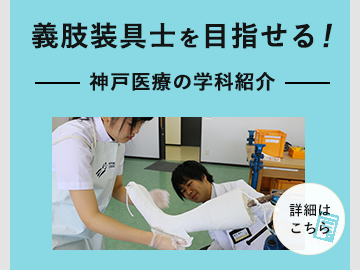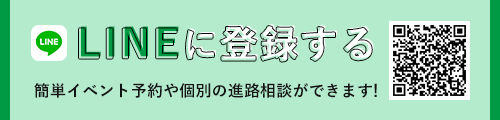今日の医療業界では、より良い医療を提供していくために、さまざまな形で遠隔操作ロボットが取り入れられています。
近年、医療業界の中でも義肢装具の世界でも遠隔操作ロボットが注目されています。
そこで今回は遠隔操作ロボットと義肢装具士をテーマに、さまざまな視点でご紹介していきます。
目次
医療業界の遠隔操作ロボットとは
はじめに、医療業界では遠隔操作ロボットがどのように取り入れられるようになったのかをたどっていきましょう。
医療業界の遠隔操作ロボットが、日本に初めて導入されたのは2000年の慶應義塾大学病院と言われています。
その後2009年に厚生労働省内にある、薬事・食品衛生審議会が医療業界で使用できる遠隔操作ロボット製造販売が認められ、今日に至っています。
そして、医療業界の遠隔操作ロボットはさらに種類が増えてきており、現在カテゴリーとして下記のように分けることができます。
- 医師をサポートするタイプの遠隔操作ロボット
- 対象者(患者)をサポートするタイプの遠隔操作ロボット
以上のように、医師をサポートするタイプと対象者(患者)をサポートするタイプと2種類の医療業界の遠隔操作ロボットがあります。
では、タイプごとにどのような遠隔操作ロボットが活躍しているのか、見ていきましょう。
医師をサポートするタイプ
まずは医師をサポートするタイプの遠隔操作ロボットから見ていきましょう。
医師をサポートするタイプの遠隔操作ロボットで、もっとも代表的なものは手術用のロボットです。
手術用ロボットは、手術をすることによって起きてしまう出血や痛み、発熱などをできるだけ少なくしながら手術をすることができる遠隔操作ロボットです。
中でも、もっとも使用されている手術用の遠隔操作ロボットは、da Vinci(ダ・ヴィンチ)です。
da Vinci(ダ・ヴィンチ)は、実際に患者の手術をするペイシェントカート、医師が操作するサージョンコンソール、手術の様子を見ることができるビジョンカートの3つで構成されています。
ペイシェントカートにある3つのアームを交換すれば、さまざまな手術を行うことができることから、今日多くの医療現場で使用されています。
対象者(患者)をサポートするタイプ
 2つ目は対象者(患者)をサポートするタイプの遠隔操作ロボットです。
2つ目は対象者(患者)をサポートするタイプの遠隔操作ロボットです。
身体機能の低下、もしくは障がいを抱えている人にさまざまなサポートを行っていくもので、今日もっとも代表的なものが手に装着するタイプの遠隔操作ロボットです。
手に装着するタイプの遠隔操作ロボットは、さまざまな要因で動かすことが困難になった手をサポートするもので、医療業界をはじめ、さまざまな分野でも多く見られるようになりつつあります。
そして、対象者(患者)をサポートするタイプの中には、義肢装具の分野に「節電電動義手」を取り入れた遠隔操作ロボットがあります。
節電電動義手は、欠損した上肢の断端にソケットで固定し、動かそうとするときに皮膚票目に微弱な電気信号を送り、動きをコントロールするものです。
モーターで動かすタイプよりも柔軟な対応ができることから、節電電動義手は義肢装具士の間でも注目されていました。
そして節電電動義手の動きをよりコントロールしやすくするために、コントロールシステムを設けることで節電電動義手を遠隔操作できるように開発も進められていることから、より利便性を高められるタイプと言えるでしょう。
このように、医療業界の遠隔操作ロボットには医師をサポートするタイプ、対象者(患者)をサポートするタイプの2種類があります。
以上を見ていると、今後より可能性を広げられるタイプは、義肢装具の分野で生かすことが期待されている対象者(患者)をサポートするタイプであると言えます。
しかし、義肢装具の分野で可能性が広げられると見込めていても、より広げるためには課題が多く残されています。
そこで、次は義肢装具士と遠隔操作ロボットの今後の課題について見ていきたいと思います。
義肢装具士と遠隔操作ロボットの今後の課題
義肢装具士と遠隔操作ロボットの今後の課題は大きく2つ挙げられます。
重量がある
まず1つ目は重量があることです。
まず、対象者の人々は該当部分が欠損してしまっていることにより、筋肉が落ちていることが多いことから、義肢装具士は対象者の人の体に合わせ、動かしやすく、軽量かつ使用しやすいように製作していきます。
しかし、そこへ遠隔操作ロボットの部品を加えてしまうと、どうしても重量が出てしまいます。
そのため、筋肉が落ちてしまっていることが多い対象者の人々が、義肢装具を使用することができかねない、といったことが起きてしまう可能性が出てきてしまいます。
したがって、義肢装具士が遠隔操作ロボットを取り入れていけるようになるためには、まず遠隔操作ロボットの軽量化をできるようにすることがもっとも解決するべき課題と言えます。
予算がかかる
 2つ目は予算がかかってしまうことです。
2つ目は予算がかかってしまうことです。
義肢装具は購入するだけではなく、装着をしていくうちに劣化が起きたら修理を依頼するなど、手に入れるだけではなく、持ち続けるための予算も必要となります。
そこへさらに遠隔操作できるように、遠隔操作ロボットを取り入れていくとなると、やはり予算がかかってしまいます。
そのため、民間企業が少しでも予算を軽減できるように遠隔ロボットを製作できるようになるまでは、時間を要してしまうため、より予算がかからないように導入できるようにすることも、課題と言えるでしょう。
まとめ
今回は医療業界、そして義肢装具士世界と遠隔操作ロボットについてさまざまな視点からお送りしました。
医療業界で使用されている遠隔操作ロボットにはどのようなものがあるのか、義肢装具士が遠隔操作ロボットを取り入れていくにはどのような課題があるのかが見えてきたと思います。
今後、さまざまな技術が進化を遂げ、遠隔操作ロボットを取り入れた義肢装具がどのようなものになっているのか、チェックしてみてはいかがでしょうか。
義肢装具士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の義肢装具士科では、国家試験の合格率は、2年連続で100%!(※2022~2023年度実績) 高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
義肢装具士養成校、日本で唯一の4年制専門学校で、最新技術&グローバルな学びで多彩な活躍を目指せます。
4年制独自のカリキュラムで、医学や工学の基礎知識から整形靴の本場であるヨーロッパでマイスターの国家資格を取得したヘルプスト先生より直接指導を受けられます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや義肢装具士科の詳細情報をご覧ください。
また、義肢装具士科の学科の詳細を知りたい方は「義肢装具士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「患者さんの願いを叶えられるスペシャリストをこれからもめざしていきます。」(2017年度卒業)
「患者さんに本当に喜んでいただけた時、やりがいを感じます。」(2008年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!