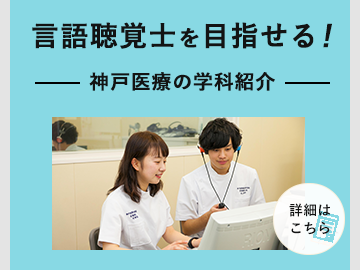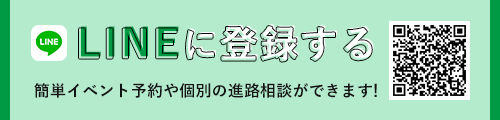言語聴覚士は、理学療法士や作業療法士と並ぶ、代表的なリハビリテーションの専門職の1つです。
これら3職種は、病気や怪我で失われた機能を取り戻す、遅れている発達を促進するなどの点で共通していますが、言語聴覚士は残りの2つの職種に比べると人数が少ないという特徴があります。
このため言語聴覚士はリハビリ職種のなかでも将来性がない?と不安になっている方もいるのではないでしょうか。
いくら人の役に立つ仕事と言えど、将来性があまり無いのであれば、その道に足を踏み入れて良いのか迷ってしまいますよね。
そこで今回、言語聴覚士の現在の状況と需要を踏まえた上で、将来性について詳しく言及したいと思います。
神戸医療福祉専門学校は、言語聴覚療法として活躍するのに必要な知識や技術を学べる専門学校です。
言語聴覚療法になりたい!目指している!という方は、オープンキャンパスの開催や、学校に関する資料請求ができますので、ぜひ一度チェックしてください!
目次
言語聴覚士は少ないの?有資格者数の現状
言語聴覚士((Speech-Language-Hearing Therapist:ST))は1997年に誕生した国家資格です。
日本言語聴覚士協会によると、2023年時点の言語聴覚士の有資格者数は4万1,657人。※1
一方、同じリハビリテーションの専門職である理学療法士(Physical Therapist:PT)の有資格者数は21万3,735人、作業療法士(Occupational Therapist:OT)は11万3,649人となっており、それぞれと比べて言語聴覚士の人数はかなり少ないことがわかります。※2 3
ちなみに、言語聴覚士の有資格者数の内訳としては男性が5,024人、女性が1万6,529人となっています。男女比は8:2です、女性の方が高い割合を占めています。
※1 会員動向 | 日本言語聴覚士協会
※2 統計情報|協会の取り組み|日本理学療法士協会
※3 質問2 組織率について|日本作業療法士協会
言語聴覚士が少ない理由は?他のリハビリ系職種と比較
同じリハビリテーションの専門職にも関わらず、言語聴覚士(ST)の有資格者数が理学療法士(PT)や作業療法士(OT)と比べて少ないのはなぜなのでしょうか?主な理由は以下のとおりです。
- 歴史が浅く、資格の認知度が低い
- 養成施設の数が少ない
- 対象となる患者が少ない
歴史が浅く、資格の認知度が低い
言語聴覚士は、1997年に施行された言語聴覚士法の成立によって誕生した国家資格です。
それに対して理学療法士と作業療法士は、1965年に施行された理学療法士および作業療法士法の成立によって誕生した国家資格となっています。
このように言語聴覚士は理学療法士・作業療法士と比べて歴史が浅いため、認知度が低い傾向にあります。
国家試験の受験者数・合格者数・合格率
言語聴覚士(ST)・理学療法士(PT)・作業療法士(OT)それぞれの直近5年間の国家試験の受験者数と合格者数、合格率の推移は以下のとおりです。
<言語聴覚士(ST)>
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 直近5年間平均 | |
| 受験者数 | 2,515人 | 2,593人 | 2,546人 | 1,766人 | 1,630人 | 2,210人 |
| 合格者数 | 1,696人 | 1,945人 | 1,766人 | 1,626人 | 1,630人 | 1,733人 |
| 合格率 | 67.4% | 75.0% | 69.4% | 65.4% | 68.9% | 69% |
データ引用:会員動向 | 日本言語聴覚士協会
<理学療法士(PT)>
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 直近5年間平均 | |
| 受験者数 | 12,948人 | 12,685人 | 11,946人 | 12,283人 | 12,605人 | 12,493人 |
| 合格者数 | 11,312人 | 10,096人 | 9,434人 | 10,608人 | 10,809人 | 10,452人 |
| 合格率 | 87.4% | 79.6% | 79.0% | 86.0% | 86.0% | 83.6% |
データ引用:統計情報|協会の取り組み|日本理学療法士協会
<作業療法士(OT)>
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 直近5年間平均 | |
| 受験者数 | 5,719人 | 4,861人 | 5,549人 | 6,532人 | 6,358人 | 5,804人 |
| 合格者数 | 4,793人 | 4,311人 | 4,510人 | 5,548人 | 4,531人 | 4,739人 |
| 合格率 | 83.8% | 88.7% | 81.3% | 87.3% | 71.3% | 82.5% |
データ引用:国家試験合格発表|厚生労働省
上記のデータに基づくと、言語聴覚士は年間1,700人前後増えている計算になります。理学療法士(PT)が年間1,0500人前後、作業療法士(OT)が年間4,700人前後増えていることを考えると、やはりその数は少ないといえます。
主な要因としては、年間の受験者数の少なさと合格率の低さが考えられます。
年間の受験者数の平均は、理学療法士が12,500人前後、作業療法士が5,800人前後なのに対し、言語聴覚士は2,200人前後です。また、合格率も理学療法士が約83.6%、作業療法士が約82.5.%とともに80%を超えているのに対し、言語聴覚士は69%とやや低めとなっています。
ただし、合格率が低いのは試験そのものの難易度が高いというよりも、理学療法士や作業療法士と比べてまだ資格の歴史が浅いため、過去問などでの試験対策が難しいということが主な理由として考えられます。
実際に、受験者数の半分以上は合格しているため、きちんと試験対策さえすれば十分に突破できる難易度だといえるでしょう。
養成施設の数が少ない
言語聴覚士の国家試験の受験者数が少ないのには 養成施設の数や定員数も関係しています。
2020年時点のデータでは、理学療法士の養成施設は全国に265校、定員数の合計は14,539人です。
作業療法士の養成施設は200校で、定員数は7,930人で、それに対して言語聴覚士の養成施設は74校、定員数は3,025人であり、そもそも養成施設に通える人数が少ないことがわかります。 ※4
対象となる患者数が少ない
理学療法士や作業療法士と比べてリハビリの対象となる患者が少ないのも、 言語聴覚士が少ない理由の1つです。
理学療法士は主に、「立つ」「座る」「起き上がる」など基本的な体の動作に関するリハビリを担当します。作業療法士は、食事や入浴、着替えなどの応用的な動作や、こころの健康に関するリハビリの専門家です。どちらも病気や障害を抱える人だけでなく、怪我をした人もリハビリテーションの対象に含まれます。
一方で、「話す」「聞く」「食べる」の専門家である言語聴覚士の対象患者は聴覚や言語コミュニケーション、嚥下(飲み込む力)に問題を抱えている人に絞られます。このように理学療法士や作業療法士と比べて対象となる患者数がそもそも少ないのも、言語聴覚士の数がも少ない原因の一つです。
しかし、日本では高齢化が進んでいるため今後、嚥下障害や誤嚥、認知症などの患者は増えていくことが予想されます。
それにともない、嚥下障害や認知症による言語障害などに対応できる言語聴覚士の需要も増加すると考えられます。
言語聴覚士の需要
言語聴覚士は、言語コミュニケーションに関わる「話す」「聞く」「書く」の分野や、嚥下(飲みこむ力)のリハビリテーションを担当する職業です。
現在、全国的に言語聴覚士の需要が高い施設としては主に以下が挙げられます。
- 医療施設
- 福祉施設
- 教育機関
医療施設
言語聴覚士の需要が最も高いのは、病院やクリニックなどの医療機関です。
実際に日本言語聴覚士協会のデータでは、言語聴覚士の有資格者の約6割が医療機関に勤務していることがわかっています。
医療施設に勤務する言語聴覚士は主に、耳鼻咽喉科やリハビリテーション科、小児科などの診療科で活躍しています。主に、耳鼻咽喉科では難聴を、リハビリテーション科では嚥下障害や言語障害を、小児科では言語発達遅延や吃音、構音障害(発音障害)をそれぞれ専門に扱っています。
介護・福祉施設
医療機関に次いで言語聴覚士の需要が高いのは、介護や福祉の分野です。
日本言語聴覚士協会のデータでは、言語聴覚士の有資格者のうち介護分野(医療分野にまたがる施設を含む)に勤務している人の割合が約24%、福祉分野(医療分野にまたがる施設を含む)が7.2%となっています。
介護施設に勤務している言語聴覚士は、介護老人保健施設(老健)などの施設や訪問リハビリテーションなどで、利用者に対するリハビリテーションを行います。介護施設では、高齢者に対する嚥下(飲み込む力)に関する訓練がメインとなりますが、障害者福祉施設や小児療育センターでは利用者それぞれが抱える障害に応じて言語コミュニケーションに関する訓練も行います。
教育機関
小児分野においては学校や幼稚園などの教育機関も、言語聴覚士の活躍の場の1つです。
主に、学校内にある特別支援学級や、聴覚障害者や知的障害者を対象とする特別支援学校で、言語の習得や教育支援、集団生活への参加促進、その他機関への情報提供などを行っています。
言語聴覚士の将来性
資格が誕生した当初は、言語聴覚士の勤務先といえば医療機関のリハビリテーション科がメインでした。しかし、近年では介護保険法の改訂などにより、介護・福祉の分野で活躍している言語聴覚士が増えてきています。
また、以下のような観点からも、今後言語聴覚士の需要は増加すると考えられます。
- 摂食・嚥下障がいの訓練は言語聴覚士特有のスキル
- 少子化による需要の高まり
- 小児領域での活躍の拡大
摂食・嚥下障がいの訓練は言語聴覚士特有のスキル
言語聴覚士の仕事は、話す・聞くの訓練が主だと思われがちかもしれませんが、食べることに関しての訓練も、言語聴覚士の領域です。
食べる事は、人間が生きていくために必要不可欠であるため、それをサポートする専門家である言語聴覚士はとても稀有な存在です。
食べる事の訓練スキルは、医療機関や介護施設、福祉施設などで大いに役立つでしょう。
言語聴覚士の数が少ないからこそ、特有の訓練スキルは重宝されるので、有資格者数が大幅に増えない限り将来性はあると言えるのではないでしょうか。
少子高齢化による需要の高まり
日本は超高齢化社会に向かいつつあるので、摂食・嚥下障がいや、老人性難聴を抱える方が増えるかもしれません。
また、認知症などによりコミュニケーション障がいになる事もあるかもしれません。
そのため、介護や福祉施設、訪問リハビリテーションの求人が活発化することが予想されます。
このことも、言語聴覚士の将来性を示しています。
小児領域での活躍の拡大
近年、言語聴覚士が特別支援学校や言語障害児学級、言葉の教室などの教育機関で働くことが増えています。
また、発達障害の認知が広まったことにより、治療×教育=療育に関わる専門職として、障害を抱えている子どもたちの発達を支援する機会も増えています。
その他一般的な幼稚園や保育園でも、言語覚士を雇用したいと考えるところが増えてきているため、小児領域における言語聴覚士の活躍の場はどんどん広がりを見せているといえるでしょう。
これからの言語聴覚士に求められる事
 有資格者が少ないことから、言語聴覚士の将来性は明るいといえるかもしれませんが、ずっと活躍できるスキルを持つためにも、言語聴覚士として働き始めても、常に勉強する姿勢を持ち続けましょう。
有資格者が少ないことから、言語聴覚士の将来性は明るいといえるかもしれませんが、ずっと活躍できるスキルを持つためにも、言語聴覚士として働き始めても、常に勉強する姿勢を持ち続けましょう。
例えば、医学や医療は日進月歩なので、常に新しい知識をインプットするように心掛けたりするのが重要なのではないでしょうか。
また、言語聴覚士の仕事に正解はないので、常に患者さんに最適な訓練を提案できるように模索し続ける根気も必要なのではないでしょうか。
まとめ
言語聴覚士の将来性は、明るいと言っても過言ではないのではないかもしれません。
少なくとも、言語聴覚士として働く覚悟があれば、言語聴覚士になろうとする自分の将来性が閉ざされる事はないのではないでしょうか。
人助けをしたいと考えている方は、言語聴覚士を志してみても良いかもしれませんね。
言語聴覚士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の言語聴覚士科では、開校以来の国家試験の合格率は、91.3%!
高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
4年間で計画的に国家試験対策ができるようカリキュラムを組んでおり、無理なく資格取得をめざせます。
学年ごとの学習到達度に合わせた弱点科目の分析など、ひとりひとりの学びをきめ細かくサポートしています。
また卒業時には「大学卒業者と同等の学力を有する」として「高度専門士」の称号が附与されます。
4年制ならではの豊富な実習と基礎から段階的に学べるカリキュラムで、コミュニケーションの大切さや、その重要性を見つけ出せるような指導が受けられます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや言語聴覚士科の詳細情報をご覧ください。
また、言語聴覚士科の学科の詳細を知りたい方は「言語聴覚士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「患者さん一人ひとりに合った提案ができるよう、これからもチャレンジを続けていきたい」(2018年度卒業)
「担当したお子さんが少しずつ上手く話せるようになり、その場面をご家族とも一緒に共有できてとてもやりがいを感じた」(2018年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!