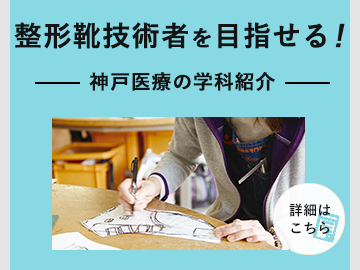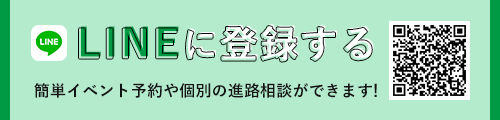「自分の足のサイズがない」「靴擦れをして足が痛い」
そんな既製品の靴に対する悩みを解消する、オーダーメイドの靴作りとは?
この記事では、「靴を自分で作ってみたい」という方や、靴職人を目指している人のために、靴作りに必要な知識と流れを解説。
今後、本格的に靴作りを勉強するための方法についても紹介していきます。
目次
良い靴を作るためには何の勉強が必要?

オーダーメイドの靴には、既製品にはない履きやすさ、そして歩きやすさが求められます。
そのように、快適な履き心地の靴を作るためには、一体何の勉強が必要なのでしょうか?
医学的知識
履きやすい・歩きやすい靴を作るためには、まずそれを履く人間のことについて詳しく知らなければなりません。
骨や筋肉、関節などの足のパーツを構成するパーツ、そして歩行時の状態変化などの人体の構造を知らなければ、より良い靴を考えることはできないからです。
このように足について、医学的な観点から論理的に学ぶことが、まずは良い靴を作るための第一歩です。
靴や靴作りに関する知識
もちろん、履きやすい・歩きやすい靴を作るためには、靴そのものや靴の作り方に関する知識も必要です。
革の知識
より良い靴を作るためには、素材選びが重要です。
靴といえばまず革素材が思いつきますが、一口に革といってもその種類は牛革や豚革などさまざま。
そしてさらに牛革はその中でも、生後何ヶ月かと、オスかメスかなど、使われている牛の年齢や性別によって特性が分かれます。
履く人の要望をかなえる靴を作るためには、靴に使われる革やその他の素材の特徴をきちんと把握しておかなければなりません。
採型のスキル
オーダーメイドの靴作りは、お客様の足に合わせて採寸・採型をするところから始まります。
お客様の足を正確に測ることができなければ、ぴったりとフィットする靴を作ることはできません。
このためより精巧な靴を作るためには、足の長さや幅、土踏まずの形など、足に関する情報を正確に採寸・採型できるスキルが必要です。
靴作りの流れ
ここまで、靴作りをするのに必要な知識について説明してきました。
それでは次に、実際の靴作りの流れを知ってイメージをふくらませましょう。
採寸
人の足にぴったりの靴を作るには、採寸が重要です。
つま先からのかかとまでの長さや足の幅、高さなどの基本的なデータはもちろん、左右差や歩き方の癖など、職人の目でお客さまの足をチェック。
そのほかにも直接悩みをヒアリングするなどして課題を発見し、より良い靴作りに必要なデータを多角的に集めていきます。
木型の製作
木型とは、靴のもとになる土台の型のことです。
お客さんの悩みを解消できる靴の形に、削ったり、パテで盛ったりして調整していきます。
靴の形やはき心地を大きく左右する工程ですので、作業はとても慎重に行われます。
製甲
木型を作ったら、それに合わせてまずは靴の上半分である、足の甲部分(アッパー)を作っていきます。
木型にそって、型紙(パターン)を作成。
それをもとにパーツとなる革を裁断していき、革専用の特殊ミシンでそれぞれを縫い合わせていきます。
つり込み
木型にアッパーをかぶせてシワをのばし、つま先やかかとの形をつくります。
底付け
底面に、ゴムや革などの素材でできた本底と呼ばれるパーツを取り付ける作業です。
圧着機で底を貼り付け、底の形を整えるためにグラインダーという機械で削ります。
仕上げ
いよいよ靴作りの最終工程。
木型から靴を外し、ゴミや汚れを落としてしっかり磨き上げます。
クリームや艶出しスプレーを使用して見栄えを美しく整えたら、靴の完成です!
靴作りを勉強する方法は?

靴作りに必要な知識や技術は、一朝一夕に身につくものではありません。
これから靴作りを学びたいという場合には、どのような勉強方法があるのでしょうか?
専門学校で学ぶ
靴作りを勉強したいなら、靴作りの専門学校に行くのが一番です。
日本の靴作りの専門学校は1年制〜2年制が一般的で、革靴の作り方などを基礎から学ぶことができます。
靴作りの本場であるヨーロッパで学びたいという人は、留学して、現地の専門学校に通うという選択肢もなくはありません。
しかし、言語の壁や生活環境を考えると、まずは国内の専門学校で靴作りの知識を身につけるのがおすすめ。
特に神戸医療専門学校なら、日本にいながら、ドイツの整形靴マイスターの指導が直接受けられますよ。
職人に弟子入りする
靴職人に見習いとして弟子入りし、働きながら靴作りを勉強するという方法もあります。
とはいえ国内外問わず、未経験で雇ってくれるところはほとんどありません。
このため、靴職人に弟子入りして靴作りを学びたいという場合は、靴の専門学校を卒業してから就職するのが現実的です。
自分で勉強する
twitterやInstagramなどのSNSをのぞいてみると、趣味で靴作りをしている人がいます。
こういった人たちの中には、ネットや書籍で得た情報をもとに、ゼロから独学で靴作りを勉強したという人も。
しかし今まで紹介した通り、靴作りにはさまざまな専門的な知識が必要なため、個人で学ぶには限界があります。
このためまずは趣味で靴作りをはじめてみたいという方は、手作り靴の教室や工房でイベントに参加するのもよいでしょう。
趣味ではなく、本格的に靴作りの勉強をしたいのであれば、やはり靴の専門学校で学ぶのがおすすめです。
まとめ
オーダーメイドの靴作りは、「足のサイズや形に合わない」「自分好みのデザインがない」など既製品に対する悩みを解消する特別な技術です。
このため靴作りには、革など靴に使われる素材全般の知識だけでなく、医学にもとづいた幅広い知識が必要。
個人で勉強するのは難しいので、本格的に学びたいのなら、靴の専門学校に通うのが一番です。
神戸医療福祉専門学校の整形靴科なら、靴作りの基礎から木型製作や足の疾患に合わせた靴製作など、応用的な技術を身につけることができますよ。
義肢装具士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の義肢装具士科では、国家試験の合格率は、2年連続で100%!(※2022~2023年度実績) 高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
義肢装具士養成校、日本で唯一の4年制専門学校で、最新技術&グローバルな学びで多彩な活躍を目指せます。
4年制独自のカリキュラムで、医学や工学の基礎知識から整形靴の本場であるヨーロッパでマイスターの国家資格を取得したヘルプスト先生より直接指導を受けられます。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや義肢装具士科の詳細情報をご覧ください。
また、義肢装具士科の学科の詳細を知りたい方は「義肢装具士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「患者さんの願いを叶えられるスペシャリストをこれからもめざしていきます。」(2017年度卒業)
「患者さんに本当に喜んでいただけた時、やりがいを感じます。」(2008年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!