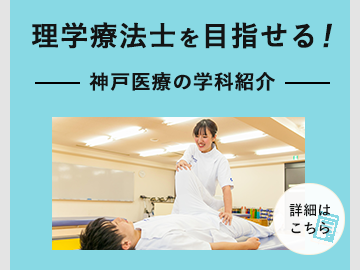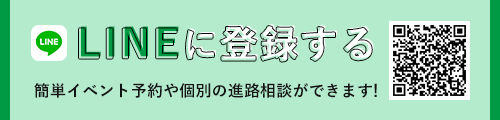理学療法士は、病気や怪我、加齢などによって身体機能が低下した方や、障害がある方に対して、日常生活を送る上で基本となる動作能力の回復や維持、または悪化の予防を目的としたリハビリテーションを行う専門職です。英語では「Physical Therapist」と呼ばれ、略して「PT」と称されることもあります。理学療法士は「動作の専門家」として、寝返る、起き上がる、座る、立つ、歩くといった基本動作の改善を目指します。具体的には、関節の可動域を広げたり、筋力を強化したり、麻痺の回復を促したり、痛みを軽減させるための運動療法や物理療法など、多岐にわたる治療法を用いて、患者さんが自立した日常生活を送れるよう支援します。
理学療法士によるリハビリテーションは医師の指示のもとで行われ、患者さん一人ひとりの状態を医学的・社会的な視点から評価し、最適なリハビリ計画を立てて実行します。近年では、高齢者の介護予防や健康増進、スポーツ分野での能力向上など、活躍の場がさらに広がっています。
目次
理学療法士が活躍出来る場所とは?
理学療法士は、医療機関の病院やクリニックだけでなく、介護老人保健施設や福祉施設など、多岐にわたる場所で活躍しています。
近年では、スポーツ分野でアスリートのサポートをする役割や、一般企業で社員の健康をサポートする役割も増えており、簡単にその活躍の場を説明することは難しいほどです。
それぞれの施設や分野で、理学療法士には異なる専門的な役割が求められます。
医療機関(病院・クリニックなど)
医療機関では、理学療法士が医師をはじめとする他の専門職と連携し、患者さんの身体機能回復をサポートしています。
特に病院やクリニックでは、脳神経外科、整形外科、内科、心臓外科など、多岐にわたる疾患の患者さんが理学療法の対象となります。
理学療法士は、患者さんの状態を正確に評価し、個別のリハビリテーション計画を立てて、運動療法や物理療法などを実施することで、その人らしい生活を取り戻すお手伝いをしています。
福祉施設(高齢者施設・障がい者施設など)
福祉施設では、理学療法士が高齢者や障がい者の自立を支援する重要な役割を担っています。
特に高齢者施設では、生活動作の維持・向上に向けたリハビリ訓練が中心です。
また、障がい者施設では、障がいの特性に応じた専門的な訓練や、日常生活に必要な動作の獲得を目指したリハビリが提供されます。
理学療法士は、これらの施設において、利用者の身体機能の回復だけでなく、精神的なサポートも行うなど、多岐にわたる役割を担っています。
スポーツトレーナーなどのスポーツ分野
理学療法士は、スポーツ分野においても重要な役割を担っています。
スポーツによる怪我からの競技復帰や再発予防のケアに携わるだけでなく、プロスポーツチームに帯同し、アスリートの健康管理やコンディション調整、スポーツ障害の予防など多岐にわたる役割を果たしています。
スポーツと医療の橋渡し役として、アスリートのパフォーマンス向上と長期的なキャリアをサポートする専門職です。
教育・研究機関(大学・専門学校など)
理学療法士は、大学や専門学校などの教育・研究機関で教員として活躍する道もあります。
教員として、将来の理学療法士を育成するだけでなく、理学療法に関する学術研究に携わることも重要な役割です。
特に大学教員を目指す場合は、修士以上の学位が求められることが多く、専門学校の教員であっても、理学療法士としての5年以上の実務経験が必要です。
授業や実習指導を通じて、学生に専門的な知識と技術を伝え、患者さんに寄り添う感性を持った理学療法士の養成に貢献します。
また、研究活動を通じて、より良い理学療法技術の確立や、理学療法全体の質の向上にも貢献しています。
一般企業(産業リハビリテーションなど)
理学療法士は、医療や介護分野で取得した専門資格を活かし、一般企業で活躍するケースも増えています。
例えば、医療機器や介護機器メーカーでは、理学療法士の視点から製品開発や効果判定に携わることができます。
また、ハウスメーカーでは、高齢者の身体機能に配慮したバリアフリー住宅の設計にアドバイスを行うなど、住環境整備の分野でも専門知識を発揮しています。
このように、産業リハビリテーションの一環として、企業の従業員の健康維持や増進に貢献することも可能です。
行政機関
理学療法士は、行政機関で働くことも可能です。
保健所や市町村の役所、児童相談所などで、福祉や介護に関する業務に従事します。
具体的には、地域住民への健康増進指導や相談業務、福祉用具の選定支援、介護予防のためのリハビリ指導などがあります。
また、特別支援学校では、障がいを持つ児童生徒の身体機能向上を目的としたリハビリテーション指導を行います。
行政機関で働く理学療法士は、地域全体の健康維持や生活の質の向上に貢献しています。
理学療法士の仕事内容とは?
理学療法士の仕事内容は、医師の指示に基づき、病気や事故、加齢などにより運動機能が低下した人々に対して、運動機能の回復を目的としたリハビリテーションを行うことです。
運動療法や物理療法を用いて、立つ、座る、歩くなどの基本的な動作能力の改善を支援します。
また、理学療法士は身体の構造に関するスペシャリストであり、スポーツ分野においても、スポーツ選手の怪我の予防や、怪我からの競技復帰に向けた運動機能の回復サポートについても専門的な知識や技術を提供しています。
リハビリを通じて患者さんの身体機能の回復を促し、その人らしい生活を送るためのサポートをする重要な役割を担っています。
検査測定・評価・記録
理学療法士は、まず患者さんの状態を正確に把握するため、筋力や関節可動域、バランス能力といった身体機能の検査測定を行います。
この結果を基に、個々の患者さんに最適な治療計画を立案し、リハビリを進めていきます。
リハビリの進行状況は常に記録し、定期的に評価することで、計画の見直しや調整を行い、より効果的な治療を目指します。
身体機能回復の訓練
理学療法士の主要な業務の一つである身体機能回復の訓練では、病気や事故による身体の障害や不自由を抱える方、あるいは加齢に伴い身体機能が低下した高齢者の方々に対し、運動機能の回復を目的としたリハビリテーションを実施します。
具体的には、医師の指示に基づき、寝返りや起き上がり、座る、立つ、歩くといった基本的な動作の改善を目指す運動療法や、温熱、寒冷、電気刺激などを利用する物理療法を組み合わせたアプローチが行われます。
患者さん一人ひとりの状態を詳細に評価し、個別性の高いリハビリテーション計画を立案し、その計画に沿って実践していくことが重要です。
例えば、脳卒中後の片麻痺患者さんに対しては、麻痺側の筋力強化とバランス訓練を集中的に行うことで、再び自力で歩けるようになることを目指します。
また、高齢者の転倒予防のために、下肢筋力やバランス能力を向上させる運動も効果的です。
これらの訓練を通じて、患者さんが日常生活をより円滑に送れるよう、身体機能の最大限の回復をサポートしていきます。
日常生活動作練習
理学療法士は、患者さんがベッドからの起き上がり、立ち上がり、歩行、階段昇降といった、日常生活において必要不可欠な動作を自力で行えるように支援します。
患者さんの身体機能の状態や目標に合わせて、段階的に難易度を調整しながら運動プログラムを作成し、実践していくことが重要です。
個々の能力に応じた適切な訓練を通じて、患者さんの生活動作の自立を目指します。この訓練は、日常生活の質を高める上で大変重要な役割を担っています。
住環境整備
理学療法士は、患者さんが退院後も自宅で安心して暮らせるよう、手すりの設置や段差の解消といった住環境の調整を提案することがあります。
患者さんの実際の生活動作を細かく評価し、その上で具体的なアドバイスや改修案を提供することで、転倒リスクの軽減や動作の負担を減らすサポートを行います。
この住環境整備は、単に物理的な改修だけでなく、患者さんのADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)の向上に深く関わる重要な業務です。
補装具の判定・調整
補装具の判定・調整について、理学療法士は患者さんの身体状態や活動レベルを評価し、適切な補装具の選定や身体への適合をサポートします。
必要に応じて作業療法士や義肢装具士といった専門職と連携し、患者さんが日常生活をより安全かつ快適に送れるよう、それぞれのニーズに合った補装具の提供を目指します。
これにより、患者さんの生活の質向上に貢献しています。
理学療法の主な手段とは?
理学療法における主な治療法は大きく3つに分けられます。
一つは運動療法で、関節可動域の拡大や筋力増強、歩行練習などにより運動機能の維持・改善を図る治療です。
次に、物理療法は、電気や温熱、光線などの物理的なエネルギーを用いて機能回復や痛みの軽減を目指す治療法になります。
そして、3つ目として、日常生活動作練習があり、患者さんの状態に合わせて着替えや入浴などの練習指導を行います。
理学療法士はこれらの治療を組み合わせて、患者さんの状態に最適なリハビリテーションを実施しています。
「運動療法」と「物理療法」とは?
理学療法は、運動療法と物理療法の2つの主要なアプローチに分類されます。
運動療法は、実際に身体を動かすことを通じて、関節可動域の改善や筋力回復を目指す治療法です。
例えば、脳卒中による麻痺や骨折、ヘルニアによって歩行が困難になった患者さんに対し、歩行訓練や筋力トレーニングなどを行います。
一方で物理療法は、温熱や寒冷、電気刺激、水治療、超音波、牽引などの物理的な刺激を外部から身体に加えることで、痛みや炎症の軽減、血行促進、組織の修復を促し、運動機能の回復を図る治療法です。
物理療法では薬物を使用せず、身体への負担が少ない点が特徴です。例えば、肩こりや腰痛の緩和、関節の炎症抑制などに用いられます。
これら2つの療法は、患者さんの状態や症状に応じて、単独で、または組み合わせて用いられることで、より効果的なリハビリテーションを実現しています。
実際に運動を行う「運動療法」
運動療法は、病気や怪我、加齢などによって低下した身体機能の回復を目指すための、理学療法における主要なアプローチの一つです。
この療法では、患者さん自身が積極的に運動を行うことで、関節の柔軟性や可動域の改善、筋力の強化、バランス能力の向上など、多岐にわたる効果が期待されます。
例えば、脳卒中による麻痺を持つ患者さんに対しては、麻痺した手足の機能回復を目指し、専門的なリハビリテーションが行われます。
また、骨折やヘルニアによって歩行が困難になった患者さんには、段階的な歩行訓練を通じて、日常生活における動作能力の再獲得をサポートします。
具体的には、ベッド上での寝返りや起き上がり訓練から始まり、立つ練習、そして歩行器や杖を使った歩行訓練へと進めていくことが一般的です。
これらの運動は、患者さんの身体状況や回復段階に合わせて個別に計画され、理学療法士の指導のもとで安全かつ効果的に実施されます。
運動療法は、身体機能の回復だけでなく、患者さんの自信や生活の質の向上にも大きく貢献する重要な治療法です。
物理的に外部から刺激を施す「物理療法」
物理療法とは、温熱、寒冷、電気刺激、水、光線、マッサージなど、様々な物理的なエネルギーを利用して、体の痛みや機能障害を改善する治療法です。
薬物を使用しないため、副作用の心配が少ないというメリットがあります。
例えば、温熱療法では、血行促進や筋肉の緊張緩和、痛みの軽減などが期待できます。
特に、慢性の腰痛や関節炎など、冷えが原因で症状が悪化しやすい疾患に有効です。
一方、寒冷療法は、急性期の炎症や腫れの抑制、痛みの緩和に効果を発揮します。
捻挫や打撲など、急性の外傷に対して用いられることが多いです。
電気刺激療法では、神経や筋肉に電気を流すことで、痛みの抑制や筋力回復、麻痺の改善を目指します。
低周波治療器や干渉電流型低周波治療器などが一般的に使われています。
これらの物理療法は、患者さんの症状や状態に合わせて、単独で、あるいは運動療法と組み合わせて実施されることが特徴です。
理学療法士は、それぞれの治療法が持つ効果や適用について深く理解し、患者さんにとって最適な物理療法を選択し、安全かつ効果的に実施する役割を担っています。
理学療法士のやりがいや魅力って?
理学療法士という職業は、患者さんの身体機能の回復を直接的に支援できるため、非常に大きなやりがいを感じられるでしょう。
患者さんが徐々に回復していく過程を間近で見守り、これまでできなかったことができるようになる瞬間に立ち会えるのは、理学療法士にとって何よりの喜びです。
例えば、脳卒中により歩行が困難だった方が再び自分の足で歩けるようになったり、スポーツ中の怪我で動かせなかった関節がスムーズに動くようになったりする様子は、理学療法士としての貢献を実感できる瞬間です。
また、理学療法士の魅力は、身体的なケアだけでなく、患者さんの心の支えにもなれる点にあります。
リハビリテーションは長期にわたることも多く、その過程で患者さんは精神的に不安定になることも少なくありません。
日々のコミュニケーションや励ましの言葉は、患者さんのモチベーション維持に繋がり、心の健康にも良い影響を与えます。
患者さんの不安を傾聴し、寄り添うことで、身体だけでなく心まで癒やすことができるのです。
このように、患者さんと深く関わり、感謝の言葉をいただけることは、理学療法士の仕事の大きなモチベーションとなります。
身体機能の回復をサポート出来る
理学療法士は、病気や怪我などによって身体機能が低下した患者に対し、運動療法や物理療法を用いて回復をサポートします。
患者さんが「できない」ことを「できる」に変えるため、一人ひとりの状態に合わせてリハビリ計画を立て、粘り強く支援することが求められます。
回復まで時間を要するケースもありますが、患者さんが自力で動けるようになった瞬間の喜びを共有できることは、理学療法士の大きなやりがいとなるでしょう。
また、患者さんの身体機能が回復することで、前向きな気持ちに変化していく姿を間近で見られることも、この仕事の魅力です。
心の支えになれる
理学療法士の役割は、患者様の身体機能回復だけでなく、精神的な支えとなることです。
病気や事故で身体が思うように動かせなくなり、精神的な苦痛を抱える患者様も少なくありません。
そのような状況で、地道なリハビリに取り組む患者様が前向きな気持ちを保てるよう、寄り添い、励ますことも大切な仕事です。
患者様が身体機能の回復に向けて希望を持てるよう、心のケアも行い、社会復帰を支援します。
感謝の言葉を頂ける
理学療法士として働く方々が特にやりがいを感じるのは、患者さんの回復を間近で見守り、直接感謝の言葉をいただける瞬間です。
患者さんがリハビリテーションを乗り越え、できなかったことができるようになった際に「ありがとう」と伝えられることは、大きな喜びと達成感につながります。
人の役に立ちたい、誰かに感謝される仕事がしたいという思いを持つ方にとって、理学療法士は非常に魅力的な職業と言えるでしょう。
理学療法士になるには?大学?専門学校?
理学療法士として働くためには、国家資格の取得が必須です。
この資格を取得するには、まず文部科学大臣または厚生労働大臣が指定する養成校で、3年以上必要な知識と技術を学ぶ必要があります。
大学や専門学校は養成校に該当し、どちらの施設でも理学療法士に必要な専門知識や技術を習得できます。
3年以上の修学を終えると、国家試験の受験資格が得られるのです。試験に合格することで、晴れて理学療法士の資格を取得できます。
【国家資格】理学療法士の取得方法とは?
理学療法士になるためには、まず文部科学大臣または厚生労働大臣が指定する養成校で3年以上学び、必要な知識と技能を習得する必要があります。
養成校には大学や専門学校があり、それぞれカリキュラムや取得できる学位が異なります。
いずれの学校を卒業しても、理学療法士国家試験の受験資格が得られます。
国家試験は毎年2月に実施され、合格することで理学療法士の資格を取得できます。
大学や専門学校など養成校に通う
養成校には4年制大学、3年制短期大学、専門学校(3年制または4年制)があり、これらの学校で必要な知識と技術を習得します。
3年制の学校では基礎的な知識と技術を効率よく学び、早期に資格を取得して現場で実践を積むことが可能です。
一方、4年制の学校ではより深く幅広い知識をじっくりと習得できるため、自身の目標や希望に合わせて選択することが重要です。
理学療法士の国家試験を受ける
理学療法士になるためには、まず国が指定する養成校で3年以上学び、必要な知識と技術を習得することが必須です。
その後、年に一度実施される国家試験の受験資格を得られます。
この国家試験に合格することで、理学療法士または作業療法士の国家資格を取得することが可能です。
専門知識と実践的なスキルを身につけ、国家資格を持つことで、患者さんのリハビリテーションをサポートする専門家として活躍できるようになります。
理学療法士と作業療法士の違いって?
理学療法士と作業療法士は、どちらもリハビリテーションに関わる国家資格であり、病院や施設で働くことが多く、混同されがちです。
しかし、この二つの職業には明確な違いがあります。
理学療法士とは、主に基本的な身体機能の回復を目的としたリハビリを行うのに対し、作業療法士は、応用的な日常生活動作の改善や、心身機能の維持・向上を目指します。
それぞれの資格の仕事内容について、ここから詳しく説明します。
理学療法士と言語聴覚士の違いって?
理学療法士は主に身体の基本的な機能回復に焦点を当てたリハビリを担当するのに対し、言語聴覚士はコミュニケーションや嚥下機能に特化したケアや訓練を行います。
言語聴覚士は、失語症や聴覚障害、発達の遅れ、認知症などにより、言葉や聴覚に問題を抱える方の治療や訓練、リハビリを担当します。
両者ともに患者さんの生活の質を高めるための重要なリハビリを提供しますが、その専門分野が異なります。
それぞれの専門性を活かし、患者さんの回復を多角的にサポートしているのです。
チーム医療~医療現場では多職種連携が必須~
医療現場では、医師の指示のもと、理学療法士をはじめとする多種多様な医療従事者が連携し、患者さんにとって最善の医療を提供しています。
このような「チーム医療」は、医療の高度化・複雑化が進む現代において、患者さんのニーズに応じた質の高いケアを実現するために不可欠です。
理学療法士は、運動や動作の専門家として、患者さんの身体機能回復を支援する重要な役割を担っています。
具体的には、患者さんの状態を詳細に観察・評価し、運動療法や物理療法を通じて起き上がり、寝返り、歩行といった基本的な動作能力の回復を目指します。
チーム医療において、理学療法士は他の職種と密接に連携します。
例えば、看護師に対しては褥瘡(じゃくそう)予防のための体位変換やポジショニングについて指導したり、患者さんの歩行を補助する際の適切な支え方を伝えたりすることがあります。
また、同じリハビリテーション専門職である作業療法士とは、患者さんの「社会復帰」という共通目標に向かって協力し、理学療法士が基本動作の回復を目指す一方で、作業療法士は買い物や料理といった応用的動作や社会生活への適応能力の回復をサポートします。
さらに、言語聴覚士と連携して嚥下機能や呼吸機能の改善をサポートすることもあります。
このように、理学療法士は自身の専門性を発揮しつつ、他職種と積極的に情報共有し、それぞれの強みを活かし合うことで、患者さんの早期回復や生活の質の向上に貢献しているのです。
多職種連携は、医療の質の向上だけでなく、医療従事者自身の視野や知識を広げ、より多角的な視点から問題解決に取り組むことを可能にするというメリットもあります。
まとめ~理学療法士とは?~
理学療法士は、病気や怪我、加齢などにより身体機能が低下した人々に対し、運動療法や物理療法を用いて機能回復をサポートする専門職です。
主に病院やクリニックなどの医療機関、介護老人保健施設や身体障がい者支援施設などの福祉施設、スポーツ分野、教育・研究機関など幅広い場所で活躍しています。
理学療法士になるには、文部科学大臣または厚生労働大臣が指定した養成校で3年以上学び、理学療法士国家試験に合格する必要があります。
国家資格である理学療法士は、医師の指示のもとで「立つ・座る・歩く」といった基本的な動作能力の回復を目的としたリハビリテーションを実施し、患者さんの社会復帰やQOL(Quality of Life:生活の質)の向上を支援する重要な役割を担っています。
理学療法士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
神戸医療福祉専門学校の理学療法士科では、開校以来の国家試験の合格率は、93.3%!(※2023年度実績)
高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
4年間で身につく学びとスキルを活かし、希望する就職先に合格するための国家試験対策を1年次からスタート。
個々の理解度を把握し個別指導を行うなど、しっかりとしたサポートで国家試験合格へバックアップします。
ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや理学療法士科の詳細情報をご覧ください。
また、理学療法士科の学科の詳細を知りたい方は「理学療法士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
卒業生の声
「回復には、信頼関係がいちばん。」(2017年度卒業)
「患者さんが元の生活に戻れるようにとリハビリテーションを行なっています。」(2017年度卒業)
「回復期のリハビリテーション病院で患者さんと関わっています。」(2013年度卒業)
「一般病棟と訪問看護ステーションで勤務。」(2013年度卒業)
心のケアを図る作業療法士も目指せます
理学療法士は身体機能が低下した患者様に対して、運動療法や物理療法のような治療法を利用し、身体のケアをするのが仕事です。これに対して、身体のケアに加えて心のケアまで行う「作業療法士」という仕事があります。
一見同じような仕事に見えますが、理学療法士と作業療法士では必要な知識や技術が異なるため、目指す職業に合わせて学べる学校・学科に進学しましょう。 神戸医療福祉専門学校は、理学療法士科とは別に作業療法士科を用意しています。身体や精神に障がいを持つ方が、いきいきとした生活を送るサポートをするための力を、4年をかけて身に付けていきます。
「時間をかけて専門的な知識や技術を確実に修得したい」
そんな方には、神戸医療福祉専門学校の作業療法士科をおすすめします。興味がある方は、ぜひ学校公式サイトの学科ページをご覧ください!
兵庫県唯一の4年制専門学校!神戸医療福祉専門学校 三田校 作業療法士科
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!
監修・運営者情報
| 監修・運営者 | <神戸医療福祉専門学校 三田校> 理学・作業・言語・救急・義肢 |
|---|---|
| 住所 | 〒669-1313 兵庫県三田市福島501-85 |
| お問い合わせ | 079-563-1222 |
| ホームページ | https://www.kmw.ac.jp/ |