
うつ病に対する治療法としては、休養や薬物療法、カウンセリングなどによる精神療法などがあります。
しかし、日本では海外ほどカウンセリングという選択肢が一般的でないため、その効果について少し懐疑的な方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、うつ病治療におけるカウンセリングの目的や効果を解説。
さらに、こころが弱っている人の力になりたいと考えている方に向けて、心理カウンセラーとして活躍できる資格についても紹介していきます。
目次
うつ病とは

うつ病とは、気分や感情がうまくコントロールできなくなり、心身に不調が現れる病気です。
うつ病となる原因はいまだに解明されていませんが、脳の神経伝達物質の減少や過度なストレス、環境の変化などによって発病すると考えられています。
ストレスに対する反応は個人差があるため、同じような状況で同じような出来事が起きても、それをストレスと感じる人もいれば感じない人もいます。
また、昇進や結婚、出産など喜ばしいことであっても、それが環境の変化としてストレスになり、うつ病を引き起こす人もいます。
このようにうつ病の引き金となる原因は人によってさまざまですが、うつ病になりやすい人の共通の特徴としては、真面目で責任感が強い、完璧主義などがあげられます。

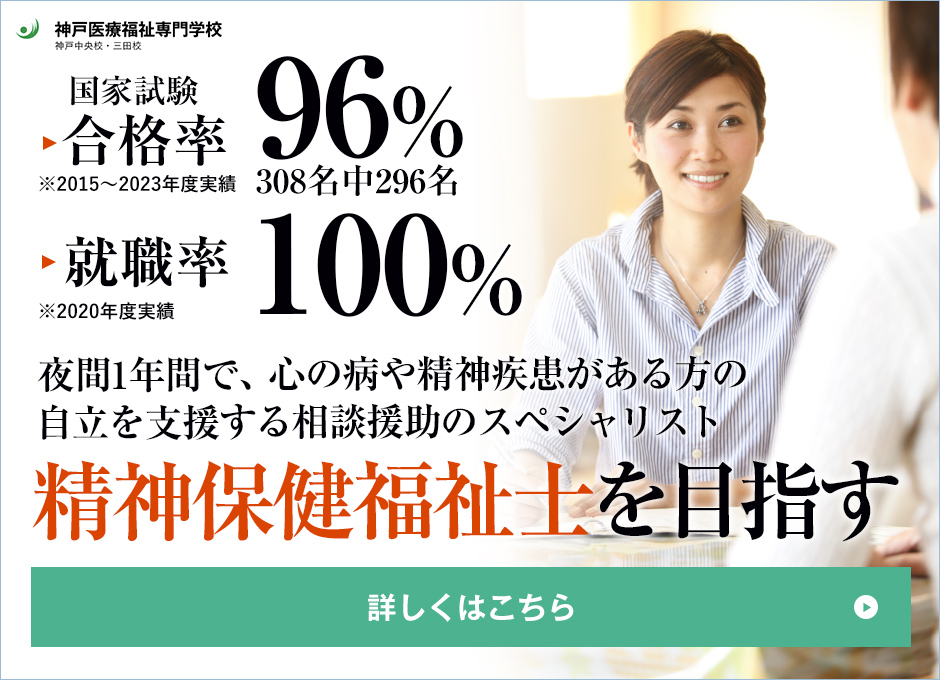
うつ病の症状
うつ病では主に、精神的な症状と身体的な症状の二つがあらわれます。
精神的な症状
うつ病になると脳の機能的なバランスが乱れ、気分の落ち込み(抑うつ気分)や意欲低下、思考力の低下などさまざまな精神症状があらわれます。
個人の性質や症状の進行具合によっても異なりますが、主なうつ病の精神症状は以下の通りです。
- 気分が落ち込む
- 口数が少なくなる
- 悲しい気持ちになる
- 焦燥感や不安感に襲われる
- 無関心になる
- 集中できない、ミスが増える
- イライラする
- 好きなことに対する興味がなくなる
- 喜んだり、楽しんだりできなくなる
身体的な症状
うつ病は以前までこころの病気だと考えられてきましたが、近年では脳の病気であるという考えが主流です。
このためうつ病は、気持ちの変化だけでなく、人によっては以下のような身体症状を発症することがあります。
- 食欲が低下する
- 動悸がする
- 疲れやすい、体がだるい
- 吐き気や下痢、便秘が続く
- 眠れない
- 物忘れが多くなる(記憶障害)
うつ病の治療法

うつ病は、治療しないと悪化して治りにくくなったり、社会生活に悪影響を及ぼしたりするため、早期に治療を開始することが重要です。
うつ病の治療法は大きく分けて、休養・環境調整、薬物療法、カウンセリングの3つがあります。
休養・環境調整
うつ病は脳にエネルギーが欠乏している状態ですから、まずは十分な休養をとることが大切です。
ストレスと距離をおいて、心と体をしっかりと休めることが治療の第一歩となります。
また、うつ状態を起こす原因や環境要因がはっきりしている場合は、そのストレスを軽減できるよう環境調整を行うことも有効です。
職場なら職種やポジション、勤務地を変更したり、家庭内なら家事の役割分担を見直したりすることで、身体的または精神的な負担を減らせるよう環境を調整します。
薬物療法
うつ病の治療は、抗うつ薬などの薬物療法が中心です。
現代日本で用いられている主な抗うつ薬には、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)などがあり、これらは「うつ病は脳の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリンなど)の減少が原因である」という仮説に基づいて開発されたものです。
そのほか抗うつ薬以外にも、患者さんの症状に合わせて抗不安薬や睡眠薬などが処方されます。
カウンセリング
心理カウンセラーなどの専門家によるカウンセリングも、うつ病の治療法の一つです。
精神療法にはさまざまな技法がありますが、うつ病の治療ではとくに認知行動療法が有効とされています。
認知行動療法とは、感情や気分に大きな影響を与える認知(物の受け取り方・とらえ方)に働きかけることで、ストレスの軽減や行動のコントロールを図る精神療法です。
患者さんとの対話を通して、しんどさを引き起こす原因となっている考え方や行動の癖を分析し、よりスムーズな日常生活を送れるよう修正していきます。

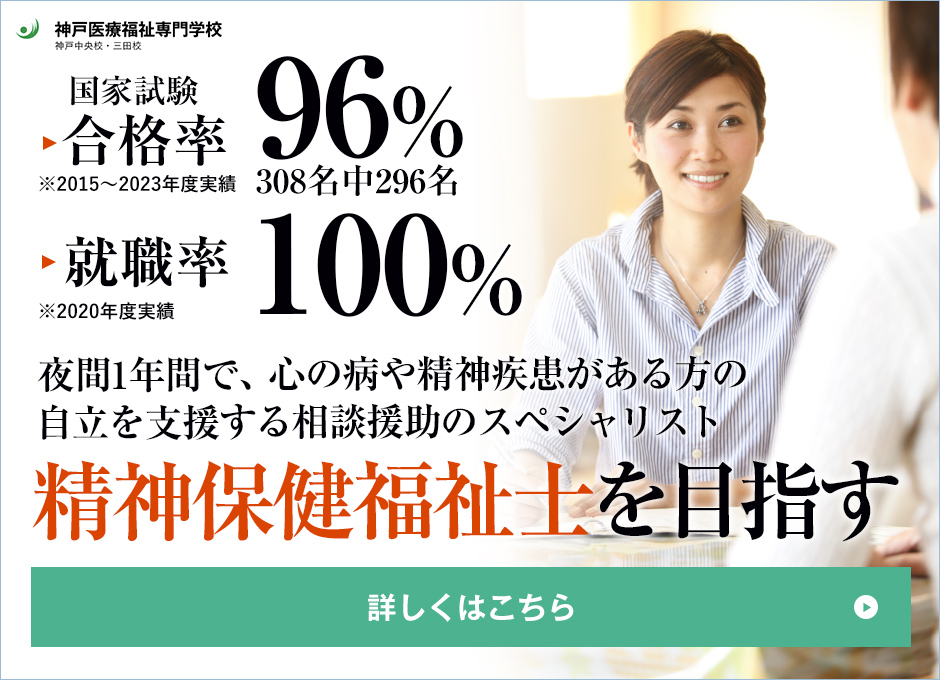
うつ病の治療でカウンセリングが選ばれるケースとは
うつ病治療では、主治医が必要であると判断した場合に心理カウンセラーによるカウンセリングが実施されます。
うつ病の治療でカウンセリングが選ばれるのは、以下のような場合です。
うつ病に心理的・社会的な問題が関係している
うつ病の治療でカウンセリングが適用される条件の一つが、うつ病になった原因に心理的・社会的な問題が関係していると考えられる場合です。
例えば仕事が原因でうつ病になってしまった場合、休養中は症状が改善したとしても、そのまま職場復帰するとまた同じようなことが起きて症状が悪化してしまう可能性が高いです。
そうならないよう、自分の性格や考え方、物事のとらえ方などを見直して修正していくことが、カウンセリングの大きな目的となります。
患者が自分で考えて話せる状態である
カウンセリングはカウンセラーとの対話によって成り立つものです。
したがって、患者が自分で考えて話せる状態であることもカウンセリングを受ける前提条件となります。
患者自身もカウンセリングを望んでいる
カウンセリングは、受ける人自身が主体的に取り組む姿勢がないとなかなか効果が得られません。
このため医師が「カウンセリングが必要」と判断しても、患者自身がその必要性を感じていなければ、カウンセリングが治療法として選択されないケースもあります。
うつ病に対するカウンセリングの効果
日本は海外に比べると、カウンセリングのような心理的支援がまだ広く浸透していません。
このため中には、カウンセリングは本当に効果があるのか疑問に思われている方や、どんな効果があるかよく知らないという方もいるかもしれませんね。
たしかに、十分な休養と適度な環境調整、薬物治療を組み合わせることでうつ病はかなり回復するといわれています。
しかし、もしうつ病になってしまった原因にその人自身の性格や考え方が大きく影響していると考えられる場合、それらを修正しないとまた何か別の出来事をきっかけにうつ病を発症してしまう可能性が高いです。
実際にうつ病は再発率が高い病気と言われており、厚生労働省によるとその再発率は60%前後。※
さらに再発を繰り返すたびに再発率も高くなるといわれています。
うつ病の治療だけでなく再発防止のためにも、カウンセリングで発症の原因を探り、思考パターンをよりよい方向へと修正することが重要です。
※ 厚生労働省 地域におけるうつ病対策検討会「うつ対応マニュアル-保健医療従事者のために-」(平成16年1月)「コラム・活動事例・資料編」の「資料1:うつ病について」

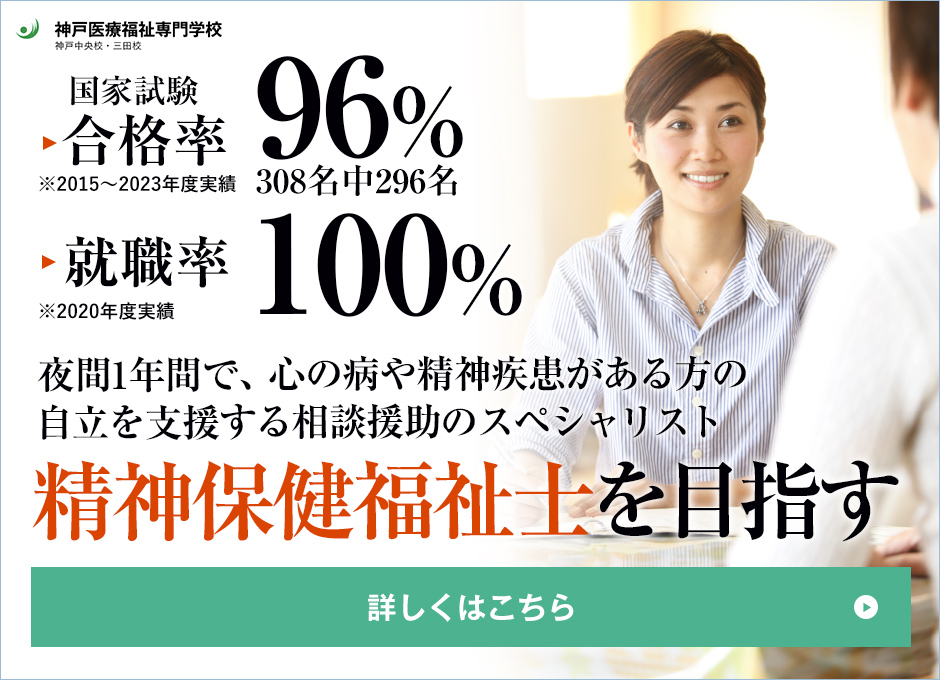
うつ病に対するカウンセリングに役立つ資格

うつ病に対するカウンセリングの意味や効果を知って、「自分も心理カウンセラーになってこころが弱っている人を助けたい」と思った方もいるのではないでしょうか?
そこで、ここからはうつ病に対するカウンセリングを行う心理カウンセラーを目指すのに役立つ資格を紹介します。
心理系の資格にはさまざまなものがありますが、そのなかでも信頼性の高い資格は臨床心理士と公認心理師の2つです。
公認心理師
公認心理師とは、2018年に新設された心理系の資格の中で唯一の国家資格です。
国家資格とは、その分野に関する知識と技術が一定水準あることを国から認められる資格であるため、社会的な信頼性はかなり高いといえます。
公認心理師の資格を取得することで、医療・福祉・教育現場などでカウンセラーとして働き、心に問題を抱えている人の相談援助や助言・指導、心の健康に関する教育や情報を提供などが可能になります。
臨床心理士
臨床心理士とは、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格です。
国家ではなく民間団体によって認定される資格ですが、1988年に誕生以来、心理系資格の中では最高峰と呼ばれるほど長い歴史と実績を誇っています。
心理学に関する専門的な知識と技術を有していることの証明となるため、公認心理師と同様、医療・福祉・教育現場などでカウンセラーとして活躍するのに役立つ資格です。
人の心を助ける職業に就きたいなら:精神保健福祉士もおすすめ

人の心を助ける職業に就きたいなら、心理カウンセラー以外に精神保健福祉士という選択肢もあります。
精神保健福祉士とは、精神に障害を抱えている方の自立した生活をサポートする職業です。
公認心理師と同様、心の支援に関係する国家資格で、社会復帰や利用可能な福祉サービスの情報提供など生活レベルでのサポートを行います。
神戸医療福祉専門学校 精神保健福祉士科は、そんな精神保健福祉士の資格取得が目指せる専門学校!
夜間一年間で、心の病や精神疾患がある方の自立を支援する相談援助のスペシャリストを目指すことが可能です。
直近8年間の国家試験の合格率は95%、就職率も100%という抜群の実績を誇っています。

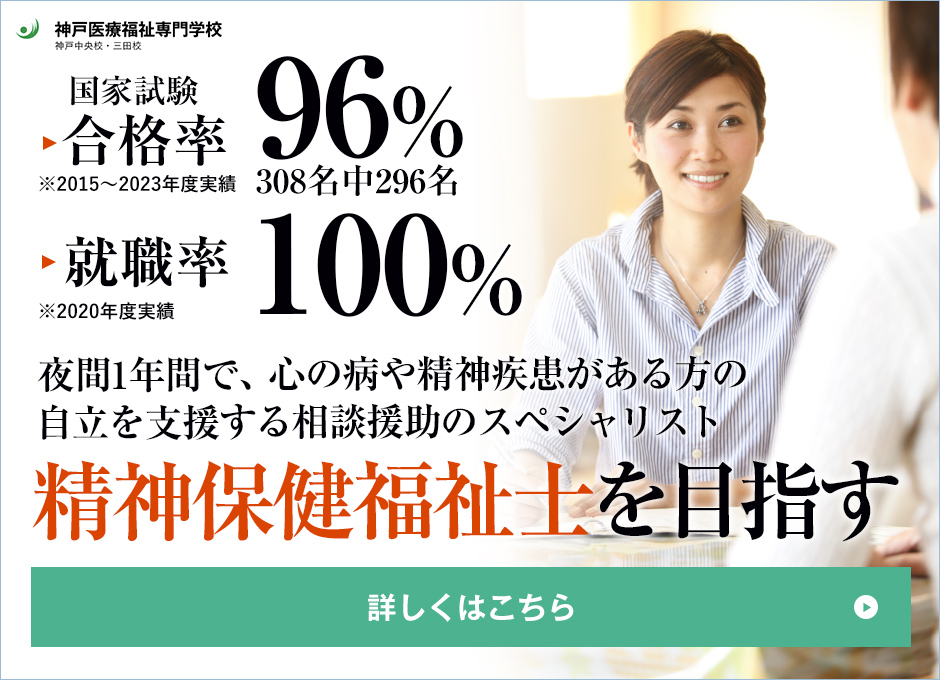
まとめ
うつ病治療におけるカウンセリングは、発症の原因を探るとともに、うつ病になりやすい偏った思考や行動を修正することで病気の再発を予防する役割があります。
うつ病治療におけるカウンセリングは、公認心理師や臨床心理士などの資格を有した心理カウンセラーによって行われるのが一般的です。
また、別の角度から心が弱っている人を支援する職業としては、精神保健福祉士があります。
精神保健福祉士とは、患者さんの心の問題の解決を図る心理カウンセラーとちがって、精神障がい者の方が抱える生活問題や社会問題の解決のために援助を行う仕事です。
人の心に寄り添う職業に就きたいと考えている方は、ぜひ選択肢の一つとして候補に入れてみてはいかがでしょうか。 神戸医療福祉専門学校の精神保健福祉士科では、国家試験の合格率は、96%!(※2015~2023年度実績) 通学制ならではの講義・演習・実習を組み合わせたカリキュラムで、夜間1年間で国家試験合格と、就職活動をサポートします。 ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや精神保健福祉士科の詳細情報をご覧ください。
精神保健福祉士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2020年度実績)
卒業生の声
「利用者さんの役に立てるよう学び続けていきたい。」(2013年度卒業)
「患者さんの暮らし全般を支えることができる。」(2011年度卒業)
「自分自身の成長を実感できる仕事。」(2010年度卒業)
「国家資格の取得を通して仕事の幅を広げる。」(2009年度卒業)
ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!




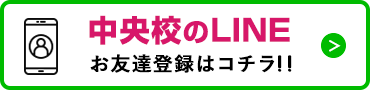

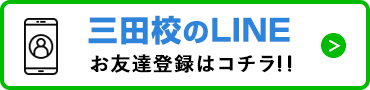
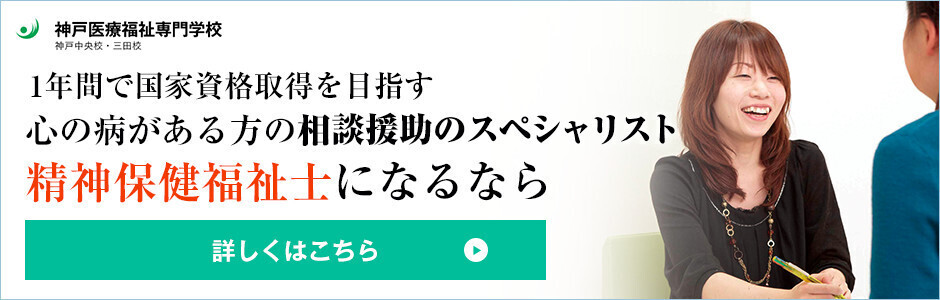
中央校