
食べること、飲むこと、話すこと。
普段、わたしたちが何気なくおこなっているこれらの口の働きは、日々のセルフケアによって支えられています。
このため加齢や病気、怪我などにより、じゅうぶんなケアができない状態が続くと、こういった口の機能が低下。
うまく食べたり、飲んだり、話したりすることができなくなって日常生活に支障が出るほか、人生の楽しみが奪われることにもつながります。
そこで今回は、そんなセルフケアが難しい要介護者のためにおこなう口腔ケアについて解説。
口腔ケアに関わる職業や主な観察項目、口腔ケアの基本的な手順について紹介します。
目次
口腔ケアとは
口腔ケアとは、口の中をキレイに保つために清掃をおこなったり、機能を維持・向上させるために口の体操などを行うことです。
口腔とは、口を大きく開けた時に見える空間を指し、具体的な部位としては歯や歯茎、顎骨や口蓋(口の中の天井部分)、唾液腺などが挙げられます。
口腔ケアの目的と内容
口腔ケアは、口腔内の健康保持と機能の維持・向上を目的としています。
代表的な口腔ケアの内容は以下のとおりです。
- 歯科検診
- 口腔の清掃
- 口周りの体操
- 歯茎のマッサージ
- 咀嚼や嚥下のトレーニング
- 口臭や口腔内の乾燥予防
口腔ケアの効果
口腔ケアには、歯周病などの感染症や口臭予防の効果があります。
また、歯や口の疾患だけでなく、誤嚥性肺炎などの全身疾患の予防にも効果があります。
口腔ケアの重要性
口腔ケアは病気予防だけでなく、健康づくりやQOLの向上という観点からも重要です。
口腔ケアによって、摂食・嚥下機能や味覚が改善されることはQOLの向上につながるほか、唾液の分泌が促進される、発熱のリスクが減少するなど健康上のメリットもあります。
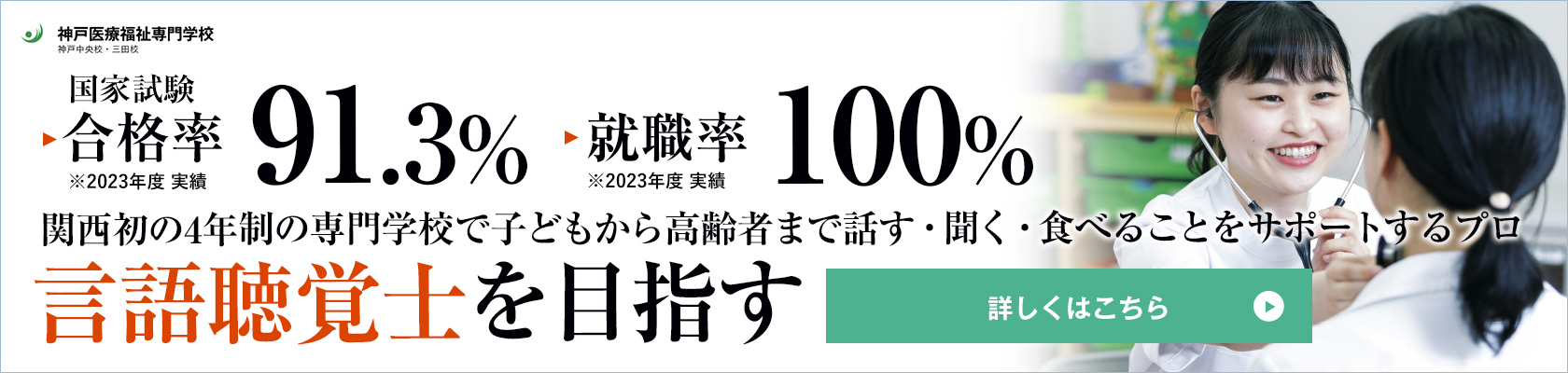

口腔ケアに関わる職業

口内の清掃というと、歯科医師や歯科衛生士などのイメージがありますが、寝たきり状態など要介護者の方の口腔ケアは、看護師や介護士、言語聴覚士などが担当することも多いです。
言語聴覚士とは、話す、聞くなどのコミュニケーションや、摂食・嚥下機能(食べる・飲み込む力)のリハビリテーションを行う職業です。
食べるために必要な筋力のトレーニングや、誤嚥してしまった時に食物を吐き出す訓練などと同様、摂食・嚥下機能に対するリハビリの一環として、口腔内の環境や機能の維持・向上を図る口腔ケアを担当します。
口腔ケアの種類
口腔ケアはその目的と方法によって、主に器質的口腔ケアと機能的口腔ケアの2つにわけられます。
器質的口腔ケア
清掃によって、口腔を清潔な状態に保つための口腔ケアです。
歯ブラシなどのケア用品を使って、歯や粘膜、舌などを掃除し、食物残滓(口の中に残った食べかす)や歯垢を除去します。
機能的口腔ケア
マッサージやトレーニングなどによって、口腔機能を維持・向上させるためのケアです。
摂食、嚥下、呼吸、発話など口腔が持っている機能を維持・向上できるよう、口の体操や摂食・嚥下訓練などをおこないます。
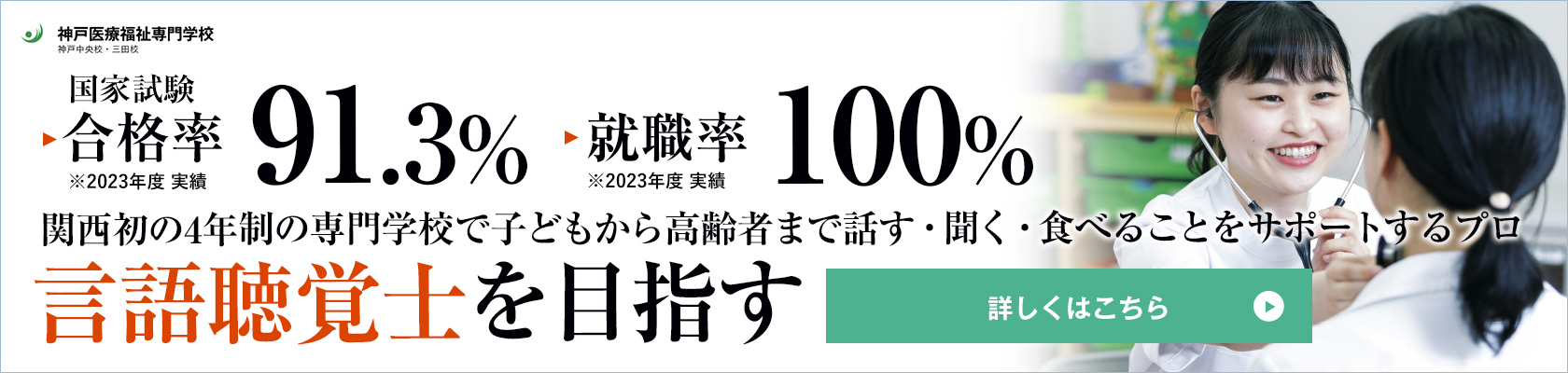

口腔観察の方法
口腔ケアの前には、口の問題・異常を発見するための口腔観察をおこないます。
要介護者が口を開けた状態を自分で維持できる場合は、そのままケアしても大丈夫か、異常がないか確認。
自力での維持が難しい場合は、口の端からやさしく指を入れて頬の内側を触り、反応を見ていきます。
口腔内が乾燥している場合、痛みを感じたり、出血したりすることがあるため、慎重に少しずつ触るようにしましょう。
口腔ケアの主な観察項目

口腔ケアをおこなう際は、事前のカウンセリングや引き継ぎなどで要介護者の基本情報を把握するとともに、口腔観察で口腔の状態を実際に確認することが重要です。
事前に把握しておくべき要介護者の基本情報と、口腔観察のときにチェックすべき具体的な観察項目は以下のとおりです。
-
<要介護者の基本情報>
- 残っている歯の本数
- 義歯の有無とその種類
- 口腔ケアの受け入れ意識
- うがいができるかどうか など
- 歯の汚れの箇所と程度
- 歯垢(プラーク)の箇所と程度
- 舌苔の箇所と程度
- 口臭の程度
- 乾燥状態
- 出血の有無
- 口内炎の有無
- う歯やぐらついている歯の有無
- 口腔ケアの受け入れ など
- 手袋
- 歯ブラシ
- 歯磨き粉
- コップ
- デンタルフロス
- 粘膜用ブラシ
- 舌ブラシ
- すい飲み
- のう盆(ガーグルベースン)
- ソフトガーゼ
- スポンジブラシ
- 口腔用ウェットティッシュ
- 口腔用綿棒
- 準備・説明
- うがい・水分保湿
- 入れ歯の清掃
- 粘膜の清掃
- 舌の清掃
- うがい・保湿薬の塗布
-
<観察項目>
継続して口腔ケアをおこなっている場合は、前回と比べて変化した点についても注意して観察する必要があります。
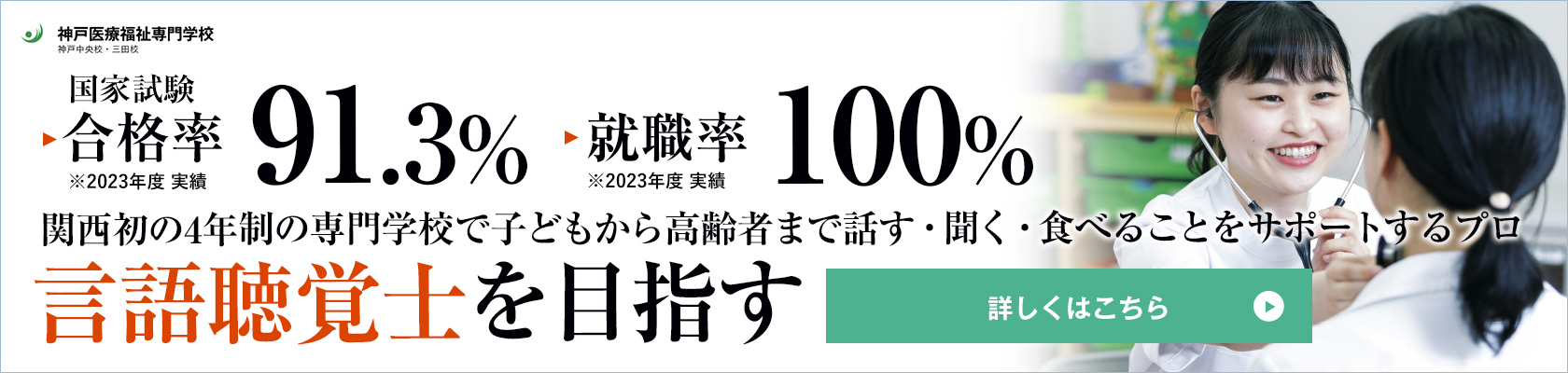

口腔観察の評価方法
適切な口腔ケアのためには、口腔観察で要介護者の状態を正しく分析・評価する(アセスメント)が重要です。
残存歯、舌、粘膜、残存歯、義歯、口腔清掃、歯痛などの項目について、口腔観察の結果をそれぞれ記録しましょう。
アセスメントを進めるにあたっては、多くの言語で翻訳されている要介護高齢者用の Oral Health Assessment Tool (OHAT)をはじめ、都道府県や病院、医療協会や医療法人などさまざまな団体が出している口腔アセスメントシートや口腔ケアマニュアルを活用すると便利です。
口腔ケアに必要なもの
口腔ケアに必要な道具は、主に以下のとおりです。
舌ブラシとは、舌に発生する舌苔(ぜったい)と呼ばれる汚れを取り除くための専用ブラシです。
すい飲みは寝たままの状態でうがいするのに、のう盆(ガーグルベースン)はその受け皿として使用します。
このほか、入れ歯がある場合は入れ歯専用歯ブラシ、舌苔が多い場合は口腔内保湿ジェルなど、症状に合わせて必要なものを用意します。
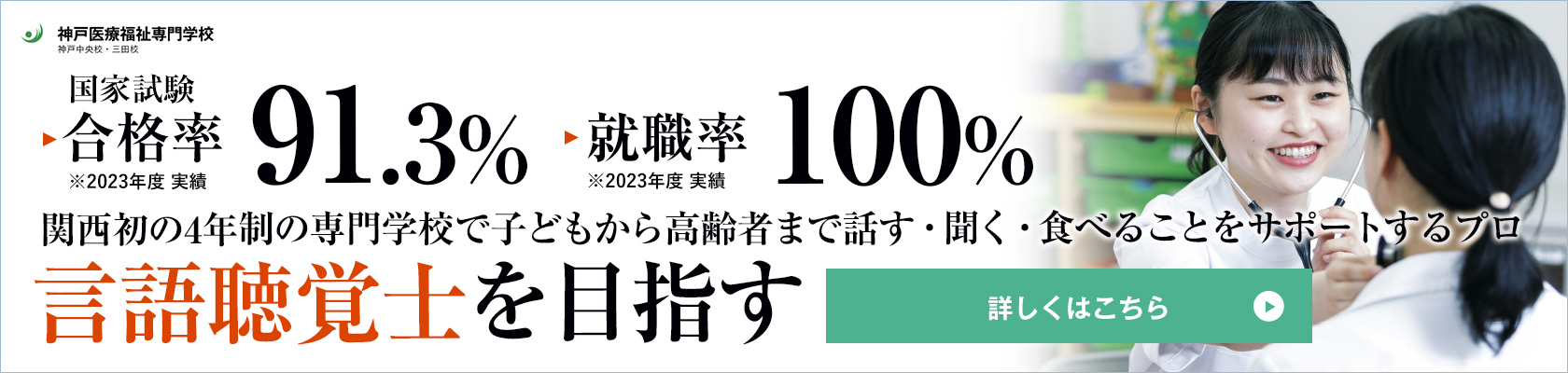

口腔ケアの基本的な手順

ここからは以下の6ステップにわけて、要介護者に対する口腔ケアの基本的な手順を紹介していきます。
準備・説明
口腔ケアの道具を準備するとともに、少しでも安心してもらえるようこれから行うケア内容や手順について説明します。
要介護者の同意が得られたら、頭を起こすなどして誤嚥を防ぐための体勢を整えましょう。
入れ歯や歯で手が傷つくと感染症を引き起こす可能性があるため、口腔ケアは必ず手袋をつけて実施します。
うがい・水分保湿
まずは、水でうがいをして食べ物のカスや汚れを簡単に落とします。
意識障害がない場合は、すい飲みで水を流し入れてうがいを促し、意識障害がない場合は、水を含んだスポンジで簡単に洗い流しましょう。
口内が乾燥している場合は、無理に口腔ケアをおこなうと出血の原因となるため、水を含ませたソフトガーゼやスポンジブラシなどで、唇や口腔内を少し湿らせます。
入れ歯の清掃
要介護者に入れ歯がある場合は、まずは入れ歯の清掃から始めます。
手で患者さんの顎を固定し、反対の手で入れ歯を外しましょう。
入れ歯は歯磨き粉で擦ると痛んでしまう可能性があるため、水でゆすいだり、濡れタオルで拭き取るなどして汚れを落とし、水または専用の消毒液で保管します。
歯磨き
入れ歯のお手入れが済んだら、次は歯を磨いていきます。
歯肉を傷つけないために上の歯は左回り、下の歯は右回りで磨き、前歯を磨くときはブラシ面を真横にしましょう。
歯の外側を磨くときは、人差し指を要介護者の頬に沿って入れ、口を広げるようにすると磨きやすいです。
粘膜の清掃
スポンジブラシや口腔用ウェットティッシュ、口腔用綿棒などで歯茎や頬の内側などの粘膜を清拭します。
デリケートな部分のため、優しくマッサージするようにおこなうようにしましょう。
舌の清掃
舌が汚れている場合、舌ブラシで優しく汚れを落とします。
口腔ケアが行き届いていない場合には、舌に白いコケ状の舌苔が付着している場合もあります。
舌苔とは、食べかすや粘膜のカスが付着してできたものです。免疫力の低下や消化器系の疾患などによって認められることもあります。
スポンジブラシや舌ブラシで、奥から前にやさしく擦り取るようにしましょう。
うがい・保湿薬の塗布
仕上げにうがいをして、残った汚れを落とします。
このときデンタルリンスやマウスウォッシュなどの洗口液を使用すると、口腔内の浄化や口臭予防に役立ちます。
最後に、唇や口の周り・口腔内の乾燥防止のために、必要に応じて保湿薬を塗布したら、口腔ケアは完了です。
まとめ
口腔ケアは、口の中がきれいになるだけでなく、口の快適な機能や嚥下機能の維持、免疫力の向上などさまざまなメリットがあります。
要介護者の状態や症状に合わせて必要なものを準備し、適切な方法でケアを継続しましょう。
神戸医療福祉専門学校 言語聴覚士科は、そんな口腔ケアを摂食嚥下訓練の一環として関わることができる言語聴覚士を目指せる専門学校です。
関西唯一の4年制の専門学校のため、無理なく段階的に言語聴覚士として活躍するのに必要な知識と技術を習得することが可能。
病院に限らず小児施設や介護施設、歯科医院などさまざま領域で卒業生も活躍しています。(※2021年実績)
興味がある方はぜひ、無料の資料請求やオープンキャンパスにご参加ください。
>>資料請求はこちら 神戸医療福祉専門学校の言語聴覚士科では、開校以来の国家試験の合格率は、91.3%! 4年間で計画的に国家試験対策ができるようカリキュラムを組んでおり、無理なく資格取得をめざせます。 また卒業時には「大学卒業者と同等の学力を有する」として「高度専門士」の称号が附与されます。 4年制ならではの豊富な実習と基礎から段階的に学べるカリキュラムで、コミュニケーションの大切さや、その重要性を見つけ出せるような指導が受けられます。 ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや言語聴覚士科の詳細情報をご覧ください。 「患者さん一人ひとりに合った提案ができるよう、これからもチャレンジを続けていきたい」(2018年度卒業) 「担当したお子さんが少しずつ上手く話せるようになり、その場面をご家族とも一緒に共有できてとてもやりがいを感じた」(2018年度卒業) ご興味がある方はぜひ以下のリンクより学校の詳細をご覧ください!
>>オープンキャンパス情報はこちら
言語聴覚士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
高い合格率に裏付けられ、希望者の就職率も100%に達しています。(※2022年度実績)
学年ごとの学習到達度に合わせた弱点科目の分析など、ひとりひとりの学びをきめ細かくサポートしています。
また、言語聴覚士科の学科の詳細を知りたい方は「言語聴覚士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。卒業生の声
監修・運営者情報
| 監修・運営者 | <神戸医療福祉専門学校 三田校> 理学・作業・言語・救急・義肢 |
|---|---|
| 住所 | 〒669-1313 兵庫県三田市福島501-85 |
| お問い合わせ | 0120-511-294 |
| 詳しくはこちら | https://www.kmw.ac.jp/ |




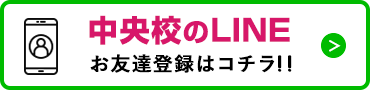

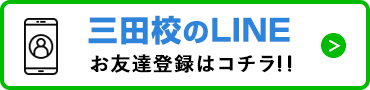

中央校