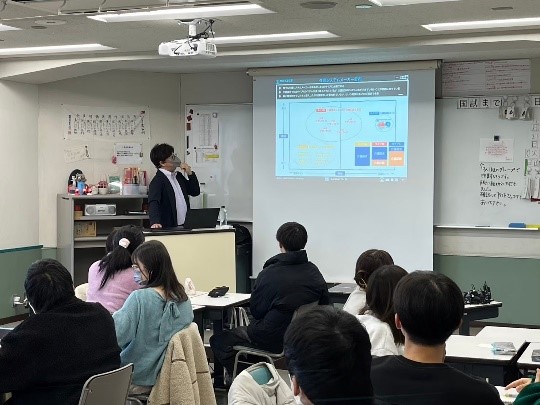みなさん、こんにちは。
神戸医療福祉専門学校中央校 介護福祉士科教員の粟内と申します。
本日は本学科の「9つの演習」より、ICT演習にて学ぶ「介護業界とICT」についてお伝えできればと思います。
「ICTってなんとなくパソコン使うのかな。」「ICTってなに?」という方もおられると思いますので、簡単に説明させて頂けたらと思います。
ICT(Information and Communication Technology)とは、情報通信技術の事を指します。具体的にはIT機器を用いて、情報の共有を図ったり、知識を共有することを指します。
介護福祉士の働く現場では、ICTを用いた動きが活発になっています。報酬面ではとりわけ、2021年に厚生労働省が打ち出した、科学的介護情報システム(LIFE)による新加算制度が注目されました。
では、具体的に現場ではどのような機器が導入されて、どのように役立っているのか見てみましょう。
〇記録のICT化によって、ペーパーレス化。客観的なデータ観測
介護現場で必須なのが記録です。サービス提供を行った証明になるものですから、毎日の記録は欠かせません。IT機器の導入によって、手書きから機器への入力へと変わります。
字が苦手な方でも、機器の入力であれば全く同じ字体で入力が可能です。音声での入力も可能ですので、直感的に入力する事もできます。また、大量の書類を保存することもなくなるので、書類を保管していた場所を有効に活用できます。
また、日常の記録だけでなく、例えば体重や身長、食事量、排せつの頻度やその有無などを記録し、データ化(グラフでの推移など)する事で、その方の傾向を客観的に知ることもできます。
〇眠りセンサーで睡眠状態の把握ができる。
眠りセンサーを導入する事で、睡眠時の状態が一目瞭然になります。入眠状態、心拍数、呼吸、床離床などが分かります。夜間帯に夜勤勤務者が各居室の見回りを行って、利用者の安全確認等を行いますが、こちらの眠りセンサーを導入する事で、より安全に配慮した見守りが可能になります。
〇介護ロボットの導入で介護負担を軽減できる。
介護技術の中でも、特にその方の身体的状況に応じた技術が必要になってくる「移乗介助」ですが、移乗方法を誤ってしまうと、利用者のケガに繋がったり、介助者の腰痛に繋がったりします。そこで、介護者向けに移乗特化したパワーアシスト機能を持ったロボットが開発、導入されています。こちらは介護者が一人で装着可能で、腰痛の予防に大変役立ちます。
また、100人以上の顔や名前を記録し、楽しくコミュニケーションを図ることのできる「パルロ」というロボットも登場しています。
これらの機器の導入によって、より質の高いケアを提供できたり、スムーズに情報共有を図れたりするのではないでしょうか。
現場でICTを活かせる介護福祉士を目指してみませんか。
神戸医療の介護福祉士科では、ICT以外にも福祉に関連する9つの分野の演習を学んで、自分の“強み”を活かした分野を2つ選択し、未来の福祉リーダーを目指します。
自分の得意なこととじっくり向き合って、応用力を身につけることで、将来の選択の幅を広げることができます。
ぜひ、福祉について一緒に学びましょう。
★介護福祉士科について詳しく知りたい方は→コチラ←
★介護福祉士科のオープンキャンパスは→コチラ←