みなさんこんにちは!神戸医療福祉専門学校三田校の大槻です。
今回のブログでは、3年生の学内実習の様子についてご紹介します。
言語聴覚士科3年生は、1月下旬からから2ヶ月間の実習を行っています。新型コロナウイルスの感染拡大防止として、学外の実習を学内に変更し、取り組んでいます。
3年生の実習では、患者さんへの接し方、身体やこころの状態確認、検査・訓練方法の選定、選定した検査・訓練の取り組みを中心に練習しました。
まずは、医学的な体調管理のスキルである、「脈拍測定」と「血圧測定」の練習を行いました。
2年生のときにチーム医療の実習の中で、救急救命士科の先生から学んだ測定方法の復習にもなりました。



正しい測り方がしっかり身についたことで、強みになりました!!これらの測定は、医療現場では基礎的なものになるので、スムーズに、そして初めての患者さんにも堂々とした手つきで取り組めるよう身に付けることができました。
次に、2人1組のペアになり、一人が患者さん役、もう一人が言語聴覚士役として検査や訓練を行う様子を全ペア見せ合いを行いました。

事前に先生から、患者さんの障がいの事例が伝えられ、その障がいはどんな症状なのか再確認をおこなうところから始めました。
言語聴覚士が関わることの多い、「失語症」「高次脳機能障害」「認知症」「記憶障害」が今回取り上げた障がいの例です。
これらの症状をより理解するため、各障がいの様子をまとめた映像も見ながら障がいの症状の理解を深めました。
〇●〇●〇●〇●〇●〇●
(ブログを読んでくださっている皆様に、具体的にどのような症状か一つ取り上げて解説いたします。)
失語症は、脳卒中などにより、大脳の言語中枢(脳の中でも、言語能力が集まっている最も大切なところ)が損傷を受け、「聞く」「話す」「読む」「書く」といった言語能力に障がいが起こること。
〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇
実際の検査や訓練を行っている医療現場通りの方法を想定し、別室で検査・訓練を行い、教室でそのリアルな映像を見ながら記録を残す練習をおこないました。
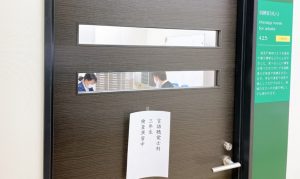

また、言語聴覚士は子どもと関わることもできるということから、小児に関わる実習も行いました。

実際に本校の附属施設である「ことばの相談室」で行っているオンラインでの小児訓練や検査の様子の見学を行いました。
*
実習は、2ヶ月間おこないました。本来なら学外実習であるところ、学内実習になったということで、実際の患者さんと関わるということができませんでしたが、今回の経験を4年生の実習、そして就職し働いていくときの糧として頑張って欲しいと思います!
実際に実習を行った3年生からは、「学内実習だったからこそ」仲間と一緒に言語聴覚士について深く学ぶことができた という声がありました◎
最後は、みんなで使用してきた場所を掃除をし、

先生からのお言葉を聞いて、

終了です!
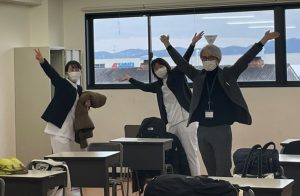
みなさん、2ヶ月間本当にお疲れ様でした!!


