
社会福祉士と精神保健福祉士は、どちらも福祉に関する相談援助系の国家資格です。
仕事内容や資格取得の流れなど共通する部分も多い両者ですが、どちらかの資格を保有しているともう一方の資格も取得しやすくなるのでしょうか?
そこでこの記事では、精神保健福祉士が社会福祉士になる方法、そして社会福祉士が精神保健福祉士になる方法を中心に両者の違いや資格の取得方法について解説します。
どちらかの資格取得を検討している方や、すでにどちらか一方の資格を保有しているという方はぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
社会福祉士と精神保健福祉士の違い
社会福祉士と精神保健福祉士はどちらも福祉の相談業務に関する国家資格です。
両方とも福祉のサポートを必要とする人の生活支援や、相談に応じて助言・指導をおこなうのが主な仕事ですが、 支援の対象者や活躍する場所などに違いがあります。
まず、それぞれの職種の概要は以下のとおりです。
社会福祉士とは
社会福祉士とは、ソーシャルワーカー(SW:Social Worker)とも呼ばれる社会福祉の専門職です。
身体的・精神的・経済的にハンディキャップを抱えている人がスムーズに日常生活を送れるよう、相談に乗ったり、必要な支援サービスにつなげたりします。
精神保健福祉士とは
精神保健福祉士とは、精神障がい者やこころの病気を抱えている人に対して援助を行う専門職です。
社会福祉士と異なり、精神的にハンディキャップを抱えている人を対象とします。
精神障がいがある人とその家族の相談に乗ったり、必要な支援サービスにつなげたりするほか、就労に必要な訓練や就職活動のサポートを行うなど、社会復帰を支援するのも精神保健福祉士の仕事です。
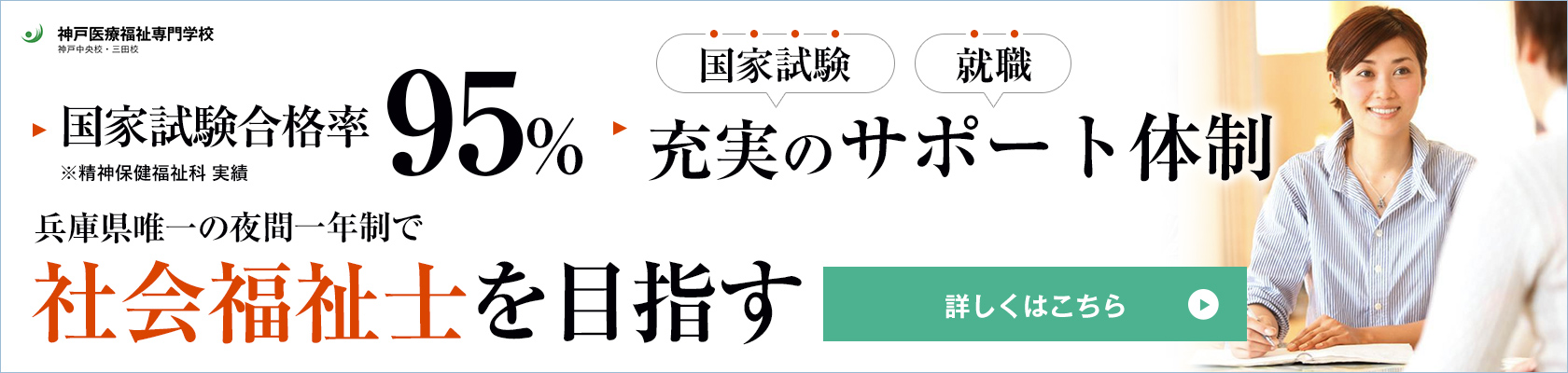

社会福祉士と精神保健福祉士の違い①資格(国家試験)
社会福祉士と精神保健福祉士は、別の国家資格です。
社会福祉士の資格は、1987年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて誕生し、精神保健福祉士の資格は1997年の精神保健福祉法によって誕生しました。
社会福祉士・精神保健福祉士になるには、一定の受験資格を満たしたうえで、それぞれ社会福祉士国家試験または精神保健福祉士国家試験に合格する必要があります。
社会福祉士国家試験
社会福祉士の国家試験は、年1回、毎年2月上旬に行われます。
試験地は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県の24ヶ所。
午前の部・午後の部と1日かけて試験が行われ、その科目は以下のとおりです。
<午前>
- 医学概論
- 心理学と心理的支援
- 社会学と社会システム
- 社会福祉の原理と政策
- 社会保障
- 権利擁護を支える法制度
- 地域福祉と包括的支援体制
- 障害者福祉
- 刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職
- ソーシャルワークの理論と方法
- 社会福祉調査の基礎
<午後>
- 高齢者福祉
- 児童・家庭福祉
- 貧困に対する支援
- 保健医療と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
- ソーシャルワークの理論と方法(専門)
- 福祉サービスの組織と経営
参照:[社会福祉士国家試験]試験概要|社会福祉振興・試験センター
令和6年2月4日に実施された試験の受験者数は3万4,539人。
合格者数は2万50人となっており、合格率は58.1%です。
一見高い合格率のように見えますが、前年にあたる令和5年の合格率は44.2%、そしてさらにその前年の令和4年の合格率は31.1%であることを考えると、油断せず気を引き締めて勉強する必要があるといえるでしょう。
精神保健福祉士国家試験
精神保健福祉士の国家試験は年1回、毎年1月下旬〜2月上旬頃行われます。
試験地は、北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県の7ヶ所。
社会福祉士国家試験と同様、午前の部・午後の部にわけて試験が行われ、その科目は以下のとおりです。
<午前>
- 精神医学と精神医療
- 現代の精神保健の課題と支援
- 精神保健福祉の原理
- ソーシャルワークの理論と方法(専門)
- 精神障害リハビリテーション論
- 精神保健福祉制度論
<午後>
- 医学概論
- 心理学と心理的支援
- 社会学と社会システム
- 社会福祉の原理と政策
- 社会保障
- 権利擁護を支える法制度
- 地域福祉と包括的支援体制
- 障害者福祉
- 刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職
- ソーシャルワークの理論と方法
- 社会福祉調査の基礎
参照:[精神保健福祉士国家試験]試験概要|社会福祉振興・試験センター
令和6年2月3日・4日に実施された試験の受験者数は6,978人。
合格者数は4,911人となっており、合格率は70.4%です。
過去5年間の合格率は60%〜70%を推移しており、これは社会福祉士国家試験より高い合格率といえます。
ただし、どの受験者もしっかり準備して臨んだ結果であることを考えると、抜かりない試験対策が必要です。
社会福祉士と精神保健福祉士の違い②支援の対象者と仕事内容
社会福祉士と精神保健福祉士は、どちらも福祉のサポートを必要とする人の生活支援や、相談に応じた助言・指導を行うことが主な仕事ですが、 支援の対象者や具体的な業務内容には違いがあります。
社会福祉士は、精神的・身体的に障がいを持つ方だけでなく、高齢者や1人親家庭、低所得者など幅広い人を対象に、相談業務や支援サービスの手続き、各関係機関との連絡・調整を行います。
それに対して精神保健福祉士は、精神障がいやこころの病気を抱えている人に特化して援助を行う専門職です。
相談業務や各関係機関との連絡・調整などは社会福祉士と共通する仕事内容ですが、それ以外にも日常生活を送るための訓練、就労支援など社会復帰に向けたサポートも行います。
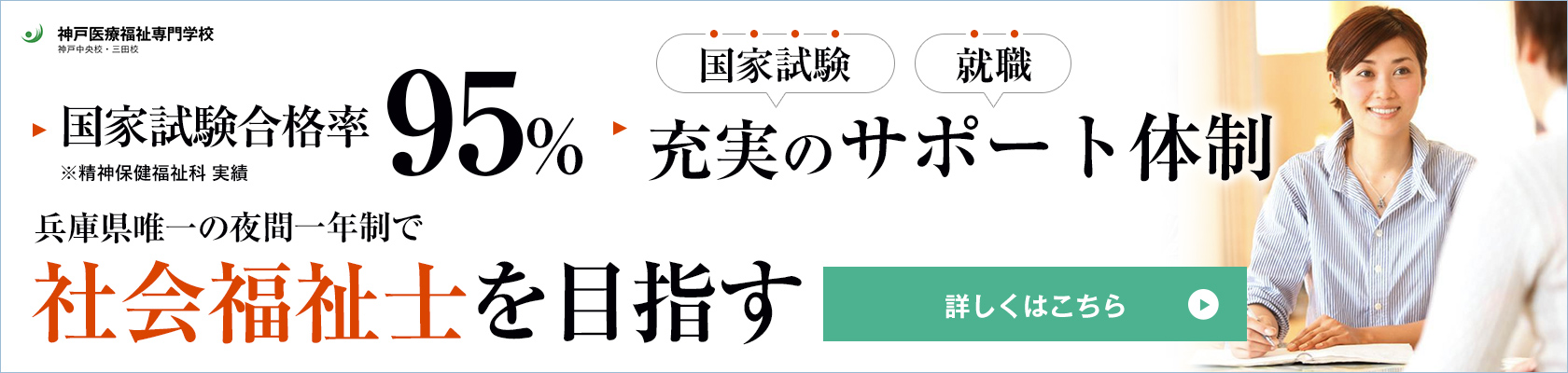

社会福祉士と精神保健福祉士の違い③活躍している場所
支援の対象者が異なるということは、活躍する場所にも違いがあるということです。
精神保健福祉士は、主に精神科や心療内科のクリニックなどの医療機関で活躍し、生活の援助や日常生活を送るための訓練を行っています。
また、就労継続支援事業所、地域活動支援センターなどの精神障害者福祉施設で働いている精神保健福祉士は、就労に関するトレーニングなど社会復帰の支援が仕事です。
それに対して社会福祉士は、支援対象者が幅広いことから就職先も豊富なのが特徴です。
もっとも活躍しているのは、高齢者を対象としている高齢者福祉の現場ですが、それ以外にも障がい者福祉や児童・母子支援、医療機関などさまざまな分野で福祉のエキスパートとして活躍しています。
社会福祉士の主な就職先5つを紹介!職種や支援の対象、仕事内容の違い
社会福祉士になる方法

社会福祉全般のスペシャリストである社会福祉士を目指すには、一定の要件を満たした上で社会福祉士国家試験を受験し、合格する必要があります。
社会福祉士の国家試験の受験資格を満たすためのルートは、主に以下の3つにわかれます。
- 指定科目ルート
- 基礎科目+短期養成施設ルート
- 一般養成施設ルート
基本的に、①の指定科目ルート以外を選択した場合は、社会福祉士の養成施設に通学し、必要に応じた実務経験を積む必要があります。
養成施設のなかには夜間制や通信制のところもあるため、そういった大学や専門学校を選べば社会人からでも社会福祉士を目指すことが可能です。
社会人から社会福祉士を目指すには?通信制のメリット・デメリットを解説
指定科目ルート
福祉系の大学や短大などで指定科目を履修している場合のルートです。
福祉系大学を卒業した場合は、卒業後すぐに社会福祉士国家試験を受験することが可能。
福祉系の短大などで指定科目を履修した場合は卒業後、3年制の短大の場合は1年、2年制の短大の場合は2年の相談援助の実務経験を積むことで受験資格が得られます。
基礎科目+短期養成施設ルート
福祉系の大学や短大などで基礎科目を履修している場合のルートです。
福祉系大学を卒業した場合は、卒業後短期養成施設などに6ヶ月以上通学することで、社会福祉士国家試験の受験資格を得ることが可能。
福祉系の短大などで基礎科目を履修した場合は、指定科目ルートと同様、3年制の場合は1年、2年制の場合は2年の実務経験を積んだ後、短期養成施設などに6ヶ月以上通学することで受験資格が得られます。
一般養成施設ルート
一般の大学や短大などを卒業した場合のルートです。
4年制の一般大学の場合は卒業後、一般養成施設などに1年以上通学することで、社会福祉士国家試験の受験資格を得ることが可能。
一般の短大などを卒業した場合は、3年制の場合は1年、2年制の場合は2年の実務経験を積んだ後、一般養成施設などに1年以上通学することで受験資格が得られます。
また、大学や短大などを卒業していない場合は、4年の実務経験を積んだ後、一般養成施設などに1年以上通学することで受験資格を得ることができます。
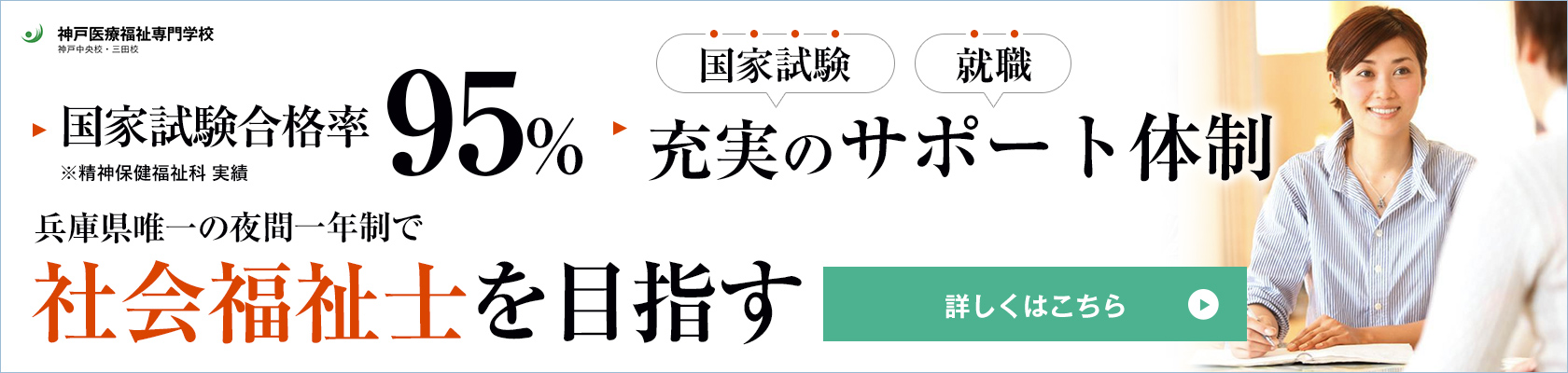

精神保健福祉士になる方法

精神保健福祉士は、精神疾患やこころの病気を抱える方を支援するスペシャリストです。
精神保健福祉士になるには社会福祉士と同様、一定の要件を満たした上で精神保健福祉士国家試験を受験し、合格する必要があります。
精神保健福祉士の国家試験の受験資格を満たすためのルートは、主に以下の3つにわかれます。
- 指定科目ルート
- 基礎科目+短期養成施設ルート
- 一般養成施設ルート
指定科目ルート
福祉系の大学や短大などで指定科目を履修している場合のルートです。
福祉系大学を卒業した場合は、卒業後すぐに精神保健福祉士国家試験を受験することが可能。
福祉系の短大などで指定科目を履修した場合は、3年制の短大を卒業した場合は1年、2年制の短大を卒業した場合は2年の相談援助の実務経験を積むことで受験資格が得られます。
基礎科目+短期養成施設ルート
福祉系の大学や短大などで基礎科目を履修している場合のルートです。
福祉系大学の場合は卒業後、短期養成施設などに6ヶ月以上通学することで、精神保健福祉士国家試験の受験資格を得ることが可能。
福祉系の短大などで基礎科目を履修した場合は、指定科目ルートと同様、3年制の場合は1年、2年制の場合は2年の実務経験を積んだ後、短期養成施設などに6ヶ月以上通学することで受験資格が得られます。
一般養成施設ルート
一般の大学や短大などを卒業した場合のルートです。
4年制の一般大学の場合は卒業後、一般養成施設などに1年以上通学することで、精神保健福祉士国家試験の受験資格を得ることが可能。
一般の短大などを卒業した場合は、3年制の場合は1年、2年制の場合は2年の実務経験を積んだ後、一般養成施設などに1年以上通学することで受験資格が得られます。
また、大学や短大などを卒業していない場合は4年の実務経験を積んだ後、一般養成施設などに1年以上通学することで受験資格を得ることができます。
精神保健福祉士から社会福祉士になるには
こうして見比べてみると、社会福祉士と精神保健福祉士はどちらも国家資格を取得するまでの流れはほぼ同じ。
しかし、履修が必要な科目は異なるため、どちらかの資格取得者がもう一方の資格取得を目指す場合は、あらためて受験資格を確認し、国家試験に臨む必要があります。
まずは、一定の実務経験を積む、短期養成施設や大学に通うなど、自分に合った方法で受験資格を満たしましょう。
また、精神保健福祉士と社会福祉士の国家試験では、以下の出題分野が共通科目となっています。
- 医学概論
- 心理学と心理的支援
- 社会学と社会システム
- 社会福祉の原理と政策
- 社会保障
- 権利擁護を支える法制度
- 地域福祉と包括的支援体制
- 障害者福祉
- 刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職
- ソーシャルワークの理論と方法
- 社会福祉調査の基礎
参照:[精神保健福祉士国家試験]よくあるご質問|社会福祉振興・試験センター
精神保健福祉士の資格を持っている人が社会福祉士国家試験を受験する場合は、受験申請の際にその登録証のコピーを提出することで上記科目が免除となります。
ただし、社会福祉士の専門科目である以下の分野については受験が必要です。
- 社会調査の基礎
- 相談援助の基盤と専門職
- 相談援助の理論と方法
- 福祉サービスの組織と経営
- 高齢者に対する支援と介護保険制度
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
- 児童虐待やひとり親家庭の援、児童福祉法などに関する知識
- 就労支援サービス
- 更生保護制度
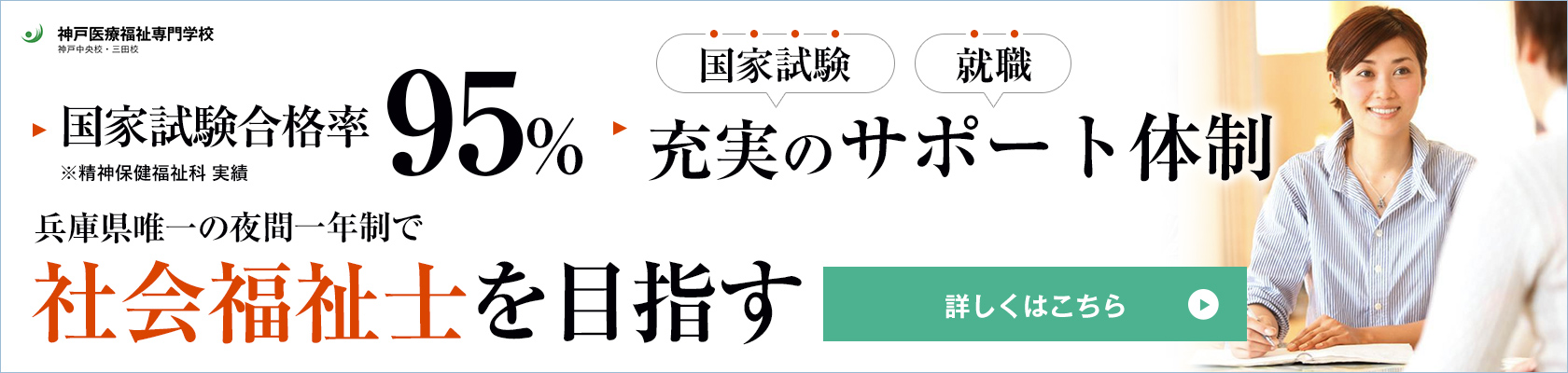

社会福祉士から精神保健福祉士になるには
社会福祉士の資格を持っている人が精神保健福祉士の資格取得を目指す場合も、自分に合った方法で受験資格を満たし、精神保健福祉士国家試験に臨む必要があります。
精神保健福祉士が社会福祉士国家試験を受けるとき同様、共通科目が免除されますが、精神保健福祉士の専門科目である以下の分野については受験が必要です。
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
- 精神疾患とその治療
- 精神保健の課題と支援
- 精神保健福祉・相談援助の基盤
- 精神保健福祉の理論と相談援助の展開
- 精神保健福祉に関する制度とサービス
- 精神障害者の生活支援システム
参照:第26回精神保健福祉士国家試験を実施します|厚生労働省
社会福祉士と精神保健福祉士の同時受験は可能?
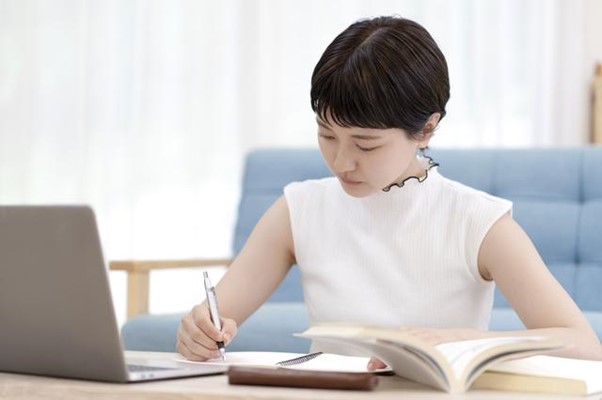
理論上は、 双方に必要な科目を履修できる大学に通うことで 、精神保健福祉士と社会福祉士の同時受験は可能です。
しかし、対応できる大学が限られている、履修しなければならない科目が多い、かなりの勉強量が必要になるなどの理由からそのハードルは非常に高いといえます。
このためまずは社会福祉士と精神保健福祉士、どちらか興味がある方を目指し、国家試験を受験。
その後必要があれば、もう一つの資格取得を検討することをおすすめします。
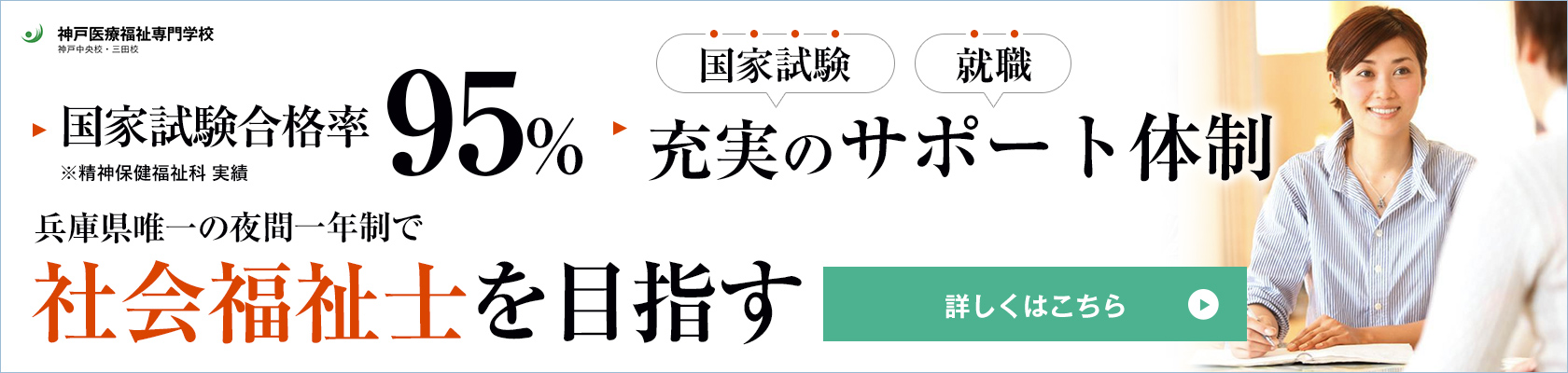

社会福祉士と精神保健福祉士、どちらを目指すか迷ったら?
どちらも福祉の専門家であり、仕事内容や試験科目など共通部分も多い社会福祉士と精神保健福祉士。
相談援助業務に興味がある方のなかには、どちらを目指すか迷っているという人も多いでしょう。
将来自分がどのように活躍したいか、どんな人の力になりたいかを考えることが職業選びのポイントです。
子どもから高齢者まで、幅広く困っている人たちを助けたいなら社会福祉士、精神疾患やこころの病気を抱えている人の力になりたいなら精神保健福祉士など、自分にとってより興味がある仕事内容や、働いている様子をイメージしやすい方を選択するとよいでしょう。
社会福祉士・精神保健福祉士のダブルライセンス
福祉のエキスパートとして活躍したい場合は、社会福祉士と精神保健福祉士のダブルライセンスがおすすめです。
社会福祉の相談業務に関する2つの国家資格を取得することで、対象者をわけることなく専門性の高い支援が可能となります。
ダブルライセンスを目指す方法
先述したように、理論上は精神保健福祉士・社会福祉士の同時受験は可能です。
具体的には社会福祉士と精神保健福祉士に必要な単位をすべて修得できる4年制大学に入学すれば、2つの受験資格取得が同時に目指せるでしょう。
また、すでにいずれかの資格をすでに保有している場合は、以下の共通科目が国家試験で免除されます。
- 医学概論
- 心理学と心理的支援
- 社会学と社会システム
- 社会福祉の原理と政策
- 社会保障
- 権利擁護を支える法制度
- 地域福祉と包括的支援体制
- 障害者福祉
- 刑事司法と福祉
- ソーシャルワークの基盤と専門職
- ソーシャルワークの理論と方法
- 社会福祉調査の基礎
参照:[精神保健福祉士国家試験]よくあるご質問|社会福祉振興・試験センター
このようにすでにどちらかの資格を持っていると、上記のように12科目が免除され、専門科目のみを受験すればよくなるためもう一方の資格も取得しやすくなります。
ダブルライセンスを取得するメリット
社会福祉士と精神保健福祉士、両方の資格を保有していると、福祉のエキスパートとしてより高度な知識と技術で幅広い対象者を支援することが可能になります。
また、社会福祉士と精神保健福祉士、どちらの求人にも応募できるようになるため、就職先や転職先の幅が広がります。
両方の資格を保有していること自体が社会福祉に関して高度なスキルを持っている証明になるため、採用にも有利に働くことが期待できるでしょう。
ダブルライセンスを取得するときの注意点
社会福祉士・精神保健福祉士のダブルライセンスを目指すには、時間や費用がかかります。
特に同時受験の場合は、両方の実習をこなす必要があるほか、試験対策も2倍です。
すでに社会福祉士と精神保健福祉士のダブルライセンスで活躍している人のなかには、「焦って同時に両方取得する必要はなかった」と感じている人もいます。
神戸医療福祉専門学校 中央校の精神保健福祉士科と社会福祉士科は、夜間1年でそれぞれの資格取得が目指せます。
平日の授業時間は18時10分〜のため、仕事帰りでも通学可能。つまり、より優先度の高い資格を先に取得し、少し落ち着いてからもう一方の学科で資格取得を目指すというのも1つの選択肢です。
無理なく夢を追えるよう、自分にとって最適なキャリアプランを考えてみてくださいね。
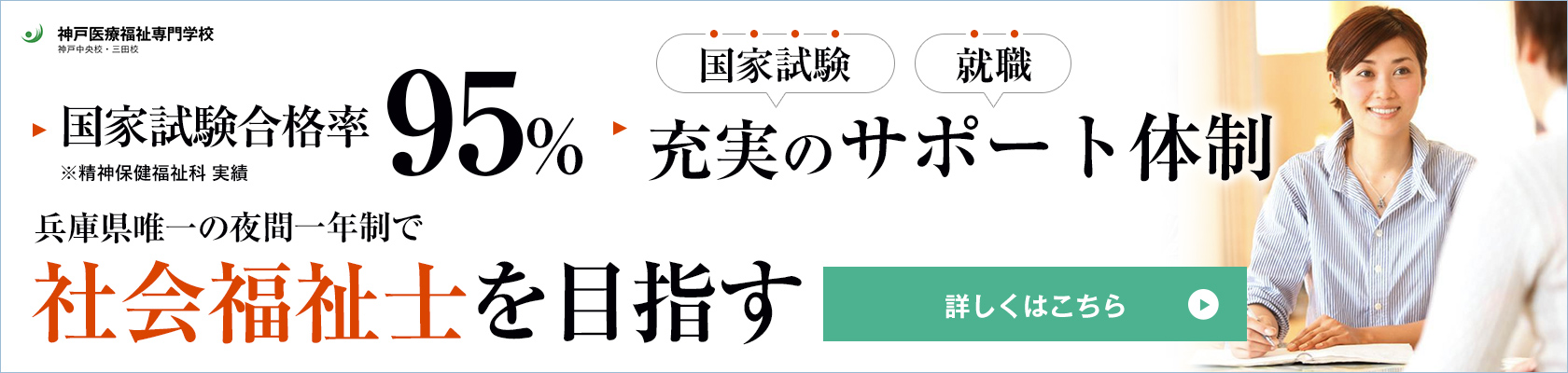

まとめ
精神保健福祉士と社会福祉士は、同じ福祉に関する相談援助系の国家資格ですが、それぞれを目指すのに履修すべき専門科目は異なります。
このため精神保健福祉士から社会福祉士、または社会福祉士を目指す場合は、あらためて受験資格を見直したうえで、国家試験の受験が必要です。
ただし、共通科目については免除となるため、その点においては有利といえるでしょう。
神戸医療福祉専門学校 中央校 社会福祉士科は、1年で社会福祉士の受験資格が取得できる専門学校です。
夜間制で授業時間は基本的に18時10分〜のため、日中は仕事で忙しい社会人の方でも無理なく通学できます。
また、同じく夜間1年で精神保健福祉士の受験資格が取得できる精神保健福祉士科も併設しているため、精神保健福祉士から社会福祉士だけでなく、社会福祉士から精神保健福祉士を目指すことも可能です。
まずはぜひお気軽にオープンキャンパスにお越しください。
>>資料請求はこちら 神戸医療福祉専門学校の社会福祉士科では、夜間1年でスクールソーシャルワーカーはもちろん、その他医療や福祉の現場でソーシャルワーカーとして幅広く活躍できる社会福祉士の資格取得が目指せます。 夜間制で授業時間は基本的に18時10分〜のため、日中は仕事で忙しい社会人の方でも無理なく通学できます。 ご興味がある方は、ぜひ以下のオープンキャンパスや社会福祉士科の詳細情報をご覧ください。
>>オープンキャンパスはこちら
社会福祉士を目指すなら神戸医療福祉専門学校で学びませんか?
また、社会福祉士科の学科の詳細を知りたい方は「社会福祉士を目指す専門学校」でご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。
監修・運営者情報
| 監修・運営者 | <神戸医療福祉専門学校 中央校> 鍼灸・介護・精神 |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-6-3 |
| お問い合わせ | 078-362-1294 |
| 詳しくはこちら | https://www.kmw.ac.jp/ |




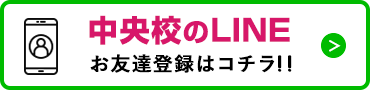

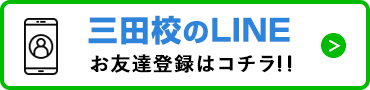
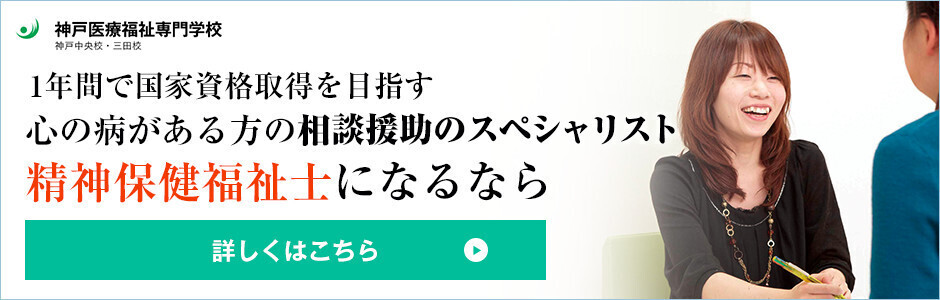
中央校