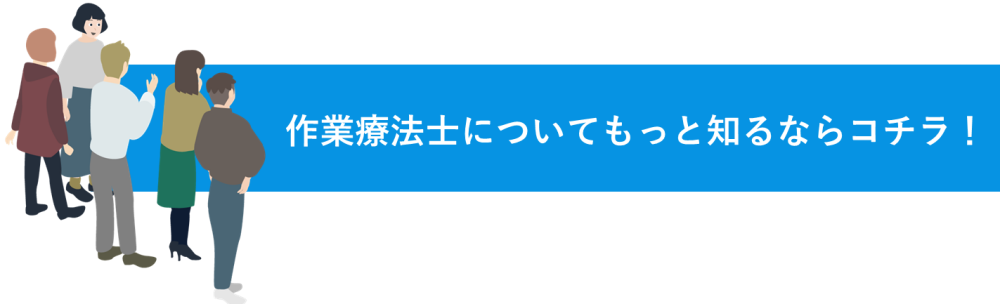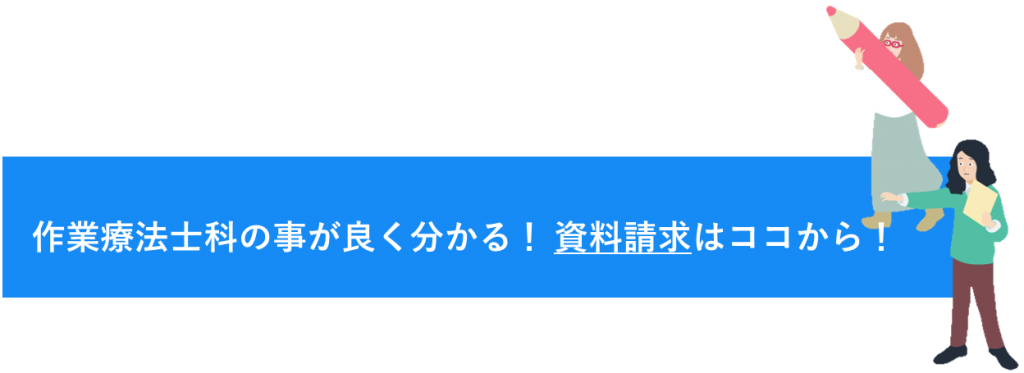こんにちは!
作業療法士科教員の大塚です。
実は作業療法士も行う、脈拍と血圧測定!
これを読んでいる方は、脈拍と血圧の測定をしてもらった事はあるでしょうか?
「脈拍と血圧測定って作業療法士に関係あるの?」と思った方もいるかもしれませんね。
実は、脈拍と血圧測定って作業療法士にとても関係があります!
脈拍や血圧を測るのは、リハビリ前が主ですが、時にはリハビリ中やリハビリ後にもする事も……。
それぞれのタイミングで行う測定には下の様な意味があります。
・リハビリ前
患者さんの状態を知るため。
患者さんは普通だと思っていても、実は体調が悪かった!という場合もあるので測定を行います。
状態が悪い時にはリハビリは行いません。
・リハビリ中
患者さんの状態が変化した時や、激しい動きのリハビリをした時等に行います。
時にはリハビリを頑張りすぎて、休まないといけないのに「大丈夫」という患者さんも。
また、リハビリ中に体調が変わる場合も。
そんな時はリハビリを中断して、脈拍と血圧を測定し患者さんの状態を把握します。
・リハビリ後
リハビリを行ってからの状態を知るため。
リハビリをしてから、体調に変化がないかを知らべます。
このタイミングであまりよくない数値が出た場合は、リハビリをもっと軽いものにしたり調整する目安にも。
この様に、作業療法士にとってもとても大切な事なんですね。
脈拍と血圧を測定する授業があるのは、作業療法評価学総論!
1年生の時に、この脈拍と血圧の測定についての授業を行います。
まずは脈拍と血圧測定の手順について講義を受けた後、
実際に測定で触れる動脈を教科書や資料で確認しながら、
「橈骨動脈でどこ?💦」
「上腕動脈ってここ?🤔」

とお互いの身体を使って確認していきます。
血圧計や聴診器など、測定で使用する各器具の名称から、その使用方法についても実際に確認しながら体験を進めていきます。
脈拍と血圧測定は学外実習や医療現場でも高頻度で行われます。
そのため、男女を含めて人を変えながら、繰り返し学習していくのです。