皆さんこんにちは!
神戸医療福祉専門学校三田校の大槻です🤗
今回は、吹奏楽部生の皆さんに送る、「進路選択応援!ブログ」をお届けします🎺

吹奏楽部生になぜ限定して送っているのかというと!?
「言語聴覚士」というお仕事は、吹奏楽で培った力が発揮できるということと、現在ブログを記載している私が元 大阪桐蔭高等学校の吹奏楽部生ということもあり、吹奏楽部生に少しでも進路選択の為になる記事を送りたい!と思い、お届けしています。
早速本題です!
みなさんは、「言語聴覚士」という職業を聞いたことはありますか??

言語聴覚士は、子どもからお年寄りまで人生の喜びに寄り添うお仕事です。
・・・人生の喜びとはどういうことでしょうか??
皆さんも自身の生活を振り返ってみながら考えてみてください。
好きな物を食べること、音楽を聴くこと、お友達とお話しをすること、好きな本や雑誌を読むこと・・・
これらの「食べる」「聞く」「話す」ということは、日々の生活で必ず必要なことであり、楽しいと思える大きなツールであると思います。

皆さんは、「食べる」「聞く」「話す」ということが、突然できなくなるとどう思いますか?
・好きな音楽を聴くことが出来なくなる
・演奏の仕方を仲間と共有することが出来なくなる
・本番の打ち上げでみんなと一緒におやつを食べる事ができなくなる
これらは、とても辛いことだと思います。
言語聴覚士が携わる患者さんは、
「今までお話しが出来ていたけれど脳の障がいによってうまく話すことが出来なくなった方」
「聴覚の障がいがあることで、聞こえが不十分な方」
「歯や舌はあるのに飲み込むことが出来ず、好きなものを食べることが出来ない方」
などがいらっしゃいます。このような方々の「出来なくなったこと」を「出来るようにする」ためのリハビリテーションを言語聴覚士が行うのです。

では、実際に言語聴覚士はどのような訓練を行うのでしょうか?
先ほどの例にあげた「今までお話しが出来ていたけれど脳の障がいによってうまく話すことが出来なくなった方」に対しては、音楽を通して訓練を行うこともあります。
頭で思っている言葉がでにくい方は、歌に乗せるとことばが出やすいこともあるため、歌を取り入れています。

また、発声の障がい=声がかすれてガラガラ声になる方に対しては、音階を広げる訓練を行います。声の高さを確認するため、キーボードを用いて行い、ボイストレーニングも行います。
このように、音楽を取り入れた訓練をしていくことを実はあまり知られていない言語聴覚士。
今回のブログを通して、是非言語聴覚士の仕事に興味を持ってもらえたら嬉しいです♪
また、患者さん自身がリハビリテーションの目標として、「また音楽ができる(歌える)生活を取り戻したい」という想いは、音楽をしてきた人であればとても共感でき、患者さんのリハビリテーションを支えることが出来ると思います。
是非、音楽をしてきた経験で患者さんを支えられる言語聴覚士を目指してみませんか?
≪言語聴覚士科の先生から楽器演奏上達のためのアドバイス≫
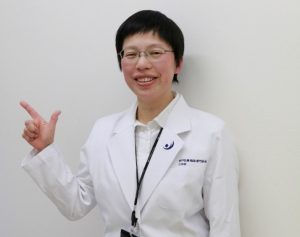
テーマ:自分らしい音色を出そう
演奏で音色を決めるのは楽器の材質と形です。それでは、演奏者独自の音色は出せないのでしょうか?
答えは、「出せます。」音の立ち上がりと処理の仕方で音色は変わります。
音の立ち上がりと処理は何に左右されるでしょうか。管楽器なら吹く息、弦楽器ならボーイングです。
楽器に息を安定供給できれば、また、楽器に吹き込む息の量を思い通りに変化させることができれば、音色も自由自在に変化させることができるのです。その呼気をコントロールするのは肺の動きに関わる筋肉です。
詰まるところ、個性ある音色、自分が追及する音色での表現のためには、腹筋運動が有効なのです。
↑コンクールが忙しくなる前に是非参加してみてね!音楽トークしましょう♪


